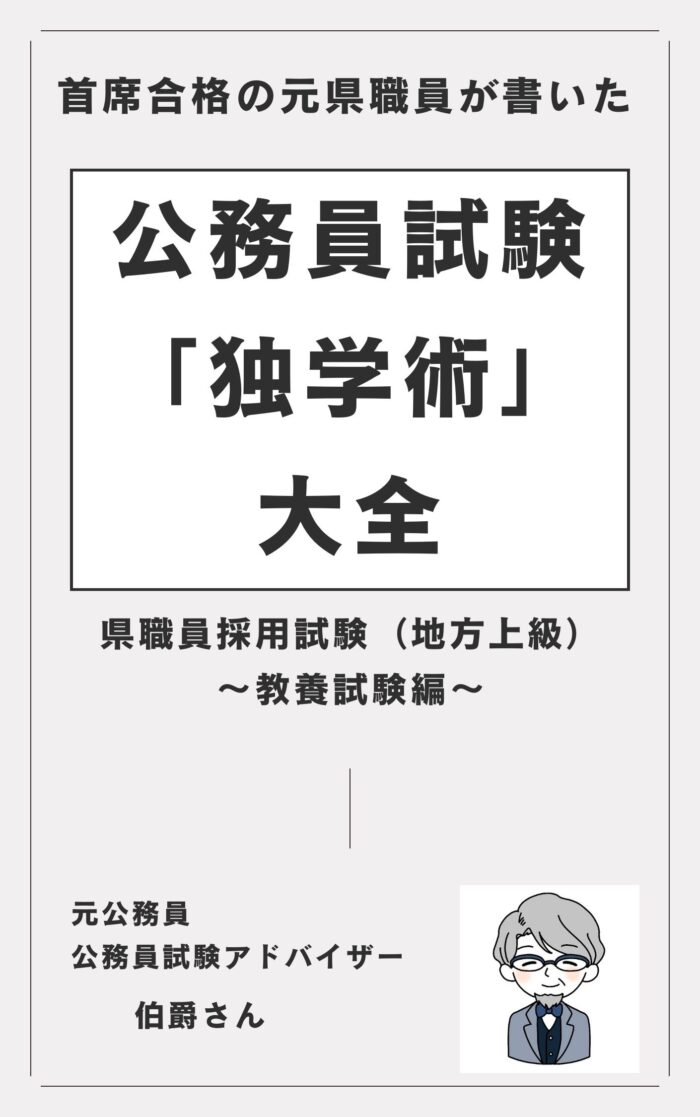「公務員試験の教養試験、参考書が多すぎてどれを選べばいいのか分からない……」
「独学で合格できる?自分に合う勉強法は?」
そんな悩みを抱えるあなたへ。
私自身も独学で公務員試験を複数回受験し、実際に教養試験で高得点(8割)を取り続けてきた元県職員です。
この記事では、独学受験生のリアルな悩みに寄り添いながら、「公務員試験 教養試験」「公務員試験 参考書」「公務員試験 独学」といった検索ニーズに完全対応。
受験の最初の壁となる参考書選びの極意や、独学で合格点を取るための最短ルート、実体験を交えた勉強法のコツまで、徹底的に解説します。
結論を先に言うと、教養試験は“参考書10冊を厳選”して、同じ教材を“3周以上”回せばOKです。
逆に言うと、参考書を買い足して迷うほど、合格から遠ざかります。
【この記事で分かること】
公務員試験の教養試験の全体像・特徴
独学合格を実現する参考書の選び方・使い方
教養試験で高得点を狙うための効率的な勉強法
失敗しない独学のコツや体験談
「独学が不安な人」向け通信講座・教材宅配コースの賢い活用法
迷わず勉強をスタートしたい人、効率重視で一発合格を狙いたい人は必見です!
この記事を書いた人

※本記事は「地方上級・大卒程度(国家一般職含む)」の教養試験対策を想定しています。自治体・年度で出題数や形式が変わるため、必ず志望先の受験案内(出題分野・時間・配点)を確認してください。
公務員試験「教養試験」とは?独学でも十分合格可能!

教養試験の全体像と独学の現実
公務員試験の「教養試験」は、国家公務員や地方公務員など多くの採用試験で課される筆記試験です。
その特徴は、「一般知能」と「一般知識」という2分野から幅広い分野の問題が出題される点にあります。
一般知能(注:数的処理・文章理解など“思考力”を見る分野)
一般知識(注:政治・経済・社会・理科・歴史・地理・時事など“知識”を見る分野)
多くの受験生が
「範囲が広すぎて何から手を付けていいか分からない」
「独学で本当に合格できるの?」
と不安を抱えています。
しかし、実は教養試験は独学でも十分に合格可能です。
現に、私自身も大学時代・社会人時代ともに独学で挑戦し、毎回高得点(8割以上)を獲得してきました。
ここからは、教養試験の構成・出題傾向・合格のポイントを詳しく解説していきます。
教養試験の科目と出題傾向(一般知能・一般知識)
■ 教養試験の出題分野
教養試験は大きく分けて「一般知能」と「一般知識」の2分野で構成されています。
一般知能分野
→ 主に思考力や判断力を問う問題で、数学や論理パズル、グラフ読解などが中心。
出題例:数的推理、判断推理、資料解釈、文章理解(国語・英語)一般知識分野
→ 主に高校までに学んだ知識や、時事問題・社会問題など幅広い分野から出題。
出題例:政治、経済、社会、現代文、日本史、世界史、地理、物理、化学、生物、地学、数学、時事問題
■ 出題数の特徴
「一般知能」の配点が高い…問題数が多く、合否を大きく左右する
「一般知識」は幅広いが1科目あたりの出題数は少なめ
時事問題も頻出…「速攻の時事」など専用対策が有効
ここが最大の落とし穴で、一般知識から気持ちよく始める受験生ほど、後半で詰みます。
■ 出題例と配点イメージ(国家/地方)
※ここはイメージです。年度で変動します。最終確認は必ず受験案内で。
【国家公務員例】
- 知能分野24題:文章理解10題、判断推理7題、数的推理4題、資料解釈3題
- 知識分野6題:自然・人文・社会に関する時事、情報6題
- 試験時間:1時間50分
【地方公務員例(神奈川県)】
- 知能分野22題:数的処理、判断推理、文章理解、資料解釈
- 知識分野28題中18題選択解答:法律・政治・経済・社会一般から12問、日本史・世界史・地理から9問、物理・化学・生物・地学・数学から7問
- 試験時間:2時間
教養試験の平均点・ボーダーライン(目安)
【教養試験の平均点】
- 国家公務員(総合職)の教養試験の平均点 → 約42%
- 国家公務員(一般職)の教養試験の平均点 → 約57%
【教養試験のボーダーライン】
- 国家公務員(就職氷河期世代枠)の教養試験のボーダーライン → 50~73%
- 地方公務員(大卒・行政職)の一次試験(教養+専門)ボーダーライン → 40%~60%
- 長野県(行政A・大卒程度)の教養試験ボーダーライン → 50%
- 愛媛県(行政事務A)の教養試験ボーダーライン → 40%
- 徳島県(行政事務・大卒程度)の教養試験ボーダーライン → 38%
【参考記事↓】
公務員試験(教養・専門)の平均点やボーダーライン(合格者最低点)はどのくらい?
公務員試験は出題数の多い分野を重点的に対策すれば、独学でも十分合格圏に届きます。
重要なのは「満点を目指さない」こと。
合格点は「だいたいこのへん」という帯で動くので、合格に必要な点数に合わせて、捨てる/拾うを決めるのが勝ちパターンです。
苦手分野は「捨て科目」として割り切る戦略も有効です(詳細は後述)。
教養試験は独学で十分合格可能!
私自身、国立大学生時代は大学受験の延長で、社会人になってからも独学で公務員試験に挑戦し、毎回教養試験で75~80%の得点率を維持してきました。
特に、センター試験(現:共通テスト)で7割以上得点した経験がある人は、独学でも十分戦えます。
一方、私立大学出身や、共通テストを経ていない受験生は、スタート時の学力で差が出やすいので、「出題数が多い科目」を重点的に対策していくことが大切です。
ここで誤解しがちですが、独学向きかどうかは学歴ではなく、だいたい次で決まります。
独学向き:自分で決めた計画を「毎日」回せる/分からないを放置せず復習できる
独学が苦手:計画が立てられない/不安で教材を買い足す/質問できないと止まる
「自分は独学向きじゃないかも…」と思った人は、後半の通信講座の賢い使い方(部分利用OK)を読んでください。
全部受講しなくても解決できます。
捨て科目戦略で効率UP
公務員試験の教養科目は出題範囲が広いですが、苦手科目・出題数の少ない科目は思い切って捨てることも合格のポイントです。
捨ててOKな科目例
苦手意識が強い分野(例:日本史・世界史・化学など)
高校時代にほとんど触れていない分野
出題数が少ない分野
捨ててはいけない科目
一般知能分野(数的推理・判断推理など)
政治・経済・社会
ここは本当に大事で、合格点は“全部できる人”が取るものじゃありません。
「点が取れるところを確実に取る人」が勝ちます。
まずは「合格に必要な点数」を見極めよう
教養試験は出題範囲が広く見えても「得点源となる分野」「捨てる分野」を見極めれば、独学で合格点は十分狙える
合格点(ボーダー)を意識して、「合格に必要な戦略的勉強法」を身につけることが成功への第一歩
教養試験おすすめ参考書10選【独学でも合格できる!】
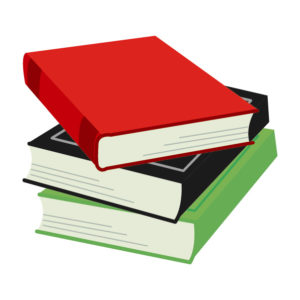
参考書選びが合否を左右する理由(参考書コレクター注意)
「公務員試験 独学」の最大の悩みは“どの参考書を選べばいいのか分からない”という点です。
本屋やネットを見ると膨大な数の参考書が並び、どれも「合格できる!」と宣伝されています。
しかし、自分に合わない参考書を選ぶと、効率が落ち、挫折や時間のロスにつながりがちです。
そこで大事なのが「合格者が実際に使った参考書」「必要最小限に絞ること」です。
多くの合格者が口を揃えて言うのは、「何冊も浮気せず、1冊を繰り返す」こと。
これが最短合格ルートです。
【POINT】
参考書は“質より量”ではなく、“厳選して繰り返す”ことが圧倒的に大切!
そしてもう一つだけ。
「迷い」って、だいたい“勉強の代わり”に出てきます。(これが厄介)
迷う時間をゼロにするために、ここからは買うべき10冊を提示します。
【まず最初の1冊】勉強法を知るための参考書
「受かる勉強法落ちる勉強法」(合格への道研究会・最新版)
→ 最初に読むべき“独学マインドセット本”。
試験範囲が広い公務員試験は、まず“勉強法”を知ることが何より重要。
独学合格者の多くがまずこの1冊からスタートしています。
ここで言う「勉強法の勉強」ができると、
①捨てる科目が決まる → ②やる順番が決まる → ③不安が減って継続できる
という流れが作れます。
今から本屋やAmazonを開くなら、最初の1冊はこれ。
そして次に「畑中シリーズ」です。順番が大事。
【一般知能】数的推理・判断推理・資料解釈・文章理解
「畑中敦子の数的推理ザ・ベストNEO」(畑中敦子)
「畑中敦子の判断推理ザ・ベストNEO」(畑中敦子)
- 「畑中敦子の資料解釈ザ・ベストNEO」(畑中敦子)
「新スーパー過去問ゼミ7文章理解・資料解釈」(資格試験研究会)
ワンポイントアドバイス:
一般知能対策は「畑中シリーズ」で決まり!
とにかく繰り返し3周以上解くのが合格のカギです。
文章理解(国語・英語)は「毎日新しい問題を解く習慣」が大切。
過去問を使い切ったら、別の問題集でもOK。
ここで独学の“勘違い”があるので補足します。
数的・判断は「解けるようになってから回す」ではなく、回してたら解けるようになります
文章理解は「まとめやる」より、毎日1題(慣れが勝ち)
【一般知識】政治・経済・社会科学・時事・自然・人文
「政治・経済の点数が面白いほどとれる本」(執行康弘)
「現代社会の点数が面白いほどとれる本」(村中和之)
「新スーパー過去問ゼミ7社会科学」(資格試験研究会)
「速攻の時事」(資格試験研究会・最新版)
理系なら:「新スーパー過去問ゼミ7自然科学」(資格試験研究会)
文系なら:「新スーパー過去問ゼミ7人文科学」(資格試験研究会)
ワンポイントアドバイス:
「政治・経済・社会」は満点を狙うくらいの気持ちで。
苦手科目・理系分野は「スー過去」で最低限の演習を、難しければ「面白いほどとれる本」で基礎力アップ。
参考書の使い方(3周法・回転のコツ)
独学で勝つ人がやってる“3周法”はこれです。
1周目:理解(解説を読む周)
いきなり満点狙いは不要
「解き方の型」を覚えるのが目的
2周目:定着(同じ型を再現できるか)
解説を見ずに、手順を再現
間違えたら、解説に戻る
3周目:スピード(試験時間に合わせる)
タイマー使用
迷う問題は“即スキップ”練習
原文の黄金ルールにもある通り、私はこれを徹底しました。
特に数的・判断は、解けなくても回す。
これが伸びます。
【重要】参考書コレクターにならないために
「新しい参考書をどんどん買い足す」「ネットで評判を調べて目移りする」――
こうした“参考書コレクター”になるのは合格への遠回りです。
私自身も受験時代、「本当にこの参考書でいいのか?」と不安になり、何度も買い足しそうになりました。
しかし、必要なのは“今使っている1冊を繰り返すこと”だけ。
浮気せず、信じて使い倒せば、着実に得点力は上がります。
【参考書選びで迷う人へ】合格者丸パクリでOK!
独学で一番効率が良いのは「合格者が使った参考書リストをそのまま使う」こと。
この記事で紹介したものを、迷わず買って繰り返せば十分です。
新しいものを買い足す必要はありません。
【参考書リストまとめ表】
| 分野 | おすすめ参考書名 | ポイント |
|---|---|---|
| 勉強法 | 受かる勉強法落ちる勉強法 | 最初に読むべき1冊 |
| 数的推理 | 畑中敦子の数的推理ザ・ベストNEO | 独学受験生の定番 |
| 判断推理 | 畑中敦子の判断推理ザ・ベストNEO | 独学受験生の定番 |
| 資料解釈 | 畑中敦子の資料解釈ザ・ベストNEO | データ読解も頻出 |
| 文章理解 | 新スーパー過去問ゼミ7 文章理解・資料解釈 | 毎日1問ずつ解くと効果絶大 |
| 政治・経済 | 政治・経済の点数が面白いほどとれる本 | 基礎から得点源まで網羅 |
| 社会 | 現代社会の点数が面白いほどとれる本 | 基礎から得点源まで網羅 |
| 社会科学 | 新スーパー過去問ゼミ7 社会科学 | 独学でも使いやすい |
| 時事 | 速攻の時事 | 最新情報は必ず対策! |
| 自然/人文科学 | 新スーパー過去問ゼミ7 自然科学/人文科学 | 独学でも使いやすい |
教養試験「独学勉強法」体験談&効率アップのコツ
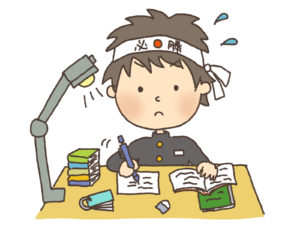
まずは“勉強法の勉強”が最強の近道
「独学で合格したい!」という人ほど、最初に“勉強法そのもの”を学ぶことが合格への一番の近道です。
多くの受験生は、いきなり参考書に手をつけてしまいがちですが、「受かる勉強法落ちる勉強法」などの“勉強法指南書”を最初に読み込むことで、「自分に最適な勉強戦略」が明確になります。
これを怠ると、「何を・いつ・どうやって勉強するか分からないまま迷走し、時間ばかり消費してしまう」という大失敗に繋がりがちです。
【体験談】独学合格者のリアルな1日の勉強ルーティン
ここで、私(元県職員・独学合格者)が実践していた“合格点を最速で取るための1日の勉強スケジュール”をご紹介します。
<独学勉強ルーティン例>
- 午前中:専門試験の勉強
午後:文章理解(国語・英語)を毎日1問ずつ解く
→「新スーパー過去問ゼミ7」や各種問題集で、“毎日新しい問題”を解くことで本番対応力を鍛える。午後:一般知能分野を集中的に勉強(数的推理・判断推理・資料解釈)
→「畑中シリーズ」を軸に、繰り返し3周以上演習。
→ 解説は必ず熟読。難問・奇問は飛ばしても構わない。午後〜夕方:政治・経済・社会を中心に、一般知識を勉強
→「点数が面白いほどとれる本」→「スー過去」の順で、まず基礎を固める。
→ 理解度に応じて何度も繰り返し。夜・寝る前:時事対策(ニュース&「速攻の時事」)
→ 毎日短時間でも時事問題に触れる。最新トピックもチェック。スキマ時間:暗記カードやスマホアプリで一問一答
→ 通学・通勤や休憩時間にサクッと知識の確認。
合格する独学の“黄金ルール”9カ条
思い切って“捨て科目”を決める
苦手な分野・出題数の少ない科目は最初から割り切るのが効率的。出題数が多い科目(一般知能・政治経済)に全力投下
得点源を徹底強化。問題集は“解かない”
問題文読んだら解かずにすぐに解説を読み、解き方を暗記。そのあとすぐ実際に解いてみる。国語・英語の文章理解は“毎日1問新規演習”が効果抜群
本番でのスピード&精度アップ。同じ問題集を何度も繰り返す(理想は3周)
1周目は分からなくてOK。繰り返すほど記憶が定着する。「今日は何時間やったか」より「何個問題を解けたか、暗記できたか」で自分を評価
時間にとらわれず、反復重視。分からない問題は“深追い禁止”で即スキップ
効率重視・無駄な時間カット。毎日必ずタイマーを使って“スピード意識”を持つ
時間配分を体に叩き込む。勉強期間は“短期集中”がベスト
ダラダラ長期間より、2~6カ月の全力投球が伸びる。
ここに“差がつく補足”を一つだけ。
「できるまでやる」じゃなくて「できなくても回す」のが公務員試験のコツです。
範囲が広いので、完璧主義は損します。
【参考記事↓】
【公務員試験(教養試験)】合格できる人の独学の方法9選(教養の勉強は独学で十分)
【実録】8割得点できた独学勉強法のリアル
体験談:元県職員・独学合格の声
「私は“苦手な日本史・世界史・化学は一切手をつけず”、その分、数的推理・判断推理・政治経済を徹底的に強化しました。スタート時は苦手意識が強かった数的推理も、畑中敦子シリーズを“1日10問以上”“3周以上”と決めて、解けなくても繰り返すことで本番には8割得点できるレベルまで到達。文章理解は毎日英語・現代文それぞれ1題ずつ。時事は寝る前に少しずつ“速攻の時事”をチェック。無理なく、でも毎日“必ず触れる”ことが本当に大切でした。」
教養試験の勉強を効率化するための“小技・コツ”
勉強場所を固定して「スイッチ」を入れる
カフェ、図書館、自宅の一角など“ここでやると集中できる”場所をつくるスマホ・SNSは勉強時間だけ強制オフ
アプリをロックして物理的に触れない工夫も毎日のルーティンを決めて「習慣化」
「朝は文章理解→夜は時事」など固定リズムで“迷い”や“だらけ”を防ぐ- どうしてもやる気が起きないときは1日だけ思いっきり遊ぶ
→ ただし翌日は“最小タスク(文章理解1題)”だけでも戻る
よくある失敗例と対策(3パターン)
パターン1:参考書を何冊も買い足してしまう
→ 1冊を繰り返せば十分。合格者のリストを丸パクリでOK!パターン2:苦手分野を“なんとなく”やって時間を消耗
→ 割り切って「捨て科目」を早めに決断するパターン3:スケジュール管理ができず直前で焦る
→ 逆算で「いつまでに何を終わらせるか」週単位で計画
補足:独学で一番きついのは、勉強そのものより「選択の連続」です。
だから最初に、参考書も順番も“固定”しましょう。
迷いが消えます。
模試(模擬試験)は“気にしすぎない”が正解!
模試は「現在の実力」や「本番の時間配分」を知る上で効果的ですが、成績や順位は一切気にしないでOK。
なぜなら、模試と本番の難易度や雰囲気はまったく異なるため、模試で半分しか取れなくても本番では8割超えも珍しくありません。
あと、受験生ごとに学力差がありすぎるので模試の結果は気にしなくて良いです。
【模試のメリット】
今の得点力や苦手分野が分かる
本番形式の“制限時間プレッシャー”を体験できる
モチベーション維持になる
【参考記事↓】
公務員試験の模試は受けるべき!(ただし結果は気にしなくていい)
【公務員試験模試】6社の料金と会場を比較!(会場受験のメリットも紹介)
【Q&A】独学受験生からよくある質問
Q. 仕事や学校が忙しくて十分な勉強時間が取れません…
A. 「毎日少しでも必ず教養試験に触れる」ことが最優先!1日30分でも“積み上げ型”が一番強いです。
Q. 模試や過去問で点が取れなくて不安です…
A. 本番の難易度は毎年違います。合格点(ボーダー)を目安に、「満点は不要」「得点源重視」で割り切って大丈夫です。
教養試験当日に使えるテクニック(3選)
教養試験当日のテクニックを知っておくことも大切です。
このテクニックを知っているか知らないかでは試験結果に雲泥の差がでます。
【教養試験テクニック3選】
- スピード命(解けそうで解けない問題、全くの初見問題、難問奇問は悩まず素早くスルー)
- 見直し命(基本的な問題を確実に正解することが大事。10分程度は確保したい)
- 解く順番を工夫(一般知識→文章理解→数的推理・判断推理→見直し→難問奇問)
詳しく知りたい方は以下の記事をお読みください。
【参考記事↓】
【公務員教養試験】1問あたりにかける時間&解く順番のおすすめ!
独学が不安な人へ:通信講座(教材郵送コース)を賢く使う
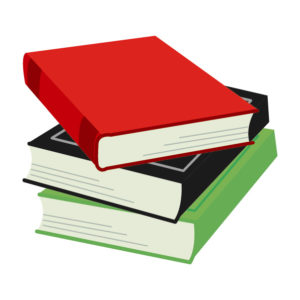
独学 vs 通信講座:比較表(どっちが向く?)
| 比較項目 | 独学 | 通信講座(教材郵送) |
|---|---|---|
| 参考書選び | 自分で選ぶ(迷いやすい) | 一式届く(迷いにくい) |
| スケジュール | 自作(挫折しやすい) | 目安がある(回しやすい) |
| 質問 | 原則できない | 質問サポートありの場合が多い |
| 面接・論文 | 自分で別途対策 | サポートが付くことも |
| 費用 | 参考書で数万円 | 10万円前後〜(内容次第) |
| 向く人 | 自走できる人 | 不安が強い/時間がない人 |
【フローチャート】あなたは独学向き?講座向き?
Q1. 毎日30分でも“継続”できますか?
├─ YES → Q2へ
└─ NO → 通信講座を検討
Q2. 計画(週単位)を自分で作れますか?
├─ YES → 独学向き(この記事の10冊でOK)
└─ NO → 通信講座が相性◎
Q3. 分からない問題を自力で解消できますか?
├─ YES → 独学でOK
└─ NO → 質問サポートのある講座 or 添削・相談サービスを利用
予備校通信講座(教材郵送コース)のメリット
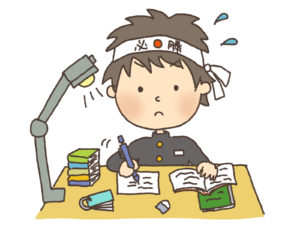
独学&初学者で、試験まであと半年や数ヶ月しかないという人は、「通信講座(教材郵送コース)」がおすすめです。
通信教育は、最初に教材が一式送られてきて、あとは自分で勉強するスタイルです。
(添削や質問は可能です)
通信教育には、たくさんのメリットがあります。
【通信教育のメリット】
- 初めから参考書が揃っている(参考書選びの時間が必要ない)
- 費用が安い(独学で参考書を買う費用とそこまで差がない)
- サポート体制が整っている(添削、質問が可能)
- スケジュール表がある(自分にあったスケジュールが組める)
- 自分のペースで勉強ができる
- 通学の時間を省ける
おすすめの予備校通信講座(教材郵送コース)2社

安くておすすめの通信教育2社をご紹介します。
※情報は変わる可能性があるため、申込前に公式で最新を確認してください
(2025年6月7日時点での情報)
なお、この他にも通信教育を扱っている会社はありますので、興味がある方はお調べください。
| ユーキャン | 東京アカデミー | |
|---|---|---|
| 費用 | 大卒公務員受験対策講座 国家一般職・地方上級コース 99,000円(税込み) (分割支払いも可能:月々6,240円✕16回=99,840円) | 総合対策(教養+専門)コース 104,000円(税込み) (入会金5,000円含む) |
| 教材 |
|
|
| 模試 | ー | 最大8回受験可能 |
| 添削 | 教養3回、専門9回、論文1回 | 教養90回、専門60回 |
| 面接対策 |
| 校舎にて個別面接練習や集団討論練習を1回利用可能 |
| 質問 | 1日3問まで | SOSカード10枚 |
| 特徴 |
| 論文対策コースがオプションで付けられる 教養のみ・専門のみも選べる |
| HP・資料請求 | ユーキャンの公務員講座 | 東京アカデミー |
なお、社会人枠で受験しようと思っている方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
【公務員に転職】社会人が受験できる試験3種類のメリット・デメリット&勉強方法
独学が苦手な受験生は予備校の通信講座を利用
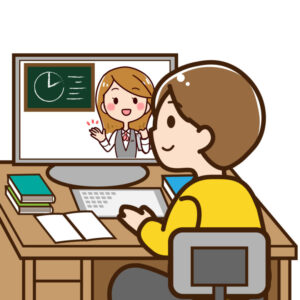
受験生の中には、お金の問題で独学で勉強したいけど、独学がどうしても苦手な人もいると思います。
そういう方は、予備校の通信講座がおすすめです。
【通信講座のメリット7選】
- 予備校通学よりも安い
- 面接対策までしてもらえる(模擬面接、面接カード添削)
- 担任制あり
- 質問サポートあり
- 模試あり
- 講義形式で授業を受講できる
- 参考書選びで悩まなくていい
公務員試験の通信講座がある予備校は10校以上あり、どの通信講座を利用するか非常に悩むところです。
ここでは、パターン別に私のおすすめを挙げておきます。
- 安さを追求したい大学生におすすめ → 内定特典で全額返金がある「アガルート(資料請求)
」
- 合格実績が完璧で(2025年度84%の生徒が合格)、通信講座なのに面接対策&相談サポートがとても充実しているのでおすすめ → 「EYE(資料請求
)」
※講座は年度で制度が変わるので、比較するときは最低でも次の3つを見てください。
①面接カード添削 ②模擬面接 ③質問サポート(回数・期限)
【関連記事↓】
- 【元公務員が厳選】公務員通信講座おすすめ12選と選び方ガイド(2025年版)
- 【2026年最新版】社会人が公務員に転職するためのおすすめ通信講座4選を元県職員が徹底比較
- 公務員予備校費用を最も安くする方法はズバリ「内定特典」(実質無料)
【Q&A】通信講座のよくある疑問
Q. 独学と比べて通信講座は本当にメリットがありますか?
A. 参考書選び・スケジュール管理・質問対応・面接サポートなど、独学の弱点をほぼ全てカバーできます。独学が不安な方はコスパ良しです。
Q. どこを選んでも内容は同じ?
A. 細かいカリキュラム・サポート体制は異なります。合格実績や面接対策、返金特典の有無も比較ポイントです。
よくある質問と失敗しない独学のコツ【Q&A】

Q1. 独学で本当に合格できますか?
A. はい、十分可能です!
実際に私自身や多くの合格者が独学で教養試験を突破しています。
重要なのは「自分に合った参考書を厳選し、1冊を繰り返す」こと。
また、“捨て科目”や“得点源の集中強化”など、独学ならではの戦略が合格のカギとなります。
Q2. どれくらい勉強すれば合格できますか?
A. 平均して2〜6カ月の集中学習が目安です。
毎日1〜2時間でもコツコツ積み上げれば十分。
教養試験のみでいえば、短期集中型なら1日4〜5時間で3カ月仕上げも現実的です。
大切なのは「毎日教養試験に必ず触れる」「何周繰り返せたか」を重視することです。
【参考記事】
公務員試験の勉強はいつから始めるべき?合格に必要な勉強時間とスケジュールの立て方【元県職員が解説】
Q3. 模試や過去問で点が伸びません。どうしたらいい?
A. 模試や過去問の点数は気にしすぎなくてOK!
本番と同じ難易度・出題傾向になることは稀です。
模試は「時間配分や苦手分野の確認」と割り切り、苦手科目を“捨てる勇気”も持ちましょう。
Q4. 参考書は何冊あれば十分ですか?
A. 教養対策は“厳選10冊”で十分です。
むしろ増やすほど回転数が落ちて逆効果になりがちです。
まずは「一般知能(畑中+文章理解)」を固定し、必要なら知識系を足す。
これが最短です。
Q5. 独学だと面接や論文が不安です。
A. 筆記は独学でも、面接や論文は通信講座や添削サービスの活用が有効です。
近年は「オンライン面接練習」「添削サービス」も充実しているので、筆記合格後に部分的に利用する方法もおすすめです。
Q6. 仕事や学校が忙しくて十分な勉強時間が取れません…
A. 「毎日少しでも必ず教養試験に触れる」ことが最優先!
1日30分でも“積み上げ型”が一番強いです。
Q7. 途中でやる気が切れそうになった時の対策は?
A. 小さな成功体験を積み重ねて“勉強の習慣化”を目指しましょう。
1日1問だけでも継続、勉強記録ノートやアプリで「見える化」する、模試の申込で“強制イベント”を入れる、勉強仲間とSNSで進捗共有するなど、ちょっとした工夫で続けやすくなります。
【参考記事】
【公務員試験】勉強のやる気が起きないときの対処法10選!(これでモチベアップ!)
まとめ|「参考書は厳選して繰り返す」だけで合格は見えてくる!
ここまで公務員試験独学受験生におすすめの教養試験の参考書を紹介してきました。
公務員試験用の参考書はたくさん発売されているので、初心者はかなり迷いますし、参考書を何度も買い直すことになると思います。
そうならないためにも、合格者(特に教養試験で高得点をゲットした人)の使用した参考書を丸パクリするのはコスパ・タイパ的に良い考えだと思います。
今回ここで紹介した参考書は私が自信を持って紹介できるものですので、これ以上買い足さずに同じ参考書を繰り返し解いてください。
そうすれば、自ずと教養試験での高得点が近づき、合格への近道となります。
【まとめ】
公務員試験の教養試験は、出題範囲が広くても“戦略的独学”で十分合格できます。
参考書は「合格者が使ったもの」を厳選し、1冊を繰り返すことが最大の近道。
「苦手分野は捨てる」「得意分野を徹底的に伸ばす」ことで短期間でも効率的に得点できます。
模試・通信講座・添削サービスも、必要に応じて部分活用すれば独学でも安心。
「不安なことは行動で解決!」一歩踏み出して、自分だけの合格ロードマップを完成させましょう!