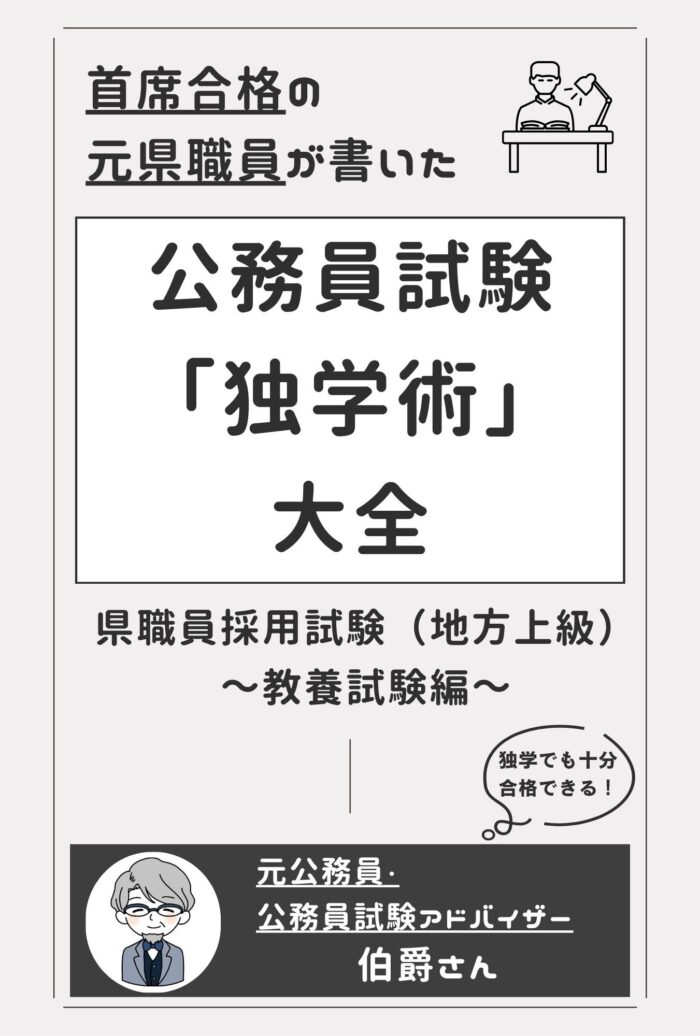「公務員試験の教養試験、毎回時間が足りない…」
「どこから解くべき?見直しの時間が取れない…」
そんな悩みを抱える受験生のために、この記事では教養試験の時間配分とおすすめの解く順番を詳しく解説します。
私自身、国・県の公務員試験を複数回受験し、すべての試験で得点率75〜80%をキープしてきました。
その経験をもとに、合格につながる“時間戦略”をお伝えします!
【執筆者↓】

なぜ公務員教養試験は「時間が足りない」のか?
公務員試験の教養試験(筆記試験)は、以下のような特徴があります。
試験時間:120分(2時間)
問題数:約50問(自治体により違う)
試験形式:マークシート方式(4択 or 5択)
つまり、1問あたり約2.4分で解かないと間に合いません。
しかも数的処理や文章理解など、時間のかかる問題が多いため、戦略的な時間配分が超重要なんです。
【結論】時間配分のポイント3つ
1問あたりにかける時間を科目別に決める
高得点が狙える科目に時間を割く
自分に合った解く順番を事前に決めておく
これを実践するだけで、得点率が大きく上がります。
【科目別】教養試験の時間配分と目安配分
それでは科目別に教養試験の時間配分と目安配分を紹介します。
一般知識(時事・社会・人文・自然など)
→1問あたり1分~2分
時間をかけすぎると他の問題が解けなくなる
解けそうにない問題は、マークだけして次へ進む
捨て科目は最初から選択肢を見ずにマークOK(4択なら25%の確率で正解できる)
【対策ポイント】
迷ったら即次へ。割り切りが勝負の分かれ目!
文章理解(現代文・英文など)
→1問あたり3分~5分
時間をかければ正解できる可能性が高い
粘りすぎ注意。1問5分以上かけると後半が崩れる
毎日1問ずつ演習してスピード強化
【対策ポイント】
短期では伸びづらい。毎日の積み重ねが効果的!
数的推理・判断推理
→1問あたり3分~5分
出題数が最も多く、配点も高い
合否の分かれ目になる超重要分野
解けそうで解けない問題は5分で見切りをつける
【対策ポイント】
「時間をかければ解けそう」でもダメ。時間制限を決めて切り替え!
資料解釈
→1問あたり3分~5分
グラフや表を読み取り、計算や比較を行う問題
丁寧にやれば正答できるが、時間がかかる
1問5分を超えないよう注意
【対策ポイント】
「読み取り→比較→計算」の流れに慣れよう!
解くスピードを上げるには?
✅ ストップウォッチを使って演習する
→ スマホでもOK!問題を解く際に必ず計測。タイムは問題文の横に書き残していく。
✅ 暗記・参考書も時間を決めて学習する
→ ダラダラ読まない。「15分で10ページ読む」など具体的に!
✅ 模試を活用して本番と同じ環境で練習
→ 模試は最低2回、必ず会場受験で!
【おすすめ】教養試験の解く順番と時間配分(例)
以下は私が実際に実践していた解き方です。
試験時間が120分の場合の目安です。
| 順番 | 科目 | 時間配分 |
|---|---|---|
| ① | 一般知識 | 30分 |
| ② | 文章理解 | 20分 |
| ③ | 数的推理・判断推理 | 50分 |
| ④ | 資料解釈 | 10分 |
| ⑤ | 見直し | 10分 |
解く順番のポイント
一般知識を先に終わらせてプレッシャーを軽減
得点源となる「数的・判断」「文章理解」に集中
最後に資料解釈 → 比較的正答率が高く、点数が取りやすい
ポイントは「どれだけ一般知識に時間をかけず、一般知能に時間を費やせるか」です。
【試験中のテクニック】迷った問題の扱い方
解けない問題に時間をかけすぎるのはNG。
目安は30秒程度でいいと思います。
以下の手順で“後回し対応”しましょう。
- 問題を読む
- 明らかに違う選択肢を消す
- 残った選択肢の中で1つをマーク(仮)
- 問題番号に「×」や「☆」をメモ
問題にマークをつけておくと、あとで解きなおす際に、すぐにその問題を見つけ出すことができるのでおすすめです。
最後の数分が勝負を決める|見直しの重要性
「たった数分の見直しで1〜2問正解できる」ことは本当によくあります。
冷静に読み直せば、勘違いに気づく
繰り返し見た選択肢で直感が働くことも
特に倍率の高い試験では、1問の差=合否の差です。
【おすすめ】教養試験直前期の過ごし方
解く順番と時間配分を本番形式で練習
ストップウォッチ付きで50問を時間内に解く
公開模試を最低2回(初期・直前)受験
苦手分野は“捨てる勇気”も必要!
まとめ|公務員教養試験は「時間との闘い」
教養試験で高得点を取るには、解く順番と時間配分の戦略が欠かせません。
特に意識すべきポイントはこの5つ!
科目ごとに「かけていい時間」を決める
数的推理・判断推理・文章理解を最重視
見直し時間を10分は確保する
迷った問題はマーク&印をつけて後回し
模試で本番をシミュレーション