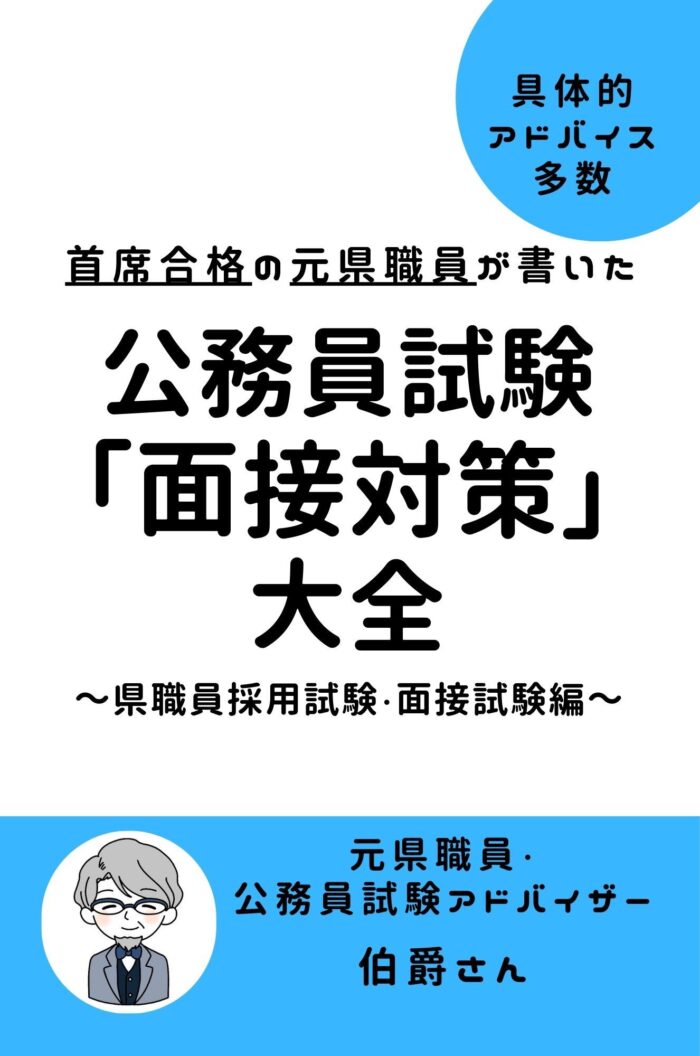「面接カードってどう書けばいいの…?」
「志望動機や自己PR、なんとなくで書いていいのかな…?」
公務員試験の面接対策で、多くの受験生が最初につまずくのが「面接カードの書き方」です。
実は、面接カードは単なる事前提出書類ではありません。
面接官があなたを評価する“最初の判断材料”であり、面接本番の質問内容にも大きく影響する重要なツールなのです。
本記事は、面接カード対策の「まとめ記事」です!
このページは、筆者(元県職員で2回の合格経験あり)が執筆した「公務員試験 面接カード対策」に関する各記事を網羅的にまとめたポータル記事(まとめ記事)です。
「今すぐ知りたい情報だけをピンポイントで確認したい」
「面接カードの全体像をまず掴みたい」
という方は、ぜひこの記事から順番に確認していってください。
【本記事でわかること】
面接カードを書く前に絶対知っておきたい8つの基本ポイント
志望動機・自己PR・短所・関心事項・趣味の項目別の具体的な書き方と注意点
合格者が実際に書いた面接カードの実例
よくある質問(Q&A)や失敗パターン
面接カードの添削サービスやおすすめの活用方法
各セクションでは、さらに詳しく解説した関連記事にもリンクしていますので、必要に応じて深掘りしてください。
【この記事はこんな人におすすめ!】
面接カードを書いたけど、内容に自信がない
これから面接カードを書こうとしているが、何から手をつければいいかわからない
志望動機や自己PRの書き方を具体的な実例とともに知りたい
添削してもらう方法やサービスを探している
筆者は元県職員として、地方上級の技術職・事務職両方の面接カードを実際に書き、合格した経験があります。
その体験と、これまでに寄せられた多数の相談内容をもとに、「初めての人でも迷わない」内容を意識して構成しました。
この後は「面接カードを書く前に知っておくべき8つのポイント」から順に、項目ごとの書き方や実例を解説していきます。
あなたの面接カードづくりの道しるべになれば幸いです!
この記事を書いた人

- 1 面接カードを書く前に知っておくべき8つのコツ【合否を左右する準備フェーズ】
- 2 志望動機の書き方|面接官に刺さるための5ステップ+構成テンプレート
- 3 自己PRの書き方|「一緒に働きたい」と思わせるための3つのコツ+構成テンプレ
- 4 短所・苦手なことの書き方|“印象ダウン”を防ぎ、“信頼アップ”につなげる4つのコツ
- 5 関心事項の書き方|「あなたらしさ」と「志望職種との接点」を伝えるチャンス!
- 6 趣味の書き方|“安心感”と“人柄”を伝えるさりげないチャンス!
- 7 合格者の面接カード実例|リアルな記述内容と“改善ポイント”も紹介!
- 8 面接カードQ&A|よくある疑問・不安をまるごと解決!
- 9 面接カードは添削を受けるべき?|“必須級”の理由とおすすめの依頼先
- 10 【まとめ】公務員試験 面接カードの最終チェックリスト|合否を分ける“仕上げの一手”とは?
- 10.1 この記事で学んだことを振り返ろう!
- 10.2 最終チェックリスト|提出前に確認しておきたい10のこと
- 10.2.1 🔲 1. 字は丁寧に書いてあるか?読みにくくないか?
- 10.2.2 🔲 2. 志望動機は「なぜその職種・自治体なのか」まで書けているか?
- 10.2.3 🔲 3. 自己PRは「強み+エピソード+活かし方」の構成になっているか?
- 10.2.4 🔲 4. 短所は“改善中のストーリー”になっているか?
- 10.2.5 🔲 5. 関心事項は職種と関連性のある話題か?
- 10.2.6 🔲 6. 趣味は「人柄や継続力」が見える内容になっているか?
- 10.2.7 🔲 7. 全体を通して“嘘のない、あなたらしい言葉”で書けているか?
- 10.2.8 🔲 8. 内容が長すぎたり、詰め込みすぎて読みづらくないか?
- 10.2.9 🔲 9. 誤字脱字・形式ミス(敬語、句読点、表記ゆれなど)はないか?
- 10.2.10 🔲 10. 誰かに添削を依頼したか?フィードバックを反映できているか?
- 10.3 合格への近道は、“丁寧に考え、丁寧に書くこと”
- 10.4 公務員面接対策でお困りの方へ
- 10.5 最後に
面接カードを書く前に知っておくべき8つのコツ【合否を左右する準備フェーズ】
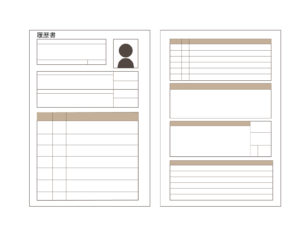
「面接カードって、志望動機とか自己PRを書けばいいんでしょ?」
――そう思って、なんとなく書き始める人は、正直かなり危険です。
なぜなら、公務員試験の面接では面接カードが“評価の起点”になるからです。
面接官は面接当日にあなたと初めて会うわけではありません。
すでに事前に提出された面接カードを読み込み、そこから質問内容やチェックポイントを練っています。
つまり、「どんな面接カードを書くか」で面接の流れ・雰囲気・質問内容、そして評価までが変わるのです。
ここでは、面接カード作成に取りかかる前に絶対に知っておきたい「8つの土台となる考え方・戦略」を詳しく紹介します。
① 面接カードは“合否に直結する”最重要ツール
面接カードは単なる提出書類ではありません。
あなたの考え方や志望動機
これまでの経験やスキル
業務への適性や価値観
など、あらゆる情報を凝縮して伝える「自己プレゼン資料」であり、**面接官との“最初の接点”**となるものです。
筆記試験が得意でも、面接カードが雑だと、面接官の印象は大きくマイナスになります。
一方で、丁寧に戦略的に書かれた面接カードは、質問がしやすく、面接官に「しっかり準備してきた人だな」と好印象を与えます。
② 面接対策は筆記試験後でもOK。ただし“準備”は前もって
筆記試験が終わってから面接カードを準備するのは一般的です。
しかし、「書く作業」に入る前にやるべき準備はたくさんあります。
自己分析(強み・弱み・価値観)
志望先の研究(自治体の重点政策や地域課題)
自分の経験やスキルの棚卸し
公務員に求められる人物像の理解
これらは筆記試験の勉強と並行して少しずつ進めておくと、いざ書くときに焦らず質の高いカードが作れます。
③ 志望動機は“職種別・自治体別”にカスタマイズが基本
「人の役に立ちたい」
「安定した職に就きたい」
といった漠然とした志望動機では、差別化はできません。
公務員には、行政職・技術職・事務職・学校事務・林業職などさまざまな職種があり、それぞれ求められる役割や現場も異なります。
また、県庁と市役所では対応する業務範囲も大きく違います。
志望動機を書く際は、職種ごと・自治体ごとに分けて考えるのが基本です。
④ 志望動機や自己PRは“エピソードと具体性”が命
評価される志望動機・自己PRは、以下の3要素を含んでいます:
きっかけとなった具体的な経験や背景
自分の価値観や強みとの接点
志望先・職種とどうマッチしているか
たとえば、「地域貢献をしたい」だけでは弱いですが、「高校時代、地域清掃ボランティアに3年間関わり、高齢者から感謝された経験が、将来は地域行政に関わりたいという思いに変わった」といった具体例を入れることで、グッと説得力が増します。
⑤ 面接官との“キャッチボール”を意識した書き方に
面接カードは一方的に書くだけで終わりではありません。
面接当日、面接官がその内容をもとに質問してくるため、「ツッコミどころを作っておく」ことが面接全体の雰囲気を左右します。
質問が広がりやすく、話しやすい内容であれば、自然な会話になり、評価も良くなります。
逆に、あまりに抽象的だったり、どこにも引っかかりのない内容だと、面接官も質問に困り、淡々とした雰囲気になりがちです。
⑥ 面接対策は“練習回数=自信”に直結する
面接カードが完成したら、それを元に何度も話す練習をしましょう。
声に出して話す練習
模擬面接
家族や友人にロープレしてもらう
など、実践的な練習を重ねることで、内容が自分の言葉としてしっかり定着します。
「内容は良かったのに、うまく説明できなかった…」というのは非常にもったいないです。
⑦ 圧迫質問には“完璧な答え”より“誠実な対応”を
「前職を辞めた理由、甘くないですか?」
「その志望動機、他の自治体でも通用しますよね?」
といった圧迫気味の質問に対して、沈黙してしまうのはNG。
大切なのは、正解を言おうとすることではなく、冷静に答える姿勢です。
多少言葉に詰まっても、真摯に自分の考えを伝えようとする姿勢が評価されます。
⑧ “メラビアンの法則”を意識して印象アップを狙う
「人の印象は話の内容よりも“見た目と声”で決まる」
これは心理学の「メラビアンの法則」によるもので、以下の割合で第一印象が決まるといわれています。
視覚(表情・姿勢・服装):55%
聴覚(声のトーン・話し方):38%
言語(話の内容):7%
どんなに内容が素晴らしくても、姿勢が悪かったり、声が小さいとマイナス評価につながることも。
面接カードと合わせて、“伝え方”も磨く意識を持つと、評価を大きく上げられます。
この章で紹介した8つの準備ポイントを押さえることで、あなたの面接カードは「伝わるカード」に変わります。
【詳細な内容はこちら↓】
【公務員試験】受かる人が使っている面接のコツ8選(非常に役立った公務員面接参考書も紹介)
次章では、実際に志望動機・自己PR・短所など、設問別の書き方テクニックを解説していきます。
志望動機の書き方|面接官に刺さるための5ステップ+構成テンプレート
面接カードで最も注目される項目――それが「志望動機」です。
どんな自治体でも、どんな職種でも100%質問される鉄板テーマであり、面接全体の印象を左右する超重要ポイントです。
あなたがどんなに立派な経歴を持っていても、「志望動機」が曖昧・浅い・ありきたりだと、面接官の評価は上がりません。
逆に、自治体や職種との“接点”が見える、具体的で説得力のある志望動機が書ければ、あなたへの信頼感・納得感が一気に高まります。
よくあるNGパターン
「人の役に立ちたいと思ったから」→ 抽象的すぎる
「安定しているから」→ 本音だとしても評価されにくい
「公務員ならなんでもいいです」→ 志望動機になっていない
これらは一見するともっともらしく見えますが、面接官に「他の受験者と同じ」「うちじゃなくてもいいのでは?」と思われてしまう典型例です。
評価される志望動機に仕上げる5ステップ
①「なぜ公務員なのか?」の原体験・動機を明確にする
まずは「民間ではなく公務員を選んだ理由」を明確に言語化しましょう。
たとえば:
災害時に活躍する行政職員の姿に心を動かされた
家族が行政サービスに助けられた経験がある
前職で感じた制度の限界を、公務の立場で変えたいと思った
など、あなたにしかないきっかけや体験を入れることで、説得力のある動機づけになります。
🖊【例文】
大学時代、地域福祉のボランティア活動に参加する中で、行政職員が地域の要となって動いている姿に触れ、自分も将来、地域課題の解決に携わりたいと感じた。
②「なぜこの自治体・職種なのか?」を具体的に書く
次に大切なのが、数ある選択肢の中で「なぜこの自治体」「なぜこの職種」を選んだのかという点。
✅ 参考にすべきポイント:
自治体の施策・スローガン・重点分野
過去の訪問経験・フィールドワーク
自分の出身地や地元への思い
職種の仕事内容と自分の適性との一致
🖊【例文】
○○市では高齢者支援に力を入れており、大学で学んだ社会福祉の知識を活かし、行政と地域をつなぐ役割を果たしたいと思い志望しました。
③ 自分のスキル・経験と結びつける
「やりたい」だけでは不十分。
「自分には何ができるのか」を具体的に示すことが、即戦力としての信頼を高めます。
✅ 使えるエピソード例:
前職での業務経験
大学や資格取得で得た専門知識
アルバイトやボランティアの実践経験
🖊【例文】
前職では窓口対応や資料作成を担当しており、正確さと丁寧さを求められる環境で鍛えられました。こうした経験を、住民対応が求められる市役所の行政職で活かしたいと考えています。
④ 志望動機の構成テンプレート(初心者向け)
以下の構成に沿って書けば、自然で説得力ある文章が書けます:
【志望動機テンプレ】
【きっかけ】なぜ公務員を目指すようになったか(原体験)
【志向性】どんな価値観・思いを持っているか
【自治体との接点】なぜこの自治体・職種を選んだか
【スキル接続】自分の強みや経験をどう活かすか
【締め】今後どう成長し、貢献したいか
🖊【構成に沿った例文】
大学時代に地域の子育て支援ボランティアに参加した経験を通して、「行政の立場から地域の暮らしを支える仕事がしたい」と思うようになりました。
特に、少子化対策に力を入れている○○市の取り組みに共感し、自分もその一助となりたいと考えています。
前職では、保護者対応や会議資料の作成などを通じて、正確かつ迅速な対応力を磨いてきました。
こうした経験を生かし、地域の声を行政に反映できる職員として成長していきたいと考えています。
⑤「地に足がついた言葉」で書く
最後に重要なのが、背伸びをせず、あなた自身の言葉で書くことです。
「理念」や「理想論」だけで終わらず、
実際のエピソード
日常的な感情や体験
自分なりの気づき
など、等身大の言葉で書かれた志望動機こそが、読み手の心に届きます。
【さらに学びたい方はこちらの記事もおすすめ】
より詳細な志望動機の書き方や合格者の例文は、以下の記事で解説しています。
【完全ガイド】公務員試験面接カードの書き方|志望動機・自己PRのコツと例文を元県職が解説!
次章では「自己PRの書き方」に進みます。面接官に「一緒に働きたい」と思ってもらえるPR方法を徹底解説します!
自己PRの書き方|「一緒に働きたい」と思わせるための3つのコツ+構成テンプレ
面接カードでほぼ確実に登場するのが「自己PR欄」です。
志望動機と並び、あなたの魅力をダイレクトに伝える超重要項目。
ここが弱いと、面接官に「印象が薄い人だな…」と思われてしまうこともあります。
でも…
「何をアピールすればいいか分からない」
「誇れるような実績なんてない」
「ただの真面目な学生・社会人だけど、大丈夫?」
…という不安、ありますよね。
大丈夫です。
自己PRに必要なのは、「すごい実績」ではなく「誠実な姿勢と具体性」です。
どんな人でも、日常の中に“アピール材料”は必ずあります。
ここでは、それを引き出し、面接官に伝わる形に整えるための3つのコツをお伝えします。
自己PRを成功させるための3つのコツ
①「施策や業務内容をしっかり勉強」しておくこと
いきなり自己PRを書き始める前に、まず大切なのが、志望する自治体や職種の仕事を理解することです。
住民対応が多い窓口業務
書類処理が正確さを求められる事務職
チームで連携して課題を解決する福祉職や学校事務職
など、職種によって求められる人物像が違います。
だからこそ、自己PRでも「その仕事に必要な能力を持っていること」を自然に伝えることが大切なんです。
②「自分の知識・スキル・経験」で役立ちそうなものを1つ選ぶ
自己PRで最も大事なのは、「1つに絞ること」です。
協調性
傾聴力
継続力
課題解決力
忍耐力
丁寧さ など
これらの中から、自分が「これは誰にも負けないかも」「これは仕事でも活かせそうだ」と思えるものを1つ選びましょう。
そして、その強みを証明する具体的なエピソードを添えます。
🖊【例】
「私の強みは継続力です。大学時代に苦手な英語を克服するため、毎日30分の英語日記を1年間続けたことで、TOEICスコアが250点伸びました。途中で投げ出しそうになったこともありましたが、“やり抜く力”を育てられた経験でした。こうした地道な努力を、公務員の仕事でも活かしていきたいと考えています。」
③「業務への活用イメージ」まで書いて仕上げる
最後に、その強みが公務員の仕事でどう活かせるかを明記して、自己PRを締めましょう。
ここが抜けている人、結構多いです。
「私は協調性があります」で終わるのではなく、
「その協調性を、庁内外の連携業務や住民対応で活かしたい」といった形にすると、実務との接続が見えて、説得力が一気に高まります。
自己PRテンプレート(使いまわせる型)
【強み提示】私の強みは〇〇です。
【エピソード】この強みは、△△の経験で培われました。
【結果と学び】この経験を通して□□を身につけました。
【活かし方】この強みを、公務員として○○の場面で活かしたいです。
🖊【例文(傾聴力)】
私の強みは、相手の話をしっかり聞く「傾聴力」です。
大学時代、学生相談室のボランティア活動に参加し、悩みを抱える学生の話を丁寧に聞くことに努めてきました。
話を遮らず、相手の言葉の背景まで汲み取ろうとする姿勢を続けたことで、「話してスッキリした」「分かってもらえた気がする」と言ってもらえることが増えました。
この経験を活かし、公務員としても、住民の声を丁寧に受け止め、安心感を与えられる対応をしていきたいと考えています。
「参考書がかなり使える」ってホント?
はい、本当です。
自己PRに悩んだら、公務員試験対策用の面接本を1冊読むだけでも、言い回し・構成・差別化ポイントが一気に整理されます。
例えば、
公務員試験現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本 2025年版 著 大賀英徳
自己PRは「素直さ・等身大・公務員らしさ」で勝負しよう
ウソをつかない
スゴく見せようとしない
けれど手を抜かない
これが、面接官に「一緒に働いてみたい」と思ってもらえる自己PRの3原則です。
次は「短所・苦手なこと」の書き方に進みます!
短所も“伝え方次第”で印象が逆転する設問。正しく伝えて、評価を落とさないようにしましょう。
短所・苦手なことの書き方|“印象ダウン”を防ぎ、“信頼アップ”につなげる4つのコツ
「短所」や「苦手なこと」は、面接カードの定番項目のひとつ。
正直なところ、あまり書きたくない人が多いと思います。
短所を正直に書くと落とされる?
→ そんなことはありません。
むしろ、「自分を客観視できていない人」「課題を放置している人」こそが面接で落とされます。
面接官は、あなたに完璧さを求めているわけではなく、
自分の弱さを把握できているか
その弱さをどう改善しようとしているか
短所が職務に致命的でないか
を見ています。
だからこそ、「書いてはいけない短所」「書いてもよい短所」「評価される書き方」を理解することが大切です。
書く前に知っておきたい4つのポイント
① 面接官は“人間らしさ”と“向き合う力”を見ている
短所の設問は、「完璧じゃないあなた」を知るためのものです。
逆に「特にありません」と書くと、「自分を客観的に見られない人」と評価されてしまう可能性があります。
② 書いていい短所/書かないほうがいい短所
✅ 書いてOKな短所(見方によって長所になるもの)
心配性 → 丁寧・慎重
せっかち → 行動力・スピード感がある
緊張しやすい → 事前準備を徹底するタイプ
人見知り → 慣れると深い関係を築ける
頼られすぎる → 責任感が強い
❌ 書かない方がいい短所(致命的に受け取られるもの)
協調性がない
報連相ができない
嘘をつくクセがある
時間が守れない
無気力/やる気がない
③「短所→対策中→改善中」のストーリーで書く
短所を書くときは、「私は○○が苦手です」で終わってはいけません。
必ず「どう向き合っているか・改善に向けて何をしているか」をセットで伝えましょう。
🖊【例】
私の短所は、人前で話すときに緊張しやすい点です。これまでは発表の場面で声が小さくなってしまうことがありました。
そこで、大学ではプレゼンの授業を選択し、人前で話す機会を増やす努力をしています。今では少人数の前なら落ち着いて話せるようになってきました。
このように、苦手意識を克服するために前向きに取り組んでいます。
④ 面接では想定問答を必ず準備しておく
「短所」は、面接でもよく深掘りされる項目です。
「それは業務に支障はないですか?」
「今も同じ失敗を繰り返していますか?」
「改善するために他に何をしていますか?」
こうした質問にしっかり答えられるように、想定問答をノートに書いておくことをおすすめします。
面接官のツッコミを想定して準備しておくことで、「この人、ちゃんと考えているな」と信頼感が高まります。
短所の書き方テンプレ(4ステップ)
- 【短所の提示】私の短所は○○です。
- 【具体例】過去にこのような場面で課題を感じました。
- 【改善努力】そこで□□のような対策を行っています。
- 【今後の意気込み】これからも意識して改善し、業務に活かしていきたいです。
�【例文(せっかち)】
私の短所は、少しせっかちなところです。
急いで行動するあまり、周囲の意見を十分に聞かずに進めてしまうことがあり、大学のグループワークではうまく連携が取れなかった経験があります。
その反省を踏まえ、今ではまず相手の意見を聞いてから動くよう意識しています。
公務員としても、住民や同僚と連携を取ることが大切だと考えており、冷静さを持って丁寧な対応を心がけたいと思っています。
【さらに詳しく知りたい方はこちら↓】
【公務員試験面接カード】短所・苦手なことの書き方(長所にもなる短所を書く)
次章では「関心事項」の書き方を解説します!
書き方に悩みやすい設問ですが、うまく使えば“独自性”をアピールできるポイントになります。
関心事項の書き方|「あなたらしさ」と「志望職種との接点」を伝えるチャンス!
「関心事項」――あまり見慣れない設問ですが、面接カードや面接本番でときどき出てくる質問です。
志望動機や自己PRと比べると、軽く見られがちですが、実はこの項目は**“あなたの価値観や視野の広さ、そして職務適性”が読み取られる重要なパーツ**です。
「関心事項」で見られている3つのポイント
最近の社会的テーマに関心を持っているか
志望職種とつながる内容になっているか
自分の視点や考えを言語化できるか
つまり、関心事項とはただの「好きな話題」ではなく、「あなたの知的関心」や「仕事との親和性」が表れる項目なんです。
関心事項を書くときの6つのコツ
① 私的な話題は避ける
趣味や芸能ネタ、ゲーム、恋愛トークはNG。
面接官に「話を広げにくいな…」と思われるだけでなく、「公務員としての資質が見えない」と評価されかねません。
② できるだけ“最近の”テーマを選ぶ
1年前の話題や古いニュースでは、アンテナが低い印象を与えてしまいます。
直近のニュース、法改正、自治体の動きなど、フレッシュな話題を選びましょう。
③ 志望職種に関係のあるテーマを選ぶと強い
たとえば:
行政職 → 地方創生、子育て支援、観光振興、防災
学校事務職 → 教育行政、教員の働き方改革、不登校対策
福祉職 → 高齢者支援、生活困窮者支援、障害者福祉
自分の関心と、職務で扱うテーマが重なっていると、面接官に「この人、ちゃんと調べてるな」「業務に関心があるな」と好印象を与えられます。
④ 面接官に「もう少し聞きたい」と思わせる内容にする
具体的すぎず、あえて少し“問いかけ”や“問題提起”の形にすると、面接本番で会話が広がります。
🖊 例:「子どもの体験活動が減っている中で、自治体がどのように関わるべきか考えています。」
⑤ 強すぎる主張はNG!中立的に・穏やかに
行政批判・政権批判・強い思想の主張は避けましょう。
「自分の考えを持っているけど、冷静に対話できる人」というバランスが◎です。
⑥ 自分の行動・経験と絡めると説得力UP
ただ「ニュースで興味を持ちました」では弱いです。
関心を持ったきっかけや、自分の行動(読んだ本、イベント参加、調べたことなど)を少し加えると、グッとリアリティが出ます。
使える!関心事項テンプレート(初心者向け)
【テーマ提示】最近、○○について関心を持っています。
【理由・きっかけ】きっかけは□□で、調べるうちに興味が深まりました。
【考察】その中で、○○のような課題を感じました。
【締め】今後は、自分でもさらに情報を集め、理解を深めていきたいと考えています。
【例文:学校事務職を志望する場合】
最近、子どもたちの学びの質や体験活動の機会について関心を持っています。
きっかけは、大学での教育実習で感じた「子どもの主体性の弱さ」でした。
コロナ禍を経て、学校外の活動が制限される中で、自治体や学校がどうサポートできるのか、課題も多いと感じています。
学校事務職として、教育活動を支える立場から子どもたちの成長に間接的に関われることに魅力を感じており、今後もこのテーマについて学びを深めていきたいです。
【もっと詳しく知りたい人はコチラ】
【元県職員が解説】公務員の面接カード「関心事項」で差がつく書き方と例文
次章では「趣味」の書き方に進みます。軽く見られがちな設問ですが、ちょっとした工夫で“人間らしさ”や“好印象”につながる項目です。
趣味の書き方|“安心感”と“人柄”を伝えるさりげないチャンス!
「趣味って…正直、何を見られてるの?」
「適当に書いていいのかな?」
「ゲームとかアニメじゃまずいよね…?」
面接カードに登場する「趣味欄」、軽く見られがちですが、実は面接官にとってはあなたの“人柄”や“ストレス耐性”“職場での付き合いやすさ”を垣間見るポイントだったりします。
趣味欄で見られているポイントはこの3つ!
人間的な魅力や価値観があるか
継続力・ストレス解消力などが見えるか
周囲とのコミュニケーションがとりやすそうか
つまり、「スゴイ趣味」や「珍しい趣味」を書く必要はまったくありません。
でも、「どんなふうに取り組んでいるのか」「その趣味から何を得ているのか」を一言添えるだけで、印象が大きく変わります。
趣味を書くときの5つのコツ
① 結論:趣味は“なんでもいい”!
読書、音楽、散歩、料理、野球観戦、旅行、映画、ランニング――
面接官は「何をしているか」より、「どんな人なのか」を知りたいのです。
堂々と、あなたが楽しんでいることを書きましょう!
② 趣味を書くときは“正直に・具体的に”
「読書」とだけ書くより、「読書(特に歴史小説が好きで、○○作品に感銘を受けました)」など、ちょっとした補足があると印象UP!
③ 注意:「書かない方がいい趣味」もある
政治・宗教的な活動
ギャンブル系(競馬、パチンコなど)
好き嫌いが激しく分かれるもの(例:過激な格闘技観戦など)
ゲーム・YouTubeなど(言い方次第ではOK)
これらは誤解を招く可能性があるので、書き方に注意しましょう。
どうしても書きたい場合は、ポジティブな影響や考え方の成長などを加えると◎。
④ 面接で話が広がるように“軽く話題性”を入れる
旅行 → 「47都道府県制覇を目指しています」
料理 → 「家庭菜園の野菜で季節料理を作るのが楽しみです」
音楽 → 「ピアノを10年以上続けています」
散歩 → 「近所の野鳥観察も趣味の一つです」
“へえ、ちょっと聞いてみたいな”と思わせるような一言があると、面接官との距離がグッと縮まります。
⑤ 職場での“人付き合い”を連想させる書き方も◎
特に社会人受験生や転職組の場合、「この人、職場でうまくやっていけそうかな?」という目線で見られがちです。
✅ たとえば:
「休日にジョギング仲間と大会に出ることが楽しみです」
「家族とキャンプに行く時間が気分転換になっています」
など、「人と関わることが好き」「チームの中で過ごせるタイプ」というニュアンスがあると安心感が出ます。
趣味の書き方テンプレ(初心者向け)
【趣味】○○です。〇年間続けており、□□という理由で取り組んでいます。
特に○○なところに魅力を感じており、今後も続けていきたい趣味です。
🖊【例文①:読書】
読書です。ジャンルは歴史小説やノンフィクションが好きで、1週間に2冊ほど読んでいます。
知識が増えるだけでなく、考え方の幅が広がる点に魅力を感じており、面接対策にも役立っています。
🖊【例文②:ウォーキング】
ウォーキングです。毎朝30分歩いており、季節ごとの風景や野鳥観察を楽しんでいます。
心身のリフレッシュになり、前向きな気持ちで日々を過ごせる習慣になっています。
【より詳しく知りたい方はこちら】
次章では、実際に合格した「面接カードの実例」を紹介します。
どのように志望動機や自己PRをまとめたのか?リアルな内容をそのままお見せします!
合格者の面接カード実例|リアルな記述内容と“改善ポイント”も紹介!
ここまで、面接カードの書き方や各項目のコツをお伝えしてきました。
でも実際、「じゃあ、どんな内容を書けばいいの?」と思った方も多いのではないでしょうか。
この章では、筆者自身が実際に書いて提出し、合格した面接カードの実例を公開します。
※この面接カードは、筆者が30代前半で県職員(小中学校事務職)を受験した際に提出したものです。
重要な注意点
この面接カードは筆者の実体験に基づく一例であり、これが“正解”というわけではありません。
志望自治体や職種、年齢、背景によって最適な内容は異なります。
「こういう構成もあるのか」と参考程度にご覧ください。
▶ 志望動機(実際に書いたもの)
「より直に人の役に立ちたい、お世話になった教員・学校の役にたちたい」前職でも人の役に立つ仕事はできたが、より直に役に立っている感覚を味わう仕事がしたいと思い、改めて本当にしたい仕事について熟考した。結果、人生の中で重要な時期である学校生活に関わり、毎日反応をみながら直に教員や生徒の役に立てる仕事をしたいという思いが強くなった。また、小中学校時代に多大に影響を受けた教員がいたことから、お世話になった教員や学校に恩返しがしたい、役に立ちたいという気持ちから学校で働ける仕事に関心が高まった。
その後、適性を調べるため、児童館職員、塾講師や部活動指導員として生徒と関わり、また学校事務や教員に関する書籍を読み、教師への聞き取りをした結果、私は教える立場よりも子供の学び・生活の質を向上させ、また教員、生徒、保護者や地域住民を幅広く支え、役立てる立場の学校事務がより自分の適した仕事であり、行政職員であった前職の経験も生かせると思い本職を志望した。
▶ 改善したい点(今振り返って思うこと)
結論が冒頭にあるが、少し抽象的でふわっとしている
職務理解を具体的に盛り込めば、より「この人分かってる感」が出せた
事実・行動・経験は多いが、やや詰め込みすぎて読みづらい
- 「だ・である調」ではなく「です・ます調」にすれば良かった
📝 ポイント:合格するためには完璧である必要はなく、「この人はしっかり考えて行動してきたな」と伝わればOKです!
合格者の例から何を学べるか?
この実例で注目してほしいのは、「正解の文章」ではなく、
志望理由が“自分の体験”とつながっていること
「現職→転職」の流れに納得感があること
実際に行動(経験・調査)していることが伝わること
です。
まとめ:実例は“ヒント”として活用しよう
面接カードの実例をそのまま真似するのではなく、
自分の過去の経験
志望先の特性
仕事への思い
を整理しながら、“あなただけの志望動機やPR”に落とし込むことが重要です。
ここでは転職時の面接カードを公開しましたが、大学生のときに受験した際の志望動機も公開していますので興味がある方は下の記事を参考にしてください↓
公務員試験首席合格者の志望動機&自己PR&面接で聞かれた質問・回答を公開!
次章では、よくある質問やつまずきポイントをまとめた「面接カードQ&A」に進みます!
面接カードQ&A|よくある疑問・不安をまるごと解決!

面接カードの記入って、意外と細かいことで悩みがち。
「こんなことで減点されるのでは?」
「形式間違えたら不合格になるのでは?」
…と、不安が尽きない受験生も多いはず。
そこでこの章では、筆者自身や受験仲間の実体験、そして読者からよく寄せられる質問をまとめて、Q&A形式で一気に解決します。
Q1. 面接カードの文字は大きめでもいい?小さく書くべき?
→ 「読みやすさ」が最優先です。
多少大きめでも構いません。
むしろ「文字が小さすぎて読めない」方が印象は悪くなります。
丁寧な字で、読み手がストレスなく読めることが何より大切です。
📝【補足】自治体によっては記入枠のサイズが決まっているため、「字を詰めすぎない」「余白を意識する」といった配慮も◎。
【参考記事】:【公務員試験面接カード】文字は大きさ・字数に決まりはないが下手でもいいから丁寧に書く!
Q2. 字が下手なんだけど大丈夫…?
→ 全く問題ありません。
面接官は書道の審査をしているわけではありません!
大切なのは、「丁寧に書こうとした気持ち」と「読みやすさ」です。
Q3. 誤字脱字をしてしまったら…?
→ まずは訂正方法を確認!
ボールペンで書いている場合:二重線(修正テープ不可)
鉛筆・消せるペンの場合:丁寧に消して書き直せばOK
📝 詳細はこちらの記事で解説しています:
【公務員試験面接カード】誤字・脱字など失敗してしまった場合の対処法
Q4. 封筒の書き方ってどうするの?
→ 多くの受験生が迷うポイント。以下を押さえましょう:
白無地の封筒(角2サイズなど)を使用
表には「面接カード在中」と朱書き
裏面に氏名・住所を記入
書類はクリアファイルに入れて丁寧に封入
📝 書き方の詳細はこちら:
【完全版】公務員面接カードの郵送方法&封筒の書き方マニュアル|添え状・宛名・折り方も解説
Q5. 「である調」と「ですます調」どっちが正解?
→ 結論:どちらでもOK。ただし、統一すること!
途中で「である調」→「ですます調」に切り替わっていると、印象はよくありません。
一貫性を持って、どちらかに統一しましょう。
読みやすさ重視なら「ですます調」がおすすめです。
Q6. 証明写真の服装は?スーツじゃないとダメ?
→ スーツが基本ですが、特に指定がなければ「清潔感」があればOK。
女性の場合はジャケットなしでも問題ないことが多いですが、「面接時と同じ服装」で撮るのが無難です。
📝 詳しくはこちら:
Q7. 他の受験生の面接カードも見てみたい…
→ 以下の記事を参考にしてください↓
【公務員】面接カードの実例・記入例を多数掲載の公務員用面接対策本を紹介!
Q&Aで解決しない場合はどうする?
一人で悩むより、誰かに見てもらうのが一番の近道です。
特に、社会人受験生は周囲に相談できる人が少ないことも多いですよね。
以下のような人に添削をお願いしてみましょう:
大学のキャリアセンター
公務員試験の予備校講師
合格経験のある先輩
ハローワークの支援員
【オンライン】ココナラで元公務員に依頼!
📝 筆者自身も添削サービスを提供中です:
【公務員試験】面接カード添削・想定問答添削・筆記試験問題解説・個別相談(元県職員による個別指導)
次章では「面接カードの添削」の重要性と、依頼時の注意点・おすすめサービスを紹介していきます!
面接カードは添削を受けるべき?|“必須級”の理由とおすすめの依頼先

「面接カードって、自分で一通り書けたからもう大丈夫かな…」
「添削って面倒くさそうだし、恥ずかしいな…」
そう思っていませんか?
結論から言うと、完成した面接カードは必ず第三者に添削してもらうべきです。
自分では気づけない「ズレ」や「もったいない表現」が山ほどあるからです。
なぜ添削が必要なのか?
① 「自己評価」と「他人の印象」はまったく違う!
自分では「具体的に書けたつもり」でも、他人から見ると「何を言いたいのか分からない」こと、よくあります。
読み手の視点に立つことは、面接カードではとても大事です。
② 面接官目線での“チェックポイント”が見えてくる
経験者や専門家に見てもらうと、
話が飛んでいないか
仕事との接点が伝わっているか
説明が長すぎないか/薄すぎないか
といった観点で、面接官の視点で改善アドバイスがもらえるのが大きな強みです。
③ 書き終えたあとの「不安」を払拭できる
「これで本当に大丈夫なのかな…?」というモヤモヤを抱えたまま出すのは、精神的にもつらいものです。
添削を受けて「よし、これでいこう!」と思えると、面接本番への自信にもつながります。
添削を頼む相手|おすすめはこの5パターン!
| 添削相手 | 特徴・メリット |
|---|---|
| 大学キャリアセンター | 就活サポートのプロ。基本無料。学生向けには最適。 |
| 教授・ゼミの先生 | あなたの活動を知っているので、具体的な強みの表現がしやすい。 |
| 公務員試験予備校の講師 | 専門家としての視点で“受かる書き方”を教えてくれる。 |
| 合格した先輩・同期 | 実体験ベースのリアルなアドバイスがもらえる。 |
| ハローワークの職員 | 社会人・転職者には心強い存在。職務経歴の書き方にも詳しい。 |
添削者が周りにいないときは?
→ オンライン添削サービスを活用しましょう。
とくにおすすめなのが、「ココナラ」などで活躍している元公務員や面接専門アドバイザーです。
✅ ココナラの特徴:
自分に合ったアドバイザーを選べる
文章を送るだけで添削してもらえる
価格も1,000円〜3,000円程度と手ごろ
「現役公務員」「元予備校講師」などのプロが多数在籍
添削してくれる人が周りにいない社会人などは、CMで話題の「ココナラ」をぜひ利用してみてください↓
📝 詳しくはこちらで紹介しています:
【公務員試験】独学受験生の面接カード添削(ES添削)や模擬面接は「ココナラ」がおすすめ!
添削を依頼する際の注意点・コツ
✔ 全体像を伝える
志望先(自治体名・職種)
受験の背景(学生か社会人か、転職か)
志望理由や想定される質問内容
をあらかじめ伝えると、より的確なアドバイスがもらえます。
✔「こういう感じにしたい」という要望も伝える
自分らしさを残したい
論理的に整えてほしい
柔らかい印象にしたい
など、方向性を伝えることで添削の“納得度”が上がります。
【PR】筆者(伯爵さん)も添削サービスを行っています
元県職員(技術職・学校事務職で合格経験あり)
合格者からの相談実績100件以上
ココナラ経由でチャット・PDFベースで丁寧に対応します
▶ 詳細・お申し込みはこちら
【公務員試験】面接カード添削・想定問答添削・筆記試験問題解説・個別相談(元県職員による個別指導)
まとめ|面接カードの完成度を一段階引き上げる「最後の一手」
自己分析・職種研究・志望動機の整理――
ここまでやってきた人ほど、あと一歩の「添削」が合否を分けることがあります。
“自分の目”だけで完結しない
第三者の視点でブラッシュアップする
このひと手間が、あなたの面接カードを“合格レベル”へと引き上げてくれます。
次章では、いよいよこの記事の総まとめに入ります!
これまでのポイントを整理しつつ、「合格する面接カード」を仕上げるための最終チェックリストをお届けします。
【まとめ】公務員試験 面接カードの最終チェックリスト|合否を分ける“仕上げの一手”とは?
ここまで、公務員試験における「面接カード」の書き方や注意点、各設問への対応方法、実例、Q&A、添削方法まで網羅的にお伝えしてきました。
面接カードは、ただの提出書類ではありません。
面接本番の進行・評価・印象すべてに影響する、**“合否に直結する最重要アイテム”**です。
この記事で学んだことを振り返ろう!
✅ 面接カードを書く前に準備すべき8つのこと
✅ 志望動機・自己PR・短所・関心事項・趣味の書き方と注意点
✅ 合格者のリアルな実例とそこから学べること
✅ よくある不安・Q&Aとその解決策
✅ 添削の重要性と依頼の方法
最終チェックリスト|提出前に確認しておきたい10のこと
書き終えた面接カード、そのまま出して大丈夫ですか?
以下のチェック項目を1つずつ確認しながら、“合格するカード”に仕上げましょう。
🔲 1. 字は丁寧に書いてあるか?読みにくくないか?
→ 字の美しさより「丁寧さ・読みやすさ」が大切!
🔲 2. 志望動機は「なぜその職種・自治体なのか」まで書けているか?
→ 公務員全体でなく、「この職種」「この自治体」へのこだわりを明示!
🔲 3. 自己PRは「強み+エピソード+活かし方」の構成になっているか?
→ ただの“性格紹介”で終わらせない!
🔲 4. 短所は“改善中のストーリー”になっているか?
→ マイナス印象ではなく「成長する人」と思わせる構成に!
🔲 5. 関心事項は職種と関連性のある話題か?
→ ニュースの深掘りや経験を絡めた表現で差がつく!
🔲 6. 趣味は「人柄や継続力」が見える内容になっているか?
→ 単なる列挙ではなく、「どう楽しんでいるか」まで書けていると◎
🔲 7. 全体を通して“嘘のない、あなたらしい言葉”で書けているか?
→ 作られた文章より、誠実な言葉が一番心に届く!
🔲 8. 内容が長すぎたり、詰め込みすぎて読みづらくないか?
→ 書きたいことを3〜4割削るくらいの「読み手目線」を意識!
🔲 9. 誤字脱字・形式ミス(敬語、句読点、表記ゆれなど)はないか?
→ 印象を下げないためにも必ず「声に出して読み直す」習慣を!
🔲 10. 誰かに添削を依頼したか?フィードバックを反映できているか?
→ “第三者の目”は最強の味方。必ず一度はチェックしてもらいましょう!
合格への近道は、“丁寧に考え、丁寧に書くこと”
面接カードは、たった1〜2枚の紙ですが、その中に
あなたの過去(経験・価値観)
あなたの現在(強み・学び)
あなたの未来(志望動機・貢献)
を詰め込むものです。
表面的な言葉ではなく、あなただけのストーリーを、自分の言葉で丁寧に伝えること。
これこそが、合格する面接カードの条件です。
公務員面接対策でお困りの方へ
筆者は元県職員として、現役の受験生・転職組問わず、公務員試験の相談や面接カード添削を多数行ってきました。
面接カードを見てほしい
面接練習のアドバイスが欲しい
志望動機や自己PRがまとまらない
そんなお悩みがある方は、お気軽にこちらからご相談ください👇
【公務員試験】面接カード添削・想定問答添削・筆記試験問題解説・個別相談(元県職員による個別指導)
最後に
ここまでご覧いただき、本当にありがとうございました!
あなたがこの面接カードを通じて、“自分らしさ”を最大限に表現し、面接で自信を持って話せることを心から応援しています。
公務員試験は長く険しい道のりかもしれません。
でも、「あなたを必要としている職場」は、きっとどこかにあります。