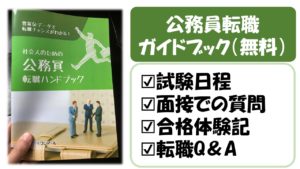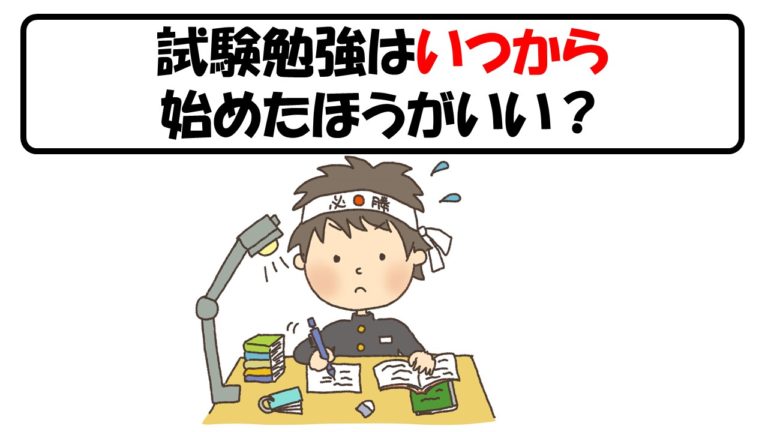社会人が公務員に転職する際に一番のネックになるのは、「教養試験」(筆記試験)です。
日々多忙な毎日を過ごしている社会人にとって、「勉強時間」の確保は頭の痛い問題です。
今回の記事では、「社会人は試験勉強をいつから始めたほうがいいか」、そして「面接対策についてはいつから始めるべきか」を私の実体験をもとに紹介します。
- 公務員試験勉強をいつから始めたらいいか迷っている社会人
- 合格するためにはどのくらいの勉強期間・時間が必要なのか分からない社会人
- 面接対策はいつから始めたらいいか迷っている社会人
に役立つ記事となっています。
- 筆記試験に合格するための勉強期間の目安は、「同じ参考書を3周繰り返す」ことのできる期間
- 社会人の面接対策は一次試験後(筆記試験後)からの短期集中で大丈夫!

社会人の公務員試験勉強はいつから始めるべきか?
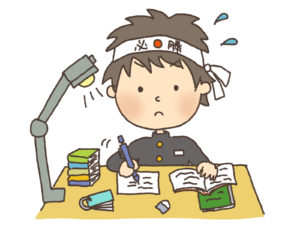
それでは社会人は「いつから勉強を始めるべきか」について紹介します。
私の合格実績と勉強期間
まずは私の合格実績と勉強期間について紹介します。
私は大学4年時(国立大学)に「県庁」と「国」を、また県庁退職後に「公立小中学校事務」と「社会人枠」を全て一発合格しています。
- ○県職員採用試験(大学卒業程度)(2008年)最終合格
- 国家公務員採用試験(一般職)(2008年)最終合格、辞退
- ○県小中学校事務職員採用試験(2018年)最終合格
- ○県職員採用候補者試験(社会人枠)(2018年)教養試験合格、辞退
いずれも筆記試験は7~8割程度の正答率で合格できました。
勉強期間ですが、
- 大学生のときは、2月~6月までの5ヶ月間
- 社会人のときは、7~9月までの3ヶ月間
で合格に至りました。
試験勉強はいつから始めるべきか
社会人が教養試験対策(高卒程度)をいつから始めるべきかですが、私の実体験をベースに「勉強期間の目安」をタイプ別にご紹介します。
注意として、過去に公務員試験の受験経験があるかないかの差は非常に大きいです。
なぜかというと、公務員試験には「一般知能」(判断推理・数的推理・資料解釈)という分野があるからです。
この一般知能は学校では勉強しない分野なので、公務員試験勉強を始めるにあたり初めて学習する必要があります。
そして、やっかいなのが一般知能はある程度まとまった勉強時間が必要となる点です。
そこを配慮して勉強期間の目安を作成しました。
【教養試験(高卒程度)の勉強期間の目安】
- 高卒+公務員試験受験経験ナシ → 6ヶ月間
- 高卒+公務員試験受験経験アリ → 4ヶ月間
- 大卒(国立大学)+公務員試験受験経験ナシ → 5ヶ月間
- 大卒(国立大学)+公務員試験受験経験アリ → 3ヶ月間
- 大卒(私立大学)+公務員試験受験経験ナシ → 6ヶ月間
- 大卒(私立大学)+公務員試験受験経験アリ → 4ヶ月間
この期間は空いている時間を全て受験勉強に専念しての期間です。
ちなみに大手通信教育(ユーキャン)の標準学習期間(教養試験のみ)は6ヶ月と書かれていました。
また、公務員試験合格に必要な勉強時間としては「600時間程度」が目安といわれています。
(参考:「公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法」、著 合格への道研究会、洋泉社)
あと、注意点として、社会人枠の教養試験は「高卒程度」のレベルとなっているところがほとんどです。
しかし、競争倍率が高いため合格するには高得点を狙う必要があり、難易度が高くなっています。
【参考記事】【公務員就職氷河期世代枠】1次試験(教養試験)のボーダーラインは?
勉強期間を考える際に大切なこと

ここまで期間のお話をしてきましたが、合格するために必要な期間を考えるうえで最も重要なのは、
「同じ参考書を3周すること」
です。
その3周する期間がそのまま「必要な勉強期間」に繋がります。
私が合格した際も、勉強期間や勉強時間を考えるにあたり、同じ参考書を3周するにはどのくらいの期間・時間が必要かと逆算して期間を出しました。
なので、人によって学習期間が異なってきます。
できれば、「短期集中(3ヶ月程度)で同じ参考書を3周するのがベスト」、これがもっとも効率的で合格しやすい勉強法です!
なお、使用する参考書については下記記事を参考にしてみてください。
【参考記事】30代社会人の公務員教養試験対策におすすめの参考書!(社会人の勉強法)
社会人の面接対策はいつからがいい?(一次試験後(筆記試験後)
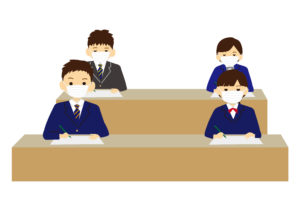
社会人が面接対策を始める時期は、「一次試験後」で十分です。
そもそも社会人は仕事をしながら試験対策をしなければならず、圧倒的に勉強時間が不足しています。
そのうえで面接対策を筆記試験と同時並行で進めていくのは時間的に困難であり、得策ではありません。
そこで、まずは筆記試験勉強に専念をし、一次試験終了後から面接対策を短期集中ですることをオススメします。
一次試験後から面接試験日までの期間は、自治体や試験区分により異なりますが、「おおよそ1~2ヶ月」となっています。
【2023年度公務員試験日程の例】
| 一次試験日 | 一次試験合格発表 | 二次試験日(面接) | |
|---|---|---|---|
| 国家公務員(経験者枠) | 9月3日 | 10月5日 | 10月11日から20日 |
| 東京都(キャリア活用枠) | 8月13日 | 9月21日 | 10月14、15、28、29日 |
| 愛知県(社会人枠) | 9月17日 | 10月6日 | 10月17日から20日 |
| 神奈川県(中途) | 7月28日~ | 9月15日 | 10月2日~ |
社会人は学生と違い、就活で何度も面接対策をすでにした経験があり、面接の基礎は十分できています。
また、実際に仕事を経験しているので、経験談を交えた密な回答が可能なため、面接対策をしすぎても、その効果は薄いと思います。
(学生は時間の許す限り面接対策はしたほうがいいですが)
【要注意】面接カードの出来で面接の良し悪しが決まる!
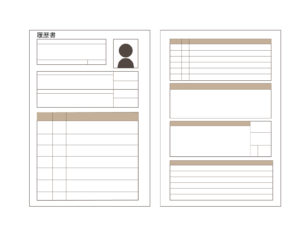
面接対策は一次試験後からで十分ですが、1つ要注意があります!
- 「なぜ現職を退職するのか」(志望動機)
- 「なぜ民間ではなく公務員を転職先にしたのか」(志望動機)
- 「民間で培った力をどう公務員で生かすか」(自己PR)
社会人の面接対策の方法

- 公務員試験の「面接対策用参考書」を1冊読む
- 「セルフディベート」を繰り返す
公務員試験の「面接対策用参考書」を1冊読む
「セルフディベート」を繰り返す
まとめ ~社会人受験生は効率よく対策を行おう~

ここまで、社会人の公務員試験の筆記試験対策と面接試験対策の始める時期について解説してきました。
社会人の面接対策については、
- 事前に面接カードを戦略的に作り込み(1~2週間)
- 一次試験後に想定問答集を作成(数日)
- セルフディベートを繰り返す(時間が許す限り)
- (可能であれば)模擬面接を1~2回
これだけです。
一次試験後から面接試験までの「数週間があれば面接対策は十分」ですので、それまでは筆記試験勉強に専念してください。
何度も言いますが、社会人はとにかく時間が足りません。
足りない中でいかに効率よく対策を行っていくかが合否の分かれ道となります。
筆記試験も面接試験も徹底的に無駄を省いてコスパよく対策を進めていきましょう!