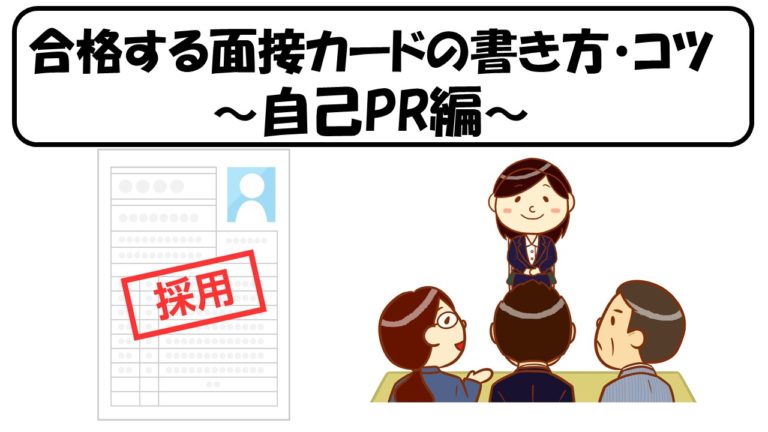公務員試験受験生にとって、避けては通れない「面接カード」の作成。
その面接カードの中でも「自己PR」がうまく書けずに困っている受験生は非常に多いです。
自分のPRをしたことがない大学生は、書くのにかなり手間取りますし、面接でのやりとりを考慮せずになんとなく書いてしまう人もいます。
しかし、この自己PRはあなたという商品を面接官に、自治体に売り込む絶好のチャンスです。
逆に言えば、自己PRは面接での評価に差がつくポイントとも言えます。
しっかり戦略をもって、書くようにしましょう!
今回はそんな公務員試験面接カードの「自己PR」の書き方について、元県職員がご紹介します。
- 面接カードは超重要
- まずは受験自治体の施策や業務内容をしっかり勉強
- 自分の知識・スキル・経験で、業務遂行に役立てそうなことを探す
- 公務員用の面接対策参考書がかなり使える

面接カードは超重要
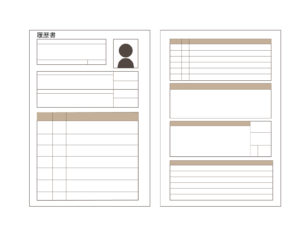
まずは面接カードの重要性について紹介します。
面接時の台本になる
前提として、「面接カード」の内容で合否が決まるわけではありません。
しかし、公務員試験の面接は、基本的に「面接カード」に沿って質問が行われます。
面接官はあなたの面接カードをみながら、
- 疑問に思ったこと
- 確認したいこと
- 興味をもったこと
などを質問してきます。
面接時間は民間に比べ短く(15分程度)、複数人面接官がいるので、1人あたりの面接官ができる質問数は限られています。
面接カードの注意点
面接官の受けを良くしようと思い、見栄を張って話を盛ったり、嘘を書くと、質問で突っつかれたときにボロがでてしまいますので絶対に止めておきましょう。
また、気合を入れすぎて面接カードに事細かに書きすぎると、面接時に質問されてもカードに書いてある内容をただ同じようにしゃべるだけになってしまいますので、聞いている面接官側はなんだか白けてしまいます。
気をつけてもらいたいことは、「面接カード自体は採点の対象ではない」ということです。
面接カードの体裁
【字の汚さ】
汚くても大丈夫ですが、面接官が読める程度にはしましょう。
【字の大きさ】
ある程度大きめに書いたほうが面接官は読みやすいです。
よく印字と同程度の大きさが良いと言う人もいますが、それでは小さい気がします。
【文字数】
欄の9割以上は埋めてください。
真っ黒に文字で埋め尽くすことなく、余白などを適宜とり、全体的にすっきりした見栄えになるようにしましょう。
【誤字脱字】
誤字脱字だけはくれぐれも注意してください。
書き終えたら念入りに見直しをするようにしましょう。
もし間違えた時は以下の記事を参考にしてみてください。
【参考記事】【公務員試験面接カード】誤字・脱字など失敗してしまった場合の対処法(書き直せるなら書き直す)
自己PRの書き方・コツ

つづいて、自己PRの書き方やコツを紹介します。
まずは施策や業務内容をしっかり勉強(これが一番大事)
受験する自治体のHPで施策や業務内容を勉強しましょう!
採用ページに業務内容が掲載されていますし、職種別パンフレット(PDF)が用意されている場合もあります。
自治体独自の「総合5か年計画」などが策定されているので、それを読むと自治体の長期ビジョンが分かり、とてもおすすめです。
総合計画を読むことで、県独自の施策や課題が把握できるため、面接カードが書きやすくなりますし、面接時に具体的な回答ができ、高評価となります。
施策や業務内容を勉強することは自然と面接対策にもつながりますので、時間をかけて重点的に行いましょう。
自分の知識・スキル・経験で、業務遂行に役立てそうなことを探す
業務内容を勉強し把握できたら、今度はその業務を遂行するうえで必要な能力を考えます。
そして、その能力を自分が兼ね備えていることをアピールできれば「自己PR」ができあがります。
例えば、
【大学生の場合】
講義・ゼミ・卒業研究・アルバイト・ボランティア・部活・サークル・その他様々な経験を大学4年間でしてきたと思います。
その中で、できる限り人とかぶらない自分オリジナルの知識・スキル・経験と公務員の業務遂行に必要な能力をつなげます。
【社会人の場合】
社会人では大学の頃のことは書かず、前職で培ってきたスキル・専門知識・経験でアピールしてください。
大学生のことを書くと、この人は社会人になって一体何を学んできたのだろう?と思われかねません。
社会人には様々な職種の人がいるので、大学生よりオリジナリティが出しやすいので有利です。
参考書がかなり使える
公務員の面接や面接カードの書き方については、現職の人事の方が書かれた有名な参考書が毎年発行されています。
公務員試験受験生ならほとんどの人が知っている、あるいはもっているのではないでしょうか。
宣伝みたいに見えてしまうかもしれませんが、本当に使えるので、おすすめしておきます。
(書店で立ち読みしてからでも良いでしょう。)
公務員試験 現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本 2025年度、著 大賀英徳
自己PRの例文

以上のことを踏まえて、自己PRを完成させます。
分かりやすくするため、例文を少しだけ挙げておきますので、参考にしてみてください。
【行政職】
「総合5か年計画のなかで、信州ブランド確立プロジェクトの推進が目標とされています。プロジェクトの成功には県外へのブランド発信が鍵となります。これからの時代はいかにITを駆使して情報発信ができるかが問われており、行政職のなかでもITスキルに長けた人材が必要だと考えます。私は昔からインターネットを利用した情報発信が好きで、大学時代もブログを立ち上げ、有益な情報を発信し続けてきました。また、将来役立つと思い、現在ITスキル関係の資格取得を目指しています。このITスキルを十分にブランド発信などの業務に活かしていきたいと考えています。」
これ分量だとちょっと長文過ぎなのでもう少し短く端的にまとめるようにしましょう。
【技術職】
(福祉職、社会人(営業系)の場合)
「相談業務の仕事で重要な能力は「傾聴力」だと考えます。傾聴するにはまずは相談者との信頼関係がなければ相談者も話しづらいです。そこで、私には営業職で培ったお客様との信頼関係構築力があるので、ぜひ福祉職で活かしていきたいと考えています。」
(福祉職、社会人(事務系)の場合)
「福祉職の業務は相談業務・支援業務がメインとなります。相談を受けたあと、相談者一人ひとりに適した支援プランを考えていくには、市町村や関係機関と連携が必要であり、チームワークが必要不可欠になります。私は前職で事務職として働いていた経験があり、その際、チームの仕事管理を担っており、効率良く業務が進むよう仕事をしていました。その仕事で培ったマネジメント能力を活かし、効率よく支援プラン作成を進めていくなど、福祉職の業務にいかしていきたいと考えています。」
こう書くと、「信頼関係構築力があるとのことですが、構築していくうえで大変だったことや心がけていたことはありますか?」と来ることは予想でき、面接対策もしやすくなります。
大変な思いをして新社会人のころから試行錯誤を繰り返してきたことへの質問なので、経験を踏また深みのある回答ができると思います。
まとめ

ここまで、自己PRの書き方についてご紹介しました。
面接カードの内容は非常に重要で、面接の際の武器となります。
業務内容をよく把握し、その県独自の施策や課題を盛り込んだ自己PRを準備しましょう。
「自己PR」はあなたが自治体に入ることで、どれだけ自治体側にメリットがうまれるのかを面接官に伝えることが重要です。
できるだけ他の受験生にはないあなた独自のスキル・知識・経験でアピールしましょう!
そうすれば、自ずと合格は近づいてきますよ!
応援しています☆
出来上がった面接カードは「ココナラ」で添削サービスをしているので、もしよければご利用ください↓
![]()
【関連記事】