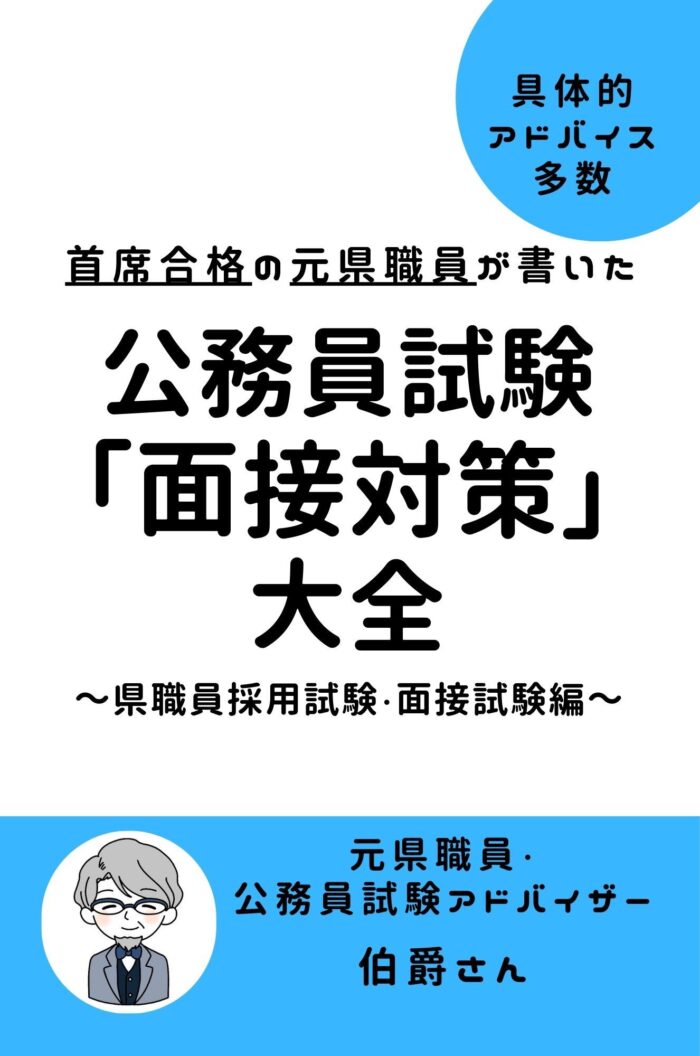公務員試験の合否を大きく左右する「面接試験」。
その中でも特に重要なのが、面接カード(エントリーシート)の記入です。
面接カードは、単なる提出書類ではなく、面接官が質問内容を考えるための「設計図」とも言える存在。
そのため、記入内容次第で面接官の印象が大きく変わり、面接試験の成否を左右することも少なくありません。
この記事では、9年間の県職員経験を持つ私が、実際の受験・指導経験を活かして「志望動機」と「自己PR」の書き方・コツ・例文をわかりやすく解説します。
また、大学卒業後に「県庁」と「国」、さらに退職後に「学校事務」と「社会人枠」で再受験し、すべて一発合格を果たした経験から、具体的なノウハウをお伝えします。
公務員試験対策として、面接カードをどう活用し、どのように書き上げれば良いか、合格を勝ち取るためのポイントを徹底解説します。
大学4年時に「県庁」と滑り止めで「国」を、また県庁を退職してから「学校事務」と「社会人枠」で再受験し、全て一発合格しています。
- ○県職員採用試験(大学卒業程度)(2008年)最終合格、採用
- 国家公務員採用試験(一般職)(2008年)最終合格、官庁訪問は林野庁、内定辞退
- ○県小中学校事務職員採用試験(2018年)最終合格、採用
- ○県職員採用候補者試験(社会人枠)(2018年)一次試験合格、二次試験辞退
面接カードとは?その役割と重要性
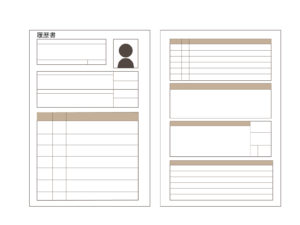
面接カードとは、公務員試験において面接試験前に提出する公式な書類で、「志望動機」「自己PR」「学生時代に力を入れたこと」「特技」など、受験者の基本的な情報を記入するものです。
多くの自治体や官公庁で面接試験前に提出が求められ、その内容が面接の成否に大きく影響します。
面接カードが果たす重要な3つの役割
面接の台本(設計図)としての役割
面接カードは、単なる事前アンケートではなく、面接官が当日どのような質問をするかを決めるための「台本」や「設計図」の役割を担っています。
面接官は、試験前に提出されたカードに目を通し、そこに書かれたエピソードや動機に基づいて質問を考えます。
そのため、記載内容がそのまま面接の質問に反映されると考えるべきです。
例えば:
「学生時代に力を入れたこと」に部活動を記入していれば、「その経験から得た教訓や学び」について深掘りされる可能性があります。
「志望動機」で県の農業支援政策に興味があると書けば、「なぜ農業に興味を持ったのか」や「具体的にどのような支援策に関心があるのか」など、細かく掘り下げられるでしょう。
このように、面接カードは面接の流れを決定づける最重要書類であり、単に空欄を埋めるだけでなく、面接官に「話を聞きたい」と思わせる工夫が求められます。
自己PRの土台としての役割
面接カードは、面接官に対して自分をアピールするための「自己PRの土台」でもあります。
特に志望動機や自己PRの部分は、単に「こうなりたい」や「こういう仕事がしたい」と書くだけでは不十分です。
自分の強みや経験が、その自治体の業務にどう貢献できるかを具体的に示す必要があります。
例えば:
行政職志望の場合:「大学で学んだ〇〇の知識を活かし、県民の生活を支える政策に貢献したい」
技術職志望の場合:「地元の自然環境保護に対する熱意があり、大学生中のボランティア経験を活かし、自然保護施策に貢献したい」
このように、個別具体的なエピソードを織り交ぜることで、面接官に強い印象を与えることができます。
面接官の興味を引くフックとしての役割
面接カードは、面接官が受験者に対して興味を持つきっかけにもなります。
面接は短時間で行われるため、いかに面接官に「もっと話を聞きたい」と思わせるかが重要です。
そのため、面接カードには単に事実を書くだけでなく、面接官の心に引っかかるようなエピソードや具体例を入れることが求められます。
例えば:
「大学時代に農業サークルで地域の活性化に取り組んだ経験」
「前職でのリーダー経験や成果」
「地域の防災活動に積極的に参加し、災害対策の重要性を実感した経験」
こうしたエピソードは、面接官が「この受験者は他の応募者とは違う」と感じるポイントになります。
なぜ面接カードが重要なのか?
面接カードは、単なる提出書類ではなく、面接試験の方向性を決定づける重要なアイテムです。
以下のような理由から、正確かつ効果的な記入が求められます。
面接の流れを決める
自己アピールの基本資料となる
面接官との初接点として、第一印象に影響する
事前準備の有無が明確に反映される
面接カードの出来が悪ければ、面接官の心証が悪くなり、その後のやりとりにも影響する可能性があるため、戦略的な記入が非常に重要です。
面接カード作成時におさえておくべき4つのポイント
面接カードは、単に空欄を埋めるだけではなく、戦略的に作成することが求められる重要な書類です。
ここでは、面接カードを作成する際に必ずおさえておきたい4つのポイントを紹介します。
ポイント1:嘘や誇張は絶対にNG
面接カードには、実際に経験したことや事実に基づくエピソードを記入しましょう。
面接官はプロフェッショナルであり、表面的な言葉や誇張された内容はすぐに見抜かれます。
嘘や誇張は、面接時に突っ込まれると簡単にボロが出てしまい、信頼性を大きく損なうリスクがあります。
具体例:
× 「大学時代、ボランティア活動に積極的に参加し、リーダーシップを発揮しました。」
〇 「大学時代、〇〇のボランティア団体に所属し、〇〇活動を通じて地域社会に貢献しました。」
このように、具体的なエピソードや実績を交えることで、より信憑性の高い自己PRが可能になります。
ポイント2:深掘り質問を意識して書く
面接カードに書かれた内容は、面接官が必ずと言っていいほど深掘りしてきます。
「書いたこと=質問されること」と考え、自信を持って話せる内容のみを記入するようにしましょう。
曖昧な内容や薄い経験は避け、具体的な事実や数字を盛り込むと説得力が増します。
具体例:
× 「私はリーダーシップがあります。」
〇 「大学時代に〇〇プロジェクトのリーダーとして10名のチームを率い、〇〇イベントを成功に導きました。」
このように具体的な実績や結果を記入することで、「なぜそれがリーダーシップなのか?」という質問にも自信を持って答えられるようになります。
ポイント3:適度な余白と簡潔さを意識する
面接カードは、あくまで面接官が質問を準備するための「台本」です。
記入欄を埋めることに必死になりすぎて情報を詰め込みすぎると逆効果です。
面接官は短時間で多数のカードを読みますので、読みやすさと理解のしやすさを重視しましょう。
具体例:
記入欄の9割を目安にする
行間を適度に取り、見た目をすっきりさせる
長文は避け、要点を押さえた簡潔な文章にする
NG例:
「私は大学時代、ボランティア活動、ゼミ活動、アルバイト、サークル活動など、多くの経験を積みました。その中でも〇〇活動に特に力を入れ、〜(以下1000文字続く)」
OK例:
「私は大学時代、〇〇活動に力を入れ、リーダーシップや問題解決力を身につけました。特に〇〇イベントでは〇〇名のチームを率いて〇〇を達成し、組織内での協調性や責任感を学びました。」
ポイント4:読みやすさにも配慮する
面接官が面接カードに目を通す時間は限られています。
そのため、誤字脱字、字の大きさ、行間、字の丁寧さなど、基本的な読みやすさにも注意しましょう。
見た目が悪いと、それだけで「準備不足」や「細かい部分に気を配れない人」という印象を与えかねません。
【字の下手さ】
下手でも大丈夫ですが、面接官が読める程度にはしましょう。
私も字がかなり汚いほうでしたが、可能な限りゆっくり丁寧に書くようにしました。
【字の大きさ】
ある程度大きめに書いたほうが面接官は読みやすいです。
よく印字と同程度の大きさが良いと言う人もいますが、それでは小さ過ぎのような気がします。
【文字数】
欄の9割程度埋めるようなイメージで良いと思います。
真っ黒に文字で埋め尽くすことなく、行間などを適宜とり、全体的にすっきりした見栄えになるようにしましょう。
欄をはみ出すような長文では、見た目の印象は悪いですし、自分の伝えたいことを端的にまとめる能力がないと思われるかもしれません。
【誤字脱字】
誤字脱字は十分注意してください。
慎重に書き、書き終えたら念入りに見直しをしてください。
一旦wordなどで作成し、それを書き写すほうが効率が良いですね。
志望動機の書き方|差がつく5つのポイント
志望動機は面接カードの中でも特に重要な要素です。
「なぜこの自治体を選んだのか?」という質問に対する明確な答えが求められます。
ただし、ありきたりなフレーズや抽象的な表現だけでは、面接官に強い印象を与えることはできません。
ここでは、他の受験生と差をつけるための5つのポイントを紹介します。
それでは志望動機の書き方・コツを5つ紹介します。
- 志望動機の区分化(なぜこの自治体なのか)
- 具体性をもたせる
- オリジナリティを出す
- 志望動機と面接カードの整合性を保つ
- 参考書や情報源を活用する
ポイント1:志望動機の区分化(なぜこの自治体なのか)
公務員試験では、「なぜ民間企業ではなく公務員なのか?」や「なぜ他の自治体ではなく、この自治体を選んだのか?」がよく聞かれる質問です。
この質問に対する答えを明確にするためには、志望動機を以下のように区分化して準備することが効果的です。
志望動機の区分化:
なぜ民間ではなく公務員なのか
なぜ国ではなく地方自治体なのか
なぜ他県ではなくこの自治体なのか
例えば、「地方自治体でなければできないこと」や、「その自治体の独自の施策」に触れると説得力が増します。
具体例:
「私は地元の活性化に貢献したいという強い思いがあり、〇〇県の△△政策に非常に共感しています。特に、〇〇地域で進められている観光振興プロジェクトは、私が大学で学んだ地域経済学の知識を活かせる分野であり、地域社会に貢献する大きなやりがいを感じています。」
このように、単なる「安定」や「地域貢献」だけでなく、具体的な施策や地域の課題に踏み込んだ志望動機が求められます。
ポイント2:具体性をもたせる
志望動機は、抽象的な表現ではなく具体的な事例や経験に基づく内容にすることで、面接官に強く印象づけることができます。
単に「地域貢献したい」や「人々の生活を支えたい」だけでは不十分で、「なぜその自治体なのか?」を説明できる具体的な根拠が必要です。
具体例:
× 「地域に貢献したいからです。」
〇 「〇〇県が取り組む△△プロジェクトに共感し、大学で学んだ〇〇の知識を活かして、地域活性化に貢献したいと考えています。」
さらに効果的なポイント:
統計データや実績を引用する
具体的な施策や地域の課題に触れる
現地視察やインターンシップの経験を盛り込む
例えば、「〇〇県の観光客数は〇〇年から増加傾向にあり、〇〇プロジェクトの成果が大きく貢献していると感じました。こうした具体的な成果に自分も貢献したいと思い、志望しました。」といったように、具体的なデータや経験を示すと説得力が増します。
業務内容・施策などは自治体のHPを利用しましょう。
採用ページに業務内容が掲載されていますし、職種別パンフレット(PDF)が用意されている場合もあります。
ポイント3:オリジナリティを出す
志望動機で最も大切なのは、自分だけのオリジナルエピソードを含めることです。
他の受験生と差別化し、面接官に強く印象づけるためには、自分の経験や強みを活かしたエピソードが必須です。
具体例:
「大学で〇〇学を専攻し、フィールドワークで〇〇県の森林保全活動に参加しました。その際、地域の方々との交流を通じて〇〇の重要性を実感し、この地域に貢献したいと強く感じました。」
また、単に「地元愛」や「地域貢献」だけではなく、自分が具体的にどのような形で貢献できるのかを明確にすることが大切です。
大学生は講義・ゼミ・卒業研究・アルバイト・ボランティア・部活・サークル・インターンシップなど様々な経験を4年間でしてきたと思うので、自分だけの経験談を踏まえて志望動機を書きましょう。
社会人は、前職・現職での経験を志望動機にもりこむようにするとより良い志望動機になります。
ポイント4:志望動機と面接カードの整合性を保つ
面接カードに書いた志望動機と、実際の面接で話す内容が矛盾しないようにすることも重要です。
面接官はカードに記載された内容を基に質問を進めますので、事前にしっかりと準備しておきましょう。
具体例:
もし、面接カードに「〇〇プロジェクトに貢献したい」と書いた場合、「なぜそのプロジェクトに興味を持ったのか」や「そのプロジェクトで具体的に何をしたいのか」など、深掘りされる可能性が高いです。
ポイント5:参考書や情報源を活用する
公務員の面接や面接カードの書き方については、現職の国家公務員人事の方が書かれた有名な参考書が毎年発行されています。
でも公務員試験受験生ならほとんどの人が知っている、あるいは持っているので、本の存在を知らない人だけが損する話ですね。(弱肉強食の世界)
私も愛用していましたし、公務員試験に合格した大学の同級生達も利用していました。
宣伝みたいに見えてしまうかもしれませんが、本当に使えるのでオススメしておきます↓
(ぜひ一度書店で立ち読みしてみてください!)
公務員試験 現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本 2025年度、大賀英徳、実務教育実務教育出版
また、自治体の「総合計画」や「施策パンフレット」は、その自治体が目指すビジョンや課題を知るための貴重な資料です。
これらを活用し、具体的な施策に基づいた志望動機を作成しましょう。
具体例:
「〇〇県の総合計画では、〇〇産業の振興が重点施策として掲げられており、その中でも〇〇プロジェクトには大きな魅力を感じました。私も〇〇の経験があり、この分野で力を発揮できると感じています。」
さらに踏み込むポイント:
自治体の長期ビジョンを調べる
施策パンフレットで具体的な業務内容を把握する
自治体が直面している課題に対する自分の考えを述べる
志望動機の例文(行政職・技術職・社会人)
ここで、参考までに例文を挙げます。
あくまで感覚や形を掴んでもらうための一例ですので、あなた独自の志望動機をしっかり考えて作成してください。
ここで紹介した内容をそのままでいくと、落ちます(深掘り質問されたときに、答えられないので)。
行政職
「私は大学で〇〇学を専攻しています。就職先を検討している中、貴県の業務説明会に参加し、〇〇が課題となっていて、県をあげて取り組んでいるとお聞きし、私が大学で学んできたことが活かせ、かつ県民のお役に立てるのではないかと思い、志望しました。説明会後、総合計画を閲覧したところ、どのプロジェクトとも非常に魅力的に感じたので、この〇〇以外の仕事が担当になっても全力で頑張っていきたいと思います。」
技術職
「大学で野生動物について学んでおり、その知識を活かし、かつ故郷のためになる仕事をしたいと考えていたところ、講義で貴県の先進的な鳥獣被害防除対策について学ぶ機会がありました。その取組に非常に共感したため、実際OBにお会いして業務内容などをお聞きしたところ、私の知識やスキルが十分活かせると思ったのと、OBが非常に熱く語ってくださった姿に、こういう人達と一緒に県民のために頑張りたいと決意が固まり志望させていただきました。」
社会人枠
「私は旅行会社で長年勤めてきました。現職でも十分やりがいを持ってお客様のために働いてきましたが、故郷である貴県で今観光客誘致・インバウンドが課題となっている、そしてプロジェクトが推進されていることを偶然一緒に仕事をさせてもらった県職員の方からお聞きしました。それなら私が旅行会社で培ってきた能力が十分活かせるのではないかと思ったのと、公益的に故郷の旅行業・観光業に携わる人の役に立てる公務員としての姿・働き方に共感したため、今回志望いたしました。」
自己PRの書き方|実務とつなげてアピール!
自己PRは、面接カードの中で最も自分の強みをアピールできる重要な要素です。
ただし、単に「私は〇〇が得意です」と書くだけでは説得力に欠けます。
自分の経験やスキルがどのように業務に活かせるのかを具体的に示すことがポイントです。
ステップ1:施策や業務内容を調べる(これが一番大事)
まず、志望する自治体の業務内容や施策をしっかりと調べることが最優先です。
どんなに優れたスキルや経験があっても、それが自治体の業務と結びついていなければ、説得力がありません。
具体例:
行政職志望の場合:「〇〇県の総合5か年計画では、〇〇プロジェクトが推進されており、これは私が大学で学んだ〇〇の知識を活かせる分野です。」
技術職志望の場合:「〇〇市の環境保全活動は、私が専門とする生態学の知識を活かせるため、非常に魅力を感じています。」
おすすめ情報源:
自治体の公式HP(総合計画や業務紹介ページ)
職種別パンフレット(PDF)
自治体主催の説明会やセミナー
自治体の施策や長期ビジョンに基づく自己PRは、面接官に対して「この受験者はしっかり準備している」という印象を与えます。
ステップ2:自分の経験・スキルを整理する
自治体の業務内容を理解したら、それに関連する自分の経験やスキルを整理しましょう。
特に、自分がどのような成果を上げてきたか、どのような問題解決力やリーダーシップを発揮してきたかを具体的に示すと効果的です。
具体例:
大学生の場合:「ゼミで行った〇〇の研究で、データ分析力とチームワークを磨きました。この経験を活かして、自治体の〇〇プロジェクトに貢献したいです。」
社会人の場合:「前職で〇〇の営業チームをまとめ、〇〇%の売上増加を達成しました。このリーダーシップやマネジメント能力を、自治体の〇〇プロジェクトで活かしていきたいです。」
さらに踏み込むポイント:
具体的な数字や成果を入れる
問題解決のプロセスを示す
自治体の施策と自分の経験をリンクさせる
【参考】
【大学生の場合】
講義・ゼミ・卒業研究・アルバイト・ボランティア・部活・サークル・その他様々な経験を大学4年間でしてきたと思います。
その中で、できる限り人とかぶらない自分オリジナルの知識・スキル・経験と公務員の業務遂行に必要な能力をつなげます。
【社会人の場合】
社会人では大学の頃のことは書かず、前職で培ってきたスキル・専門知識・経験でアピールしてください。
大学生のことを書くと、この人は社会人になって一体何を学んできたのだろう?と思われかねません。
社会人には様々な職種の人がいるので、大学生よりオリジナリティが出しやすいので有利です。
ステップ3:実務との関連性を明示する
自己PRは単に自分の強みを述べるだけでなく、その強みが実際の業務でどう活かせるかを具体的に示す必要があります。
面接官は「この受験者が本当に自治体で活躍できるのか?」を見極めたいと考えています。
具体例:
行政職の場合:「私は大学時代に地域活性化プロジェクトに参加し、地元の商店街でのイベント運営に貢献しました。この経験を通じて、地域住民との信頼関係の大切さや企画運営の難しさを学びました。これらの経験を活かし、〇〇県の地域振興政策に貢献したいと考えています。」
技術職の場合:「大学で〇〇の研究に取り組み、現場でのデータ収集や分析を通じて、環境問題への対応力を磨きました。これらのスキルを活かし、〇〇県の自然環境保護に貢献したいです。」
ステップ4:オリジナリティとエピソードを盛り込む
自己PRで他の受験生と差をつけるためには、オリジナルなエピソードや具体的な実績を盛り込むことが不可欠です。
単なる抽象的な自己評価ではなく、具体的な経験をもとに自己PRを作成しましょう。
具体例:
行政職の場合:「大学での〇〇プロジェクトで、〇〇名のチームを率い、地域イベントの企画・運営を担当しました。結果として、前年に比べて〇〇%の参加者増加を達成し、地域の活性化に貢献できたと感じています。」
技術職の場合:「〇〇の研究室で、環境保全のフィールドワークに参加し、〇〇種の生態調査を行いました。この経験から、現場でのデータ収集や課題解決能力が身に付きました。」
ステップ5:結論で締める(今後の目標も含める)
最後に、自己PRは結論でしっかりと締めくくりましょう。
その際、今後の目標や将来の展望も含めると、より強力なアピールができます。
具体例:
行政職の場合:「これまでの経験を活かし、〇〇県の地域振興や政策推進に貢献し、地域社会に貢献する職員として成長していきたいと考えています。」
技術職の場合:「これまで培ってきた技術や知識を基に、地域の環境保全に貢献し、将来的には〇〇分野でリーダーシップを発揮できる職員を目指します。」
自己PRの例文(行政職・福祉職)
以上のことを踏まえて、自己PRを完成させます。
分かりやすくするため、例文を少しだけ挙げておきますので、参考にしてみてください。
行政職
「総合5か年計画のなかで、信州ブランド確立プロジェクトの推進が目標とされています。プロジェクトの成功には県外へのブランド発信が鍵となります。これからの時代はいかにITを駆使して情報発信ができるかが問われており、行政職のなかでもITスキルに長けた人材が必要だと考えます。私は昔からインターネットを利用した情報発信が好きで、大学時代もブログを立ち上げ、有益な情報を発信し続けてきました。また、将来役立つと思い、現在ITスキル関係の資格取得を目指しています。このITスキルを十分にブランド発信などの業務に活かしていきたいと考えています。」
この分量だとちょっと長文過ぎなので、もう少し短く端的にまとめるようにしましょう。
福祉職
【福祉職、社会人(営業系)の場合】
「相談業務の仕事で重要な能力は「傾聴力」だと考えます。傾聴するにはまずは相談者との信頼関係がなければ相談者も話しづらいです。そこで、私には営業職で培ったお客様との信頼関係構築力があるので、ぜひ福祉職で活かしていきたいと考えています。」
【福祉職、社会人(事務系)の場合】
「福祉職の業務は相談業務・支援業務がメインとなります。相談を受けたあと、相談者一人ひとりに適した支援プランを考えていくには、市町村や関係機関と連携が必要であり、チームワークが必要不可欠になります。私は前職で事務職として働いていた経験があり、その際、チームの仕事管理を担っており、効率良く業務が進むよう仕事をしていました。その仕事で培ったマネジメント能力を活かし、効率よく支援プラン作成を進めていくなど、福祉職の業務にいかしていきたいと考えています。」
こう書くと、「信頼関係構築力があるとのことですが、構築していくうえで大変だったことや心がけていたことはありますか?」と来ることは予想でき、面接対策もしやすくなります。
大変な思いをして新社会人のころから試行錯誤を繰り返してきたことへの質問なので、経験を踏また深みのある回答ができると思います。
面接カードは「面接試験そのもの」だと心得よう
面接カードは、単なる書類ではなく、面接試験の設計図であり、面接官との最初の接点です。
書いた内容がそのまま面接の質問に反映されるため、「面接カードの出来=面接の出来」と言っても過言ではありません。
ここでは、面接カードが面接試験そのものと考えるべき理由と、その効果的な活用法を解説します。
1. 面接の台本としての役割
面接カードは、面接官が質問の方向性を決める基礎資料です。
面接官は、提出されたカードに目を通し、どのポイントを深掘りするかを事前に考えています。
そのため、記載内容がそのまま質問に反映されることが多く、適当に書いたり、曖昧な内容を含めるとリスクが高くなります。
具体例:
志望動機:「地域の課題解決に貢献したい」と書いた場合、「具体的にどの課題に関心があるのか?」や「その課題解決に向けてどのように貢献できるのか?」といった質問が予想されます。
自己PR:「リーダーシップがあります」と書いた場合、「具体的にどのような場面でリーダーシップを発揮したのか?」や「その経験から学んだことは?」と深掘りされる可能性があります。
このように、カードに記載した内容がそのまま面接の流れを決定づけるため、適当に埋めるのではなく、具体的かつ自信を持って話せる内容を盛り込むことが重要です。
2. 自己PRの軸としての役割
面接カードは、自己PRや志望動機の土台でもあります。
特に、「自己PR」や「学生時代に力を入れたこと」は、面接官に自分の強みや個性を伝える大切なパートです。
ここで他の受験生との差別化を図ることが、面接突破のカギになります。
具体例:
行政職志望の場合:「大学時代に〇〇プロジェクトに参加し、地域活性化に貢献した経験があります。これを活かして、自治体の〇〇政策に積極的に取り組みたいと考えています。」
技術職志望の場合:「環境保全に関するフィールドワークで〇〇種の保全活動に取り組みました。現場での実体験を活かし、〇〇県の自然環境保護に貢献したいです。」
このように、単なるスキルや経験だけでなく、その経験がどのように自治体の業務に結びつくのかを示すことが大切です。
3. 面接官の興味を引くフックとしての役割
面接カードは、面接官が受験者に対する興味を引くための「フック」でもあります。
単なる事実を並べるだけでなく、面接官が「この人の話をもっと聞きたい」と思うようなエピソードを盛り込むことで、面接がスムーズに進みやすくなります。
具体例:
独自の経験:「大学時代、〇〇県でインターンシップを経験し、地元の農家と協力して地域ブランドの開発に取り組みました。」
成果の強調:「前職で〇〇プロジェクトを担当し、〇〇%の成果を上げました。この経験から、地域住民との信頼関係の大切さを学びました。」
このように、他の受験生にはないオリジナリティや成果を盛り込むことで、面接官の関心を引きやすくなります。
4. 面接対策の基礎としての役割
面接カードは、面接対策の基礎資料としても機能します。
書いた内容をしっかりと覚え、それに基づいて想定問答を準備することが重要です。
カードに書いたエピソードが面接官から深掘りされるのは避けられないため、事前に具体的な質問に対する回答を準備しておくと安心です。
具体例:
質問例1:「〇〇プロジェクトでリーダーシップを発揮したとのことですが、その具体的な役割や成果について教えてください。」
質問例2:「地元の〇〇課題に関心があるとのことですが、それに取り組む上で最も大切だと考えることは何ですか?」
こうした想定問答を事前に用意することで、面接当日の緊張感を軽減し、スムーズな受け答えが可能になります。
5. 面接官に与える第一印象の重要性
面接カードは、面接官が受験者に対して最初に触れる情報です。
そのため、見た目の清潔感や丁寧さも評価に大きく影響します。
字の大きさ、行間、誤字脱字などにも十分注意を払いましょう。
具体例:
字の大きさ:適度な大きさで読みやすく
行間:適度な余白を取り、詰め込みすぎない
誤字脱字:必ず見直し、ミスを防ぐ
まとめ|あなたの言葉で、伝わる志望動機と自己PRを
面接カードは、単なる提出書類ではなく、面接試験の設計図であり、受験者の人柄や志望度を示す重要な要素です。
ここまで解説してきたポイントを踏まえ、最後に「伝わる志望動機と自己PR」を作成するためのまとめを紹介します。
1. 志望動機は「なぜこの自治体なのか」を明確に伝える
具体性を意識する:その自治体でなければならない理由や、特定の施策への共感を具体的に示す
個別性を重視する:他の自治体でも通用する内容ではなく、その自治体に特化した動機を書く
自分の経験と結びつける:単に「地域貢献したい」ではなく、具体的な経験や実績を絡める
具体例:
「〇〇県は地域振興政策に力を入れており、その一環で〇〇プロジェクトが展開されています。私は大学で〇〇を学び、〇〇地域でのインターンシップを通じてこの取り組みの重要性を実感しました。これまでの経験を活かし、〇〇県の発展に貢献したいと強く感じています。」
2. 自己PRは「自分の強みがどう業務に活きるか」を明示する
実績や経験を具体的に書く:単なるスキルの列挙ではなく、具体的な成果や事例を示す
実務との関連性を強調:そのスキルが実際の業務でどのように活かせるかを明確にする
オリジナリティを出す:他の受験生と差別化できるエピソードを盛り込む
具体例:
「大学時代に地域の活性化プロジェクトに参加し、〇〇名のチームを率いてイベントの企画・運営に携わりました。結果として、前年に比べて〇〇%の参加者増加を達成し、地域社会に貢献する喜びを実感しました。この経験を活かし、〇〇県の地域振興に積極的に貢献していきたいと考えています。」
3. 面接カードは「面接の台本」であることを意識する
書いた内容がそのまま質問に反映される
深掘りされる前提で自信を持って話せる内容を記入する
適度な余白と簡潔さを意識する
具体例:
「〇〇プロジェクトに携わった経験があり、〇〇名のチームを率いて〇〇を達成しました。この経験を通じてリーダーシップと問題解決力を磨くことができました。」
4. 面接カードの見た目も重要
読みやすさ:適度な字の大きさ、行間、誤字脱字のチェックを怠らない
視認性:全体的にバランスよく配置し、読み手の負担を減らす工夫をする
清潔感:字が汚くても丁寧に書けば好印象
具体例:
字の大きさ:適度に大きく、読みやすさを重視
文字数:記入欄の8〜9割を目安に埋める
誤字脱字:作成後に必ず見直し
5. 面接カードは「自分の言葉」で書く
テンプレートに頼らない
ネットや参考書の丸写しは避ける
自分の実体験や感情を反映させる
具体例:
「大学時代に地域のボランティア活動に参加し、〇〇地域の課題に直面しました。その経験から、〇〇県での課題解決に貢献したいと強く感じるようになりました。」
6. 最後に、熱意と意欲を忘れずに
自己PRや志望動機に「情熱」を込める
「どうしてもこの自治体で働きたい」という気持ちを伝える
具体的なビジョンや目標も盛り込む
具体例:
「これまでの経験を通じて培った〇〇のスキルを活かし、〇〇県の発展に全力で貢献したいと考えています。将来的には〇〇の分野でリーダーシップを発揮し、地域社会に大きな影響を与える職員を目指します。」
最後に:合格に向けて準備を重ねよう
面接カードは単なる書類ではなく、あなた自身を面接官に伝える最初のメッセージです。
時間をかけて丁寧に作り込み、「自分の言葉で伝わる志望動機と自己PR」を完成させましょう。
そうすれば、合格は必ず近づいてきます。
良かったらこちらの記事もどうぞ!
- 【まとめ】公務員試験「面接カード」大全(合格する書き方&必ず添削)
- 【公務員】面接カードの実例・記入例を多数掲載の公務員用面接対策本を紹介!
- 【公務員面接カード】「である調」と「ですます調」、どっちがおすすめ?
【添削サービス実施中】
ちなみに、出来上がった面接カードの添削を「ココナラ」上でしているので、気になる方は下記のリンクより確認してみてください。
9年間の県職員&添削歴4年の実績があり、これまで様々な自治体の合格者を輩出しています。
【出版本の紹介】