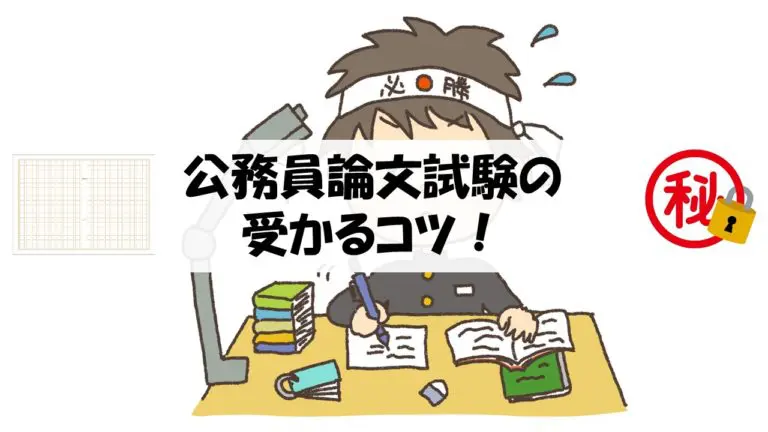公務員試験の中でも、対策が手薄になりがちな論文試験。
せっかく教養試験で高得点がとれても、論文試験に失敗し、不合格になることはなんとしても回避したいところです。
ただ、教養試験や専門試験のように数ヶ月前からしっかり対策する必要はありません。
本記事では、公務員試験論文の書き方のコツについて、元県職員が解説します。
おもに、
- 論文の対策について困っている受験生
- 論文の点数が伸びない受験生
に役立つ内容となっています。
- 論文対策は一週間くらい前からで十分
- 【注意】論文と作文は全く違う!
- すぐ書き始めない!
- 解答時間は足りない
- 誤字脱字などは絶対に避ける!(論文は減点方式)
- とにかく解答用紙をうめる!
- 論文用参考書は解答例を読むだけでいい
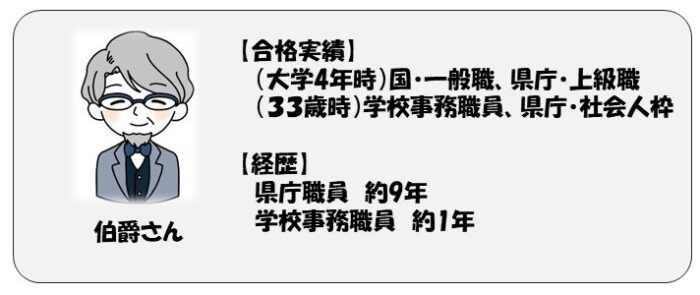
論文試験の配点
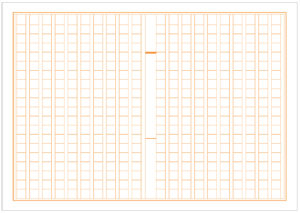
論文試験の配点例をいくつか紹介します。
【2023年度 国家公務員採用一般職試験(大卒程度) 行政区分 第1次試験】
配点:論文1/9、教養2/9、専門4/9、面接2/9
解答時間:1時間
【2023年度 長野県職員採用試験(大卒卒業程度)行政A 第2次試験】
配点:論文300点、面接900点 計1,200点(※論文の合格最低基準120点)
解答時間:1時間30分
解答文字数:1,200字以内
論文試験は、第1次試験で行う県と第2次試験で行う県がありますので、受験案内などで事前によく確認しましょう。
論文試験は高配点ではありませんが、合格には一定の基準以上の点数が必要となります。
論文試験はいつから対策を始めればいい?
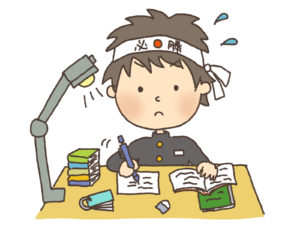
論文試験の対策は、ズバリ「試験直前」から始めればOKです。
なぜなら、大学生は普段講義の課題でレポートを書いているので、十分論述するスキルはすでに身についています。
正直、論文試験の対策をしても、劇的に文章がうまくなる、なんてことはありません。
そのため、以下に紹介する「合格できる書き方」だけをマスターし、あとは論文の参考書の解答例を眺める程度で大丈夫です。
論文試験の合格できる書き方のコツ6選

それでは、ここから論文の合格できる書き方について、具体的に解説していきます。
- 【注意】論文と作文は全く違う!
- すぐ書き始めない!
- 解答時間は足りない
- 誤字脱字などは絶対に避ける!(論文は減点方式)
- とにかく解答用紙をうめる!
- 論文用参考書は解答例を読むだけでいい
【注意】論文と作文は全く違う!
論文試験は決して作文ではありません。
意外とここを間違えてしまう受験生がいます。
論文試験で、「ですます調」でなんとなくテーマに対する感想を書くような作文をしてしまうと、間違いなく落ちます。
あくまで「論文」ですので、テーマに対して、いかに論理的に自分の意見を述べられるかが重要です。
あと、論文なので、基本「である調」を使ってください。
すぐに書き始めない!
試験開始後、すぐに多くの人が一斉にガリガリ書き始めます。
ですが、残念ながらその受験生達は途中でペンが止まることでしょう。
論述する解答時間が1時間30分ある中で、まずは10分くらいかけて、論述する内容の「骨格(スキーム)」を、十分に練りましょう。
このスキームがさえうまく固まれば、あとはひたすら文字を埋めていく作業になります。
スキームを決めずに書き始めると、論点がずれてしまったり、起承転結がうまくいかなかったりと書いている途中で問題が発生し、最悪全部消して書き直しという落ちるパターンになりかねません。
「序論」(テーマについての一般的な背景)→「課題」(2~3つ挙げる)→「対策」(課題であげた点にマッチするように具体例2~3提案)→「結論」
大事なポイントは、「結論」の部分で文字数を最終調整し、問題用紙を9~10割埋めるように書き上げましょう。
高度なテクニックですが、論述してそれを解答用紙ほぼピッタシにきれいに仕上げると、当然評価は上がります。
解答時間は足りない
90分の試験時間の場合、スキームで10分使い、誤字脱字等の見直しで10分、つまり実質70分で書き上げなくてはいけません。
普段レポートをwordなどで作成することに慣れてしまっていて忘れがちですが、手書きは時間がかかります。
スキームが決まったら、あとはどんどんスピード感をもって書き進めてください。
誤字脱字などは絶対に避ける!(論文は減点方式)
論文試験の基本の考え方は、「満点を目指すのではなく、合格ラインを目指すこと」です。
高得点を目指して、「ものすごい良い案を考えてやるぞ」と意気込むと時間が足りなくなったり、途中で論理展開が破綻しやすくなります。
はっきり言って、内容ではあまり差はつかないと思ってください!
これは採点者の立場になれば分かりますが、「この案を提案できれば満点」、そんな採点基準はありません。
採点者の主観で採点を決めることは合ってはならないことです、公務員試験には公平性が求められます。
なので、論文試験は「減点方式」で採点を行っていると考えたほうが良いです。
以下、減点項目の例をいくつか挙げておきます。
【減点項目例】
- 誤字脱字がないか
- 送り仮名を間違えていないか
- 論理展開が破綻していないか
- 現実的に実行不可能な提案をしていないか
- 時間が足りず、文章が途中で途切れている
- 解答用紙の半分しか書いていない
- 解答用紙を超過してしまっている
- 段落の書き始めは1マス空けているか
- 行の最後の句読点は文字と一緒のマス目の中に書いてあるか
- 小さい「っ」「ゃ」などを1マスに1文字で書いているか
- 会話文の終わりの句点とかぎかっこは、同じ1つのマス目に書いているか
- 改行を適宜行っているか
※句読点など書き方のルールについてはしっかり暗記しておきましょう。
とにかく解答用紙をうめる!
「解答用紙をうめる」、これが最重要です!
なにがなんでも解答用紙の「8割以上」は絶対うめてください。
文字数が少なすぎると、どんなに内容が完璧でも、大幅減点されると考えておいてください。
内容100点満点で文字数が5割しか埋まってない答案と、内容80点で文字数が8~10割埋まっている答案なら、後者が正義です!
ですが、解答用紙を超過してしまうのは絶対駄目です。
【論文試験】
- 国家公務員採用試験「文章による表現力、課題に関する理解力などをみる」
- 愛知県職員採用試験「必要な思考力、表現力等をみる」
とあり、具体的に「表現力」と表記しています。
論文用参考書は解答例を読むだけでいい
どれでもいいので論文用の参考書を一冊だけ買ってください。
そして解かなくていいので、解答例だけ読んでください。
なんとなく、こんな感じでまとめれば良いんだなという感覚を掴んでください。
そして先程挙げたスキームを自分なりに設定すれば、それで論文試験対策は準備OKです!
論文試験の平均点&ボーダーライン

論文試験の平均点やボーダーラインを公表している自治体はかなり少ないです。
今回は、私が調べた全都道府県・全政令指定都市のなかで、以下の自治体のもの(行政職・地方上級のみ)を紹介します。
- 北海道(引用:令和4年北海道行政職員等採用試験合格者の平均点等一覧)
- 山口県(引用:令和4年度山口県職員採用大学卒業程度試験及び山口県保健師採用試験の実施結果(平均点))
- 大分県(引用:令和4年度大分県職員採用上級・中級・医療Ⅰ試験実施結果)
| 自治体 | 試験区分 | 平均点(得点率) | ボーダーライン(得点率) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 一般行政A(第1回) | 52.4% | 40% |
| 山口県 | 行政 | 60.3% | ー |
| 大分県 | 行政 | 74.6% | ー |
唯一ボーダーラインを公表していた北海道では、ボーダーライン40%となっていました。
基準点(この点を超えないとその時点で不合格)さえを超えていれば、合格者の論文試験のボーダーラインは決して高くないのかもしれません。
まとめ
以上、論文試験の受かる書き方について、解説してきました。
私が受験した際の論文テーマは「高齢化社会における公共交通機関への行政の関わり方」でした。
一斉に周りの受験生がガリガリ書き始める中、一旦深呼吸をして、まずは「スキーム」を考え始めました。
問題用紙の隅に、スキームを作り、「良し、これで大丈夫!」という確信のもと、一気に書き終え、じっくり見直す余裕さえありました。
結局、対策らしい対策はほとんどしませんでしたが、論文試験は無事乗り越えられました。
受験生は教養試験・専門試験が最優先!を忘れずに、受験直前の息抜き程度に、この記事で紹介した「合格できる書き方」だけ覚えて、あとは直前にちょこっと解答例をいくつか読むだけで大丈夫です。
変に気負って、いくつも論文用の問題集を買って、結局ほぼ手つかずのまま本番に臨む、なんてことのないようにしましょう。
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます☆
【論文対策が不安な人は、予備校(通学・通信講座)を利用すれば論文も添削してもらえます↓】
【関連記事】