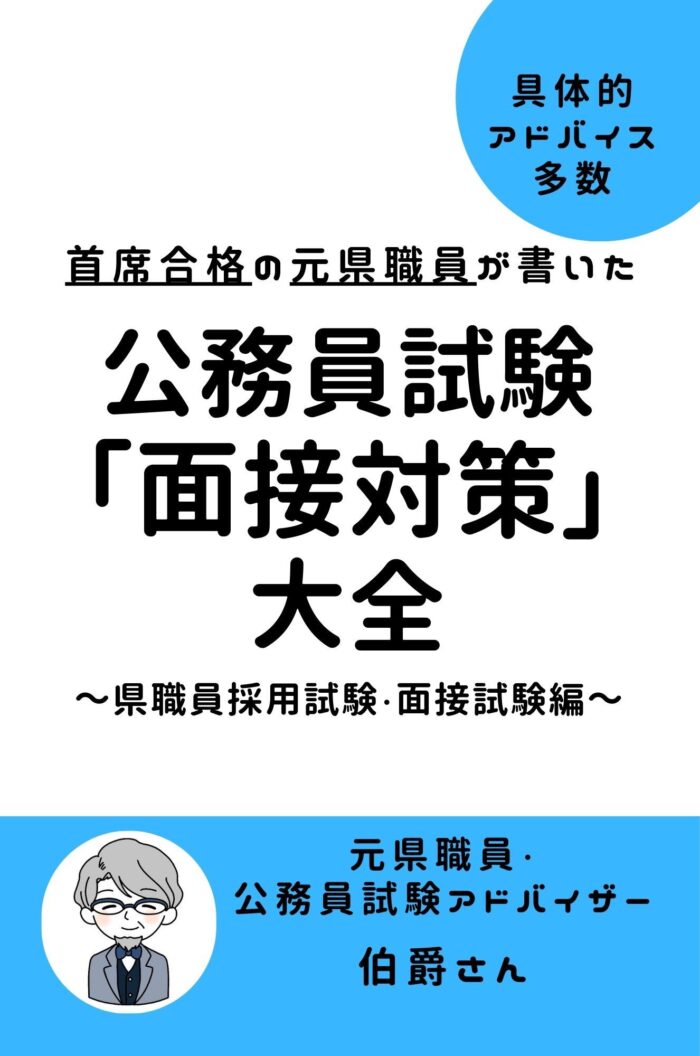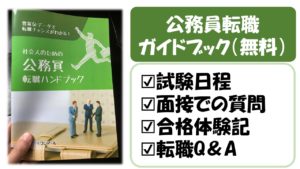公務員試験の難しさは「教養試験の科目数の多さ」と「面接対策」にあります。
元々勉強時間の確保が難しい社会人にとって、いかに効率よく短期間で対策できるかがポイントとなります。
今回の記事では、独学で勉強する社会人におすすめの「教養試験の独学勉強法」「面接対策」を、元県職員で公務員から公務員への転職経験もある私が紹介します。
- どうやって勉強したらいいか分からない社会人
- 勉強法のコツを知りたい社会人
- 忙しくて勉強にあまり時間を割けない社会人
- 公務員の面接対策を知りたい社会人
に役立つ記事となっています。
【私の公務員試験合格実績】
私は大学4年時に「県職員(地方上級)」と「国家公務員(一般枠)」に合格、また県職員退職後に同じ県の「県職員(小中学校事務)」と他県の「県職員(社会人枠)」を再受験し全て一発合格しています。
- ○県職員採用試験(大学卒業程度)(2008年) 最終合格
- 国家公務員採用試験(一般職)(2008年) 最終合格、辞退
- ○県小中学校事務職員採用試験(2018年) 最終合格
- ○県職員採用候補者試験(社会人枠)(2018年) 教養試験合格、辞退
全ての教養試験を7~8割程度の正答率で合格しています。
勉強期間は大学時代5ヶ月間、社会人時代3ヶ月間です
社会人におすすめの公務員試験教養「独学」勉強法
私が実際に行った勉強法をもとに「社会人におすすめの独学勉強法」をズバリご紹介します。
社会人の具体的な教養試験独学勉強法
- 「参考書:公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法」を読み込み、勉強法をマスター(数日程度)
- 「参考書:初級公務員一般知識らくらくマスター」をさくっと一周終わらせて、知識をある程度思い出させる(2週間程度)→その後毎日寝る前に読み続ける。
- 「参考書:畑中敦子の初級ザ・ベストプラス」で一般知能を優先的に勉強(3回繰り返す)
- 一般知能と同時に「参考書:新・初級スーパー過去問ゼミ」で一般知識をやり込む(捨て科目は一切勉強しない)
- 「文章理解(英文・現代文)」は毎日過去問を1問ずつ解く。
- 「参考書:過去問350」(余裕があれば)
※ここでは高卒程度レベルの教養試験について扱っています。自治体によっては社会人枠の教養試験が大卒程度レベルとなっている場合もありますのでご注意ください。
試験勉強期間は3ヶ月間を想定しています。
毎日の勉強時間は、3ヶ月間で参考書を3回繰り返すことができる時間を逆算して求めてください。
社会人におすすめの参考書
30代独学で公務員試験(小中学校事務職と社会人枠)に合格した私が「教養試験」の勉強で実際に使用した「参考書」を紹介します。
大学4年時に受験したときの参考書が残っていましたが、「地方上級・大卒程度」用だったので「地方初級・高卒程度」用に全て買い直しました。
どちらも勉強して分かりましたが、それぞれに問題の難易度やクセがあるので、試験区分専用の参考書で勉強したほうが良いです。
勉強法の参考書
「公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法(2023年度版)」合格への道研究会、エクシア出版
↑地方上級用しかありませんが、地方初級にも役立つことはたくさん書いてあります。
「公務員試験マル秘裏ワザ大全(国家一般職高卒・社会人/地方初級用)」津田秀樹、エクシア出版
一般知識の参考書
「初級公務員一般知識らくらくマスター」資格試験研究会、実務教育出版
「公務員試験 高卒程度・社会人 初級スーパー過去問ゼミ 社会科学」資格試験研究会、実務教育出版
「公務員試験 高卒程度・社会人 初級スーパー過去問ゼミ 人文科学」資格試験研究会、実務教育出版
「公務員試験 高卒程度・社会人 初級スーパー過去問ゼミ 自然科学」資格試験研究会、実務教育出版
一般知能の参考書
「公務員試験 高卒程度・社会人 初級スーパー過去問ゼミ 文章理解・資料解釈」資格試験研究会、実務教育出版
「畑中敦子の初級ザ・ベストNEO 判断推理」畑中敦子、エクシア出版
「畑中敦子の初級ザ・ベストNEO 数的推理・資料解釈」畑中敦子、エクシア出版
その他の参考書
「公務員試験 速攻の時事」資格試験研究会、実務教育出版
「公務員試験 高卒程度・社会人 初級スーパー過去問ゼミ 適性試験」資格試験研究会、実務教育出版
この2冊は自治体によっては不要の可能性もあるので、受験案内で出題内容をよく確認して、必要だったら準備してください。
もし、全ての参考書を3回以上繰り返して、他の参考書で力試しをしたいという方は以下の過去問をおすすめします。
「地方初級・教養試験 過去問350」資格試験研究会、実務教育出版
捨て科目
イメージとしては、「大学共通入学テスト(センター試験)全科目よりも多い科目数の試験」だと思ってもらえば良いです。
【一般知識】時事、政治経済、思想、世界史、日本史、地理、文学芸術、国語、数学、物理、化学、生物、地学
これだけ範囲が広いので、その全てを網羅的に勉強することは非常に困難です。
そこで、受験生はあらかじめ一切勉強しない科目、いわゆる「捨て科目」を事前に決めることがあります。
特に、仕事で忙しく勉強時間の確保が難しい社会人こそ「捨て科目」を多く作り、効率よく勉強することが合格への近道になります。
特に勉強時間が多大にかかる「暗記系科目」や「苦手科目」を中心に思い切って捨てましょう。
捨て科目の選び方
捨て科目の選び方ですが、重要なことは、
「出題数が多い科目(配点が多い科目)は絶対に捨ててはいけない」
ということです。
公務員試験の特徴として、「一般知能」は出題数が多く、「一般知識」は一科目当たりの出題数が少ないです。
なので、捨てる科目は「一般知識」から選ぶのがポイントです。
なお、捨て科目を決める際は、受験する自治体の出題数(配点)を必ず確認してから選んでください。(自治体ごとで出題数が変わります)
出題数(配点)の例
2024年度国家公務員社会人枠の出題数の例を挙げます。
国家公務員(経験者採用枠)30題 一般知能24題(文章理解8題、判断推理・数的推理・資料解釈16題)、一般知識6題
国家公務員では圧倒的に一般知能の出題数が多いことが分かります。
都道府県や市町村もほぼ同様な傾向です。
(最近はそもそも教養試験を課していない自治体もたくさんあるので、各自治体の受験案内で科目をしっかり調べてください)
捨ててはいけない科目
上記の出題数を踏まえると「捨ててはいけない科目」は以下のようになります。
- 一般知能の全科目(文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈)
- 社会事情(時事)
- 政治・経済
捨てていい科目
社会事情、政治・経済以外の一般知識の科目で、
「苦手としている科目」
「勉強に時間がかかる科目(コスパが悪い科目)」
は思い切ってバッサリ捨てましょう!
無理に全部の科目をやらなきゃいけない思考でいると落ちます、完璧主義は捨ててください。
社会人の中で、仕事が忙しすぎて勉強時間が全く確保できない、あるいは試験日まであと1~2ヶ月しかないという追い込まれた状況の人は、捨ててはいけない科目以外の科目を「全捨て」という選択もありだと思います。
ただ、全捨てしても試験当日は解答だけはしてください、5題に1題は当たる確率ですので。(選択肢が5つあるため)
参考書を短期間で3回繰り返すことが最も重要
勉強法のなかで最も大切なことは、「短期間での参考書3回繰り返し」です。
逆にいえば、短期間で3回繰り返すことができれば、試験本番での得点率7~8割もみえてきます。
絶対してはいけないことは、「参考書を一回終わらせたから、別の新しい参考書を買う」ことです。
ただし、文章理解だけは日々新しい問題を解いたほうがいいので、参考書をやり終えたら新しい参考書を買ってください。
また、短期間で3回が大切です。
1年で3回繰り返せたとしても、繰り返しを始める頃には1回目に覚えたことが抜け落ちてしまっています。
これでは勉強効率は著しく落ちます。
せっかく勉強に取り組むからには、その期間だけはプライベートを犠牲にしてでも「短期集中」で勉強に時間を割き、なるべく「短期決戦」で合格を勝ち取りましょう。
社会人の公務員試験勉強はいつから始めるべきか?
社会人が教養試験対策(高卒程度)をいつから始めるべきかですが、私の実体験をベースに「勉強期間の目安」をタイプ別にご紹介します。
注意として、過去に公務員試験の受験経験があるかないかの差は非常に大きいです。
なぜかというと、公務員試験には「一般知能」(判断推理・数的推理・資料解釈)という分野があるからです。
この一般知能は学校では勉強しない分野なので、公務員試験勉強を始めるにあたり初めて学習する必要があります。
そして、やっかいなのが一般知能はある程度まとまった勉強時間が必要となる点です。
そこを配慮して勉強期間の目安を作成しました。
【教養試験(高卒程度)の勉強期間の目安】
- 高卒+公務員試験受験経験ナシ → 6ヶ月間
- 高卒+公務員試験受験経験アリ → 4ヶ月間
- 大卒(国立大学)+公務員試験受験経験ナシ → 5ヶ月間
- 大卒(国立大学)+公務員試験受験経験アリ → 3ヶ月間
- 大卒(私立大学)+公務員試験受験経験ナシ → 6ヶ月間
- 大卒(私立大学)+公務員試験受験経験アリ → 4ヶ月間
この期間は空いている時間を全て受験勉強に専念しての期間です。
ちなみに大手通信教育(ユーキャン)の標準学習期間(教養試験のみ)は6ヶ月と書かれていました。
また、公務員試験合格に必要な勉強時間としては「600時間程度」が目安といわれています。
(参考:「公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法」、著 合格への道研究会、洋泉社)
あと、注意点として、社会人枠の教養試験は「高卒程度」のレベルとなっているところがほとんどです。
しかし、競争倍率が高いため合格するには高得点を狙う必要があり、難易度が高くなっています。
勉強期間を考える際に大切なこと
ここまで期間のお話をしてきましたが、合格するために必要な期間を考えるうえで最も重要なのは、
「同じ参考書を3周すること」
です。
その3周する期間がそのまま「必要な勉強期間」に繋がります。
私が合格した際も、勉強期間や勉強時間を考えるにあたり、同じ参考書を3周するにはどのくらいの期間・時間が必要かと逆算して期間を出しました。
なので、人によって学習期間が異なってきます。
できれば、「短期集中(3ヶ月程度)で同じ参考書を3周するのがベスト」、これがもっとも効率的で合格しやすい勉強法です!
社会人の面接対策の方法
- 公務員試験の「面接対策用参考書」を1冊読む
- 「セルフディベート」を繰り返す
公務員試験の「面接対策用参考書」を1冊読む
「セルフディベート」を繰り返す
社会人の面接対策はいつからがいい?
社会人が面接対策を始める時期は、「一次試験後」で十分です。
そもそも社会人は仕事をしながら試験対策をしなければならず、圧倒的に勉強時間が不足しています。
そのうえで面接対策を筆記試験と同時並行で進めていくのは時間的に困難であり、得策ではありません。
そこで、まずは筆記試験勉強に専念をし、一次試験終了後から面接対策を短期集中ですることをオススメします。
一次試験後から面接試験日までの期間は、自治体や試験区分により異なりますが、「おおよそ1~2ヶ月」となっています。
【2024年度公務員試験日程の例】
| 一次試験日 | 一次試験合格発表 | 二次試験日(面接) | |
|---|---|---|---|
| 国家公務員(経験者枠) | 9月29日 | 10月24日 | 11月2日~4日 |
| 東京都(キャリア活用枠) | 8月18日 | 9月19日 | 10月12、13、26、27日 |
| 愛知県(社会人枠) | 9月22日 | 10月16日 | 10月23日~29日 |
| 神奈川県(中途) | 8月13日まで | 9月13日 | 10月3日~17日 |
社会人は学生と違い、就活で何度も面接対策をすでにした経験があり、面接の基礎は十分できています。
また、実際に仕事を経験しているので、経験談を交えた密な回答が可能なため、面接対策をしすぎても、その効果は薄いと思います。
(学生は時間の許す限り面接対策はしたほうがいいですが)
【要注意】面接カードの出来で面接の良し悪しが決まる!
面接対策は一次試験後からで十分ですが、1つ要注意があります!
- 「なぜ現職を退職するのか」(志望動機)
- 「なぜ民間ではなく公務員を転職先にしたのか」(志望動機)
- 「民間で培った力をどう公務員で生かすか」(自己PR)
1週間前からの面接対策の方法
今回の方法は模擬面接ができない社会人向けの一週間前からの面接対策の方法を、私の経験をもとにご紹介します。
なお、可能な受験生は必ず模擬面接や併願をして、面接の場数を増やすことを強くおすすめします。
数回でも行うことでコツをつかめ、飛躍的に面接は上手になります。
【6~7日前】公務員試験の面接対策本を読む
【3~5日前】想定問答集の作成
公務員試験の面接は、基本的に事前に提出してある「面接カード」をもとに進められます。
面接官は面接カードの内容から「質問する項目」・「深堀りしたい項目」を決めています。
(面接カード以外からの質問も多少あります)
そのため、自分が面接官の立場に立って質問を考え、さらに回答まで作成しましょう。
とても面倒な作業で多少時間もかかりますが、ここがもっとも重要、合否の分かれ目です!
しっかり時間をかけて作成しましょう。
【参考記事↓】
【公務員面接試験】想定質問リスト150選!合格には想定問答集作りが必須!
朗報ですが、学生に比べて社会人は質問される部分・深掘りされる部分がおおよそ決まっています。
- 「なぜ退職したいのか」
- 「なぜ民間ではなく公務員を志望したのか」
- 「今の会社でどんなスキルを習得し、それを公務員としてどう生かせるか」
- 「現職でもっとも失敗した体験談を教えて下さい」
など、ほぼ仕事がらみになります。
【1~2日前】セルフディベートの繰り返し
あとは作成した想定問答集を利用してひたすら自分一人でセルフディベートを繰り返します。
一字一句すべてを覚えるのではなく、キーワードを覚えて本番ですらすらと答えられる程度になっていればOKです。
暗記して答えると、試験本番で思い出せなくなったときに詰まって沈黙してしまいます。
沈黙は致命的なミスになるので、丸暗記は避けましょう。
ただし、ほぼ必ず聞かれるであろう「志望動機」などについては完璧に暗記して、スムーズに答えられるようにしておきましょう。
まとめ~社会人受験生は効率よく対策を行おう~
ここまで、社会人の公務員試験の筆記試験対策と面接試験対策について解説してきました。
何度も言いますが、社会人はとにかく時間が足りません。
足りない中でいかに効率よく対策を行っていくかが合否の分かれ道となります。
筆記試験も面接試験も徹底的に無駄を省いてコスパよく対策を進めていきましょう!
ただ、受験者の基礎学力しだいでは「独学」を避けた方が良い場合もあります。
- センター試験を受験しなかった人
- 高校生のときにあまり勉強しなかった人
- 独学が苦手な人(モチベーションが維持できない人)
- お金に余裕がある人
- 参考書選びに時間をかけたくない人
は独学ではなく、サポートが手厚い公務員予備校の「通信講座」などの勉強法も検討してみてください。
【関連記事】