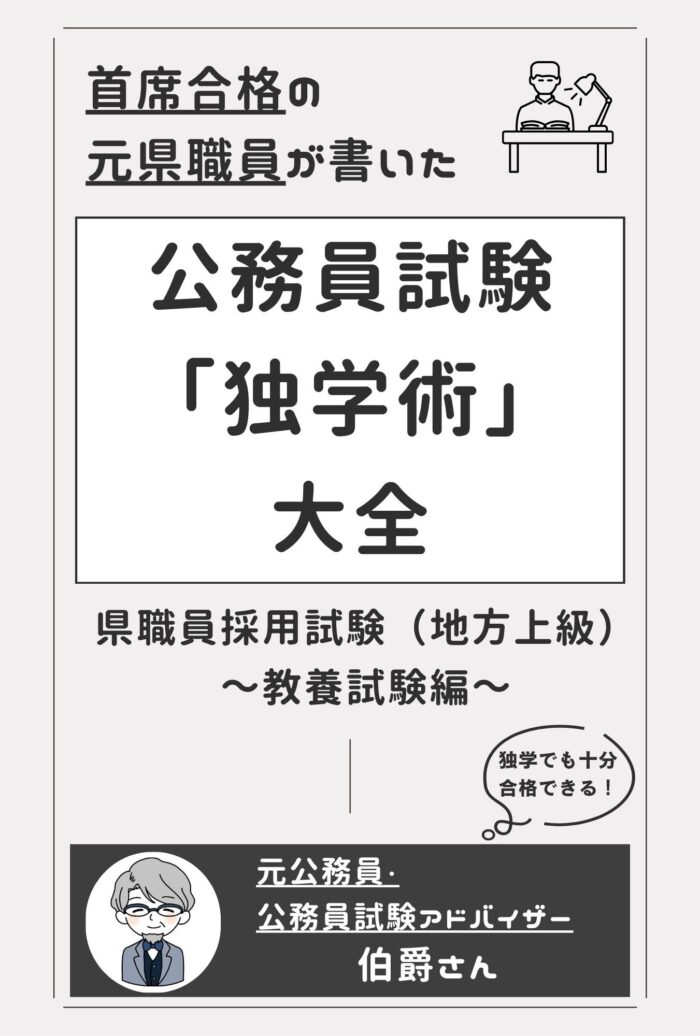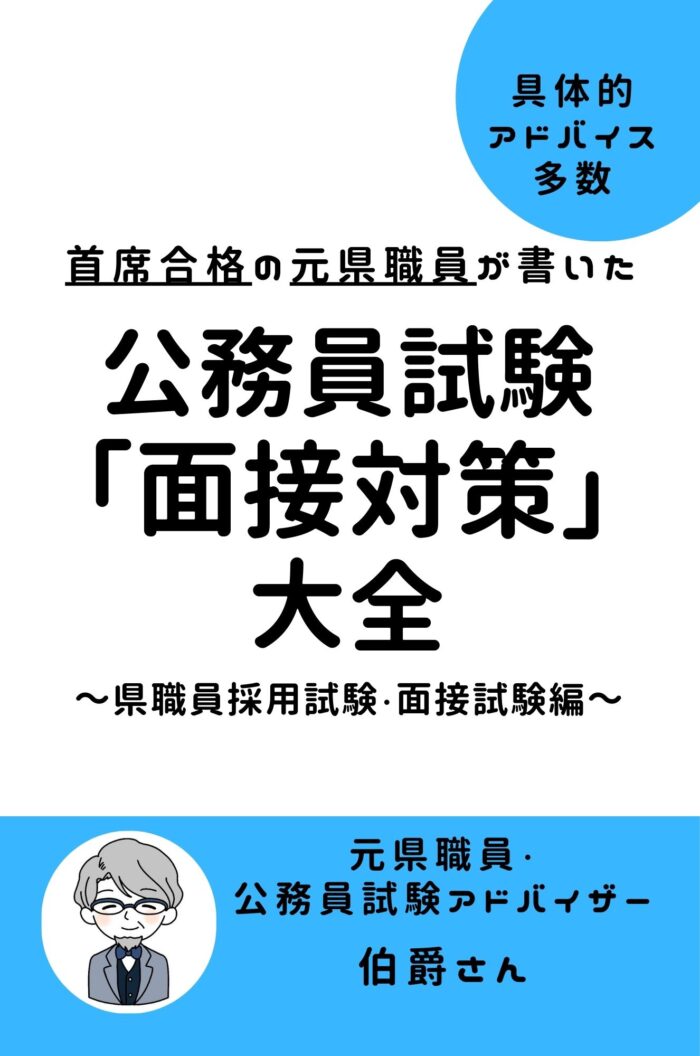「公務員試験って、やっぱり若い人が有利なの?」
「30代や40代、社会人からでも合格している人はいる?」
「受験生や合格者の年齢や職業の実態を知りたい!」
公務員試験を目指すみなさんのなかには、こんな疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に社会人から挑戦する場合、「今さらこの年齢で大丈夫だろうか…」と不安になることもあるかと思います。
実は、私も県職員を目指していた頃、同じように悩みました。
最近は、人生100年時代やキャリアの多様化が進み、「社会人経験を活かして公務員に転職したい」「民間で数年働いてから公務員を目指す」という方が年々増加傾向にあります。
ですが、ネット上の情報だけでは「実際の合格者は何歳くらい?」「どんな職業の人が受かっているの?」というリアルなデータは意外と見つかりにくいものです。
このページでは、「公務員試験 年齢」「公務員試験 職業」「公務員試験 社会人」という3つのキーワードを中心に、
一般枠と社会人枠の違い
受験生・合格者の年齢構成(最新データつき)
実際に合格している社会人・職業別の割合や特徴
筆者や合格者のリアルな体験談
――など、「合格者のリアル」を徹底解説します。
特に、年齢や職業で受験を迷っている方が一歩を踏み出せる内容になるよう、元県職員である私自身の視点も交えて分かりやすくまとめました。
【年齢や職業で迷う方こそ“この記事を読んでほしい”理由】
実際、公務員試験の合格者には幅広い年齢・職業の方がいます。
もちろん現役大学生が多いのも事実ですが、「社会人からの転職組」や「年齢制限ギリギリでチャレンジして見事合格!」という例も少なくありません。
「受験年齢制限ギリギリだけど、自分と同じ境遇の人は合格している?」
「現職公務員・民間・無職、どんな職業の人が多いの?」
「社会人枠なら何歳まで合格チャンスがある?」
このような悩み・疑問を抱えている方は、データと実例を通して「不安を自信に変える」きっかけにしていただければ嬉しいです。
【筆者プロフィール:元県職員・社会人受験経験者】
私自身も社会人を経て県庁職員に転職した経験があり、30代前半で受験しました。
受験生時代は「この歳からでも本当に受かるのか…」と何度も不安になりましたが、実際には同じように社会人経験者や年齢制限ギリギリで合格した方とも出会いました。
そのリアルな実感も交えながら、公務員試験の「年齢・職業」の本音をお伝えしていきます。
公務員試験の受験年齢と「一般枠・社会人枠」の違いを理解しよう
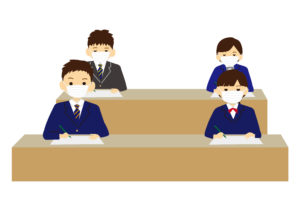
公務員試験を目指す際に、最初に知っておきたいのが「受験できる年齢」と「受験枠の種類」です。
この部分を正しく理解していないと、自分の年齢や経歴を理由に「受験は無理かも」と早合点してしまう方も少なくありません。
一般枠(新卒・既卒含む)の特徴
まず、「一般枠」と呼ばれる区分です。
この枠は、現役の大学生(4年生)や既卒者、そして民間企業で働いている社会人、さらには一度離職してブランクがある方など、多様な背景の人が受験できるのが特徴です。
受験年齢は「〜30歳」が多い
多くの自治体や国家公務員の一般枠(大卒程度)の受験年齢上限は「30歳未満」「30歳まで」が中心です。
例えば神奈川県の場合、22歳〜30歳までが受験資格。
「自分は大学卒業してからしばらく民間で働いていたから無理かな…」と諦める人もいますが、実際には25歳〜30歳の社会人も多数受験・合格しています。
【元県職員メモ】
私自身も社会人10年目で受験したので、最初は「やっぱり現役大学生がほとんどなのかな…」と不安でした。
でも実際の試験会場では、社会人経験者や既卒者も結構いて、年齢に関係なく本気で合格を目指している人が多いのが印象的でした。
一般枠は「学歴」「職歴」「ブランク」の壁が低い
基本的に「最終学歴」と「年齢」さえクリアしていれば、職歴やブランク、前職が何かは問われません。
実際、無職・アルバイト・転職希望の社会人も受験可能で、合格者のなかにもこうした背景を持つ方がいます。
筆記試験が最大の関門
一般枠では筆記試験(教養試験・専門試験)が重視されるため、現役大学生がやや有利に見えますが、社会人でも戦略次第で十分合格可能です。
合格者データでは約4人に1人が25〜30歳であり、社会人合格も現実的なラインです。
社会人枠(民間企業等職務経験者枠)の特徴
続いて、「社会人枠」について解説します。
近年、民間経験や多様なキャリアを持つ人材を積極的に登用したいという流れが強まっており、社会人経験者のみが受験できる“特別枠”を設ける自治体・官庁が増えています。
社会人枠は「30代・40代・50代」もチャンスあり
一般的に31歳〜59歳(場合によっては60歳未満まで)の幅広い年齢が受験対象です。
「社会人経験●年以上」「正社員経験●年以上」など、民間や官公庁等での職歴が求められます(詳細は自治体ごとに異なる)。
筆記試験が免除または大幅に軽減されるケースが多く、SPIや論文・面接重視型の選考が主流です。
【元県職員メモ】
かつての上司で、30代で県職員から県職員への転職に成功した方がいます。
「一般枠は年齢制限で無理だったけど、社会人枠のおかげでチャレンジできた」と語っていました。
社会人枠は、仕事で培った“社会人力”が重視されるため、「今のキャリアを活かせる」道としておすすめです。
社会人枠の合格者は年齢層も職業も多様
受験者・合格者ともに30代・40代・50代が中心ですが、実際に合格して新たな公務員生活をスタートしている人が多数います。
民間企業・他官公庁・NPO・自営業など、前職の幅も非常に広いのが特徴です。
受験枠の選び方と「併願」について
「自分はどちらの枠で受験できるのか」「両方受けられる?」と悩む方もいるかもしれません。
年齢・職歴・条件が合えば、「一般枠」と「社会人枠」の両方を受験できる自治体もあります。
ただし、一部自治体では同一年度内の併願が不可の場合もあるため、必ず公式サイト等で最新の募集要項を確認しましょう。
ここまでのまとめ
「一般枠」は現役学生〜30歳前後まで、既卒・社会人・ブランクありも可
「社会人枠」は30代・40代・50代の社会人経験者に開かれた道
年齢や職業を理由に諦める必要なし!自分に合った枠でチャレンジできる
最新データでみる公務員試験「受験生・合格者の年齢構成」【神奈川県庁データ例】
「自分と同じくらいの年齢で合格している人はいるのか?」
「年齢が高いとやっぱり不利なのか?」
——公務員試験を受けるうえで、こうした年齢への不安は誰もが感じるものです。
ここでは、神奈川県庁の公式データ「令和6年度人事委員会年報」をもとに、実際の年齢構成をわかりやすく解説します。
一般枠(大卒程度)受験生・合格者の年齢構成
まずは、21歳~30歳までが対象となる「一般枠」から見ていきます。
| 年齢 | 受験者数 | 合格者数(合格率) |
|---|---|---|
| 21歳 | 27 | 17(63%) |
| 22歳 | 668 | 216(32%) |
| 23歳 | 208 | 48(23%) |
| 24歳 | 140 | 30(21%) |
| 25歳 | 122 | 24(20%) |
| 26歳 | 70 | 17(24%) |
| 27歳 | 77 | 22(29%) |
| 28歳 | 49 | 7(14%) |
| 29歳 | 58 | 18(31%) |
| 30歳 | 52 | 13(25%) |
データからわかること
受験者の中心は22歳(大学生)ですが、25歳~30歳の社会人も全体の約3割を占めています。
合格者も、4人に1人は25歳~30歳と、社会人・既卒者の合格も十分現実的。
ただし、合格者の過半数(約57%)は21・22歳。つまり筆記対策にフルコミットできる“現役大学生”がやはり強いのは事実です。
【元県職員メモ】
私も最初「社会人は不利かも…」と感じていましたが、実際の合格者には20代後半の方も多く、勉強法や面接対策を工夫すれば十分チャンスがあると感じました。
「年齢が高いから…」と躊躇するのはもったいないです。
社会人受験生の“壁”と対策ポイント
現役大学生との最大の違いは、勉強時間の確保。
社会人の場合は仕事や家庭と両立しながらの勉強になるため、計画的な学習スケジュールや、スキマ時間の活用がカギとなります。独学が不安な人は通信講座や予備校の利用もおすすめ。
近年は「社会人向け公務員予備校」も増え、効率的なカリキュラムで短期合格を目指せる環境が整っています。
社会人枠(職務経験者採用試験)受験生・合格者の年齢構成
次に、31歳~59歳までを中心とする「社会人枠」について見ていきましょう。
| 年齢 | 受験者数 | 合格者数(合格率) |
|---|---|---|
| 31歳 | 40 | 8(20%) |
| 32歳 | 31 | 10(32%) |
| 33歳 | 33 | 5(15%) |
| 34歳 | 24 | 6(25%) |
| 35歳 | 35 | 7(20%) |
| 36歳以上 | 663 | 54(8%) |
データからわかること
受験生の約8割が36歳以上! そして、合格者の6割も36歳以上が占めています。
若い方(31~35歳)よりも、40代・50代の受験者・合格者が多いのが「社会人枠」の特徴です。
【元県職員メモ】
社会人枠で合格する方は、前職でのキャリアや人生経験をしっかり自己PRできる方が多い印象です。
実際、年齢や前職に関係なく「公務員になりたい!」という熱意が伝わる人ほど合格しやすい傾向があります。
社会人枠合格のために意識したいこと
筆記が免除or軽減される分、面接や論文での自己アピール力が重要!
「自分の社会人経験がどのように公務員の仕事で役立つか」を具体的に語れるかがカギです。
40代・50代からでも「今から公務員に転職」は十分可能!年齢をハンデではなく“強み”に変えましょう。
受験生・合格者の年齢に関するよくあるQ&A
Q1. 30代・40代で合格する人は実際どのくらいいる?
A. 一般枠は20代後半までが中心ですが、社会人枠なら40代・50代合格も現実的。近年は“多様な年代の合格者”が増えています。
Q2. 年齢制限ギリギリでも合格チャンスはある?
A. あります!実際、年齢制限ギリギリで受験し合格した例も複数あります。あきらめずにチャレンジを。
Q3. 受験会場で浮かないか心配…
A. 現役学生が多いのは事実ですが、社会人・既卒者も毎年一定数います。年齢や職業は気にしすぎる必要はありません。
公務員試験・受験生・合格者の「職業」別データと傾向分析
「どんな職業の人が合格しやすいの?」「社会人はどんな経歴が有利?」
――こんな疑問も、公務員試験を受ける方にとっては非常に大きな関心事です。
実は、公務員試験の受験者・合格者には多様な職業・バックグラウンドの方がいます。
ここでは、神奈川県庁の最新データをもとに、「一般枠」と「社会人枠」それぞれの職業別の受験・合格傾向を徹底分析します。
一般枠(大卒程度)受験生・合格者の職業構成
| 職業 | 受験者数 | 合格者数(合格率) |
|---|---|---|
| 県職員 | 6 | 2(33%) |
| 他官公庁 | 117 | 36(31%) |
| 民間企業 | 185 | 41(22%) |
| 学生 | 943 | 296(31%) |
| 無職 | 220 | 37(17%) |
データから見えるポイント
学生が最も多いものの、民間企業出身者や他官公庁からの転職希望者も一定数合格している。
無職(ブランク・転職活動中含む)でも合格者はいるが、合格率はやや低め(17%)。
現職公務員(県職員・他官公庁)もチャレンジしているが、3割程度しか合格できていない。
【元県職員メモ】
無職やフリーターから合格した人もいるので、「職歴に自信がない…」と悩む必要はありません。
社会人枠(職務経験者採用試験)受験生・合格者の職業構成
| 職業 | 受験者数 | 合格者数(合格率) |
|---|---|---|
| 県職員 | 0 | 0(0%) |
| 他官公庁 | 292 | 42(14%) |
| 民間企業 | 458 | 44(10%) |
| 学生 | 3 | 0(0%) |
| 無職 | 73 | 4(5%) |
社会人枠の合格傾向
圧倒的に民間企業出身者が多い(全体の半数以上)ですが、合格率は決して高くない(約10%)。
他官公庁(国家や市町村など)からの転職組も一定数合格しているが、現職が公務員であっても必ずしも合格はできない。
無職からのチャレンジはハードル高めだが、実際に合格した人もいる。
学生は基本的に対象外(受験要件を満たさない場合が多い)。
【元県職員メモ】
社会人枠の面接や論文では「前職の実績や経験をどう活かすか」が厳しく問われます。
民間・官公庁問わず「具体的に公務員で何がしたいか」を語れるかが大きなポイントになります。
職業別にみる「合格へのポイント」
学生・新卒:
筆記試験対策が勝負。しっかり勉強時間を確保できる点が強み。民間企業出身:
仕事で得た「実務経験」「リーダーシップ」「問題解決力」を自己PRでアピール。志望動機や転職理由も明確に伝えよう。無職・フリーター:
ブランク期間の過ごし方や「なぜ今公務員を目指すのか」を前向きに語れると好印象。「自己分析・目標設定力」が問われます。官公庁(他自治体)からの転職:
「なぜ転職したいのか」「どんな分野で貢献できるか」の説明が必要。前職の不満より“新しい挑戦”への前向きな志望理由が重要。
合格者のリアルな職業別体験談(筆者の知人)
事例①:無職(公務員浪人)から市職員(行政職)に合格したAさん(20代前半)
大学生で受験した公務員試験は全滅。
1年間無職で公務員試験勉強に専念し、見事翌年に合格を果たしました。
事例②:民間企業から市職員(土木職)へ転職したBさん(20代後半)
仕事が多忙で受験勉強が思うように進まず、4年間落ち続けたBさん。
ラストチャンスと決めて受験した5度目の挑戦で、ようやく合格でき、転職に成功しました。
事例③:県職員から県職員へ転職したCさん(20代後半)
他県の県職員になったが、結婚を機に地元の県に戻ろうと決意。
筆記試験はなんなくクリアし、面接試験もあっさりと合格。
事例④:国家公務員から県職員へ転職したDさん(30代)
家庭の事情で全国転勤ができなくったDさんは地元の県に戻ることを決意。
筆記試験はパスできましたが、面接試験で一度落ちてしまいましたが、翌年の2度目のチャレンジで合格し、転職しました。
よくある質問(Q&A)
Q. 無職やブランクが長くても受験できる?
A. 受験資格があれば問題なし!ただし、面接で「ブランク期間をどう過ごしていたか」は必ず問われるので、前向きに説明できるよう準備しましょう。
Q. 民間経験はどの程度アピール材料になる?
A. 非常に大きな武器になります!特に、コミュニケーション力やプロジェクトマネジメント力など「公務員の現場で生きる経験」は積極的にPRしましょう。
社会人が公務員試験に合格するためのポイントと勉強法
「仕事と勉強の両立がきつい」「面接で民間経験をどうアピールすればいい?」
――社会人から公務員を目指す方の多くが、このような悩みを抱えています。
しかし、社会人経験は“デメリット”ではなく“強み”にできる時代。
ここからは、公務員試験における社会人合格のリアルなコツや、筆記・面接対策のポイントを徹底解説します。
1. 筆記試験対策の戦略【社会人の“弱点”を克服する】
① スキマ時間活用&習慣化
社会人の場合、まとまった勉強時間を確保しづらいのが現実です。通勤や昼休み、家事の合間など“スキマ時間”の活用が合格のカギ。
1日2時間でも「朝30分+昼休み30分+夜1時間」など、“細切れ”を積み重ねてコツコツ進めることがポイントです。
② 自分に合った教材選び
「何を使うか迷う」という声も多いですが、社会人は“やり直し教材”よりも、要点がまとまった参考書・問題集・予想問題集を選ぶのがベター。
本屋で立ち読みして「これなら続けられそう」と思えるものを1冊決めて、繰り返し解くのが合格への最短ルートです。
③ 通信講座・予備校の活用
独学が不安な場合は通信講座・Web予備校も強い味方。最近は社会人向けに「最小限のインプット」「アウトプット重視」「添削・個別サポート」が充実しているコースが増えています。
筆者自身も最初は独学でしたが、苦手分野や論文添削はプロの添削やフィードバックが役立ちました。
④ 勉強計画の立て方・モチベ維持
「今日できることを毎日やる」「週ごとに目標を見える化する」など、スケジュール管理も合否を分ける重要ポイント。
モチベが切れそうなときは、SNSや勉強記録アプリで「見える化」「仲間づくり」もおすすめです。
2. 面接・論文で社会人経験を“武器”にするコツ
① 面接官が重視するポイント
社会人枠や既卒受験生に対しては、「民間・前職でどんな経験をし、何を学び、それをどう公務員として活かすのか」を必ず問われます。
年齢や転職回数よりも、「現職やこれまでの経験から何を吸収したか」「なぜ公務員を目指すのか」のロジックが重要です。
② 職歴・転職理由は“前向きに”
「安定だけが理由」「前職の愚痴」では評価されません。
「これまでの経験を公務員の現場でこう活かしたい」「地域や社会にこう貢献したい」という前向きなキャリアビジョンを明確にしましょう。
③ 論文・自己PRのコツ
論文やエントリーシートも、「自分の社会人経験×公務員志望動機」が伝わる具体例を。
例)「民間企業で培った顧客対応力を、住民サービスに活かしたい」「リーダー経験をチーム運営に生かせる」など。
3. 社会人合格のための“リアルな工夫”実例
実例①:夜型から朝型へ切り替えた社会人受験生(31歳)
「帰宅後は疲れて勉強が続かず、思い切って朝2時間分の勉強習慣をつくった。最初はきつかったけど、1ヶ月続けたら自然と勉強が日常に。結果、一次試験を突破!」
実例②:家族の協力を得たシングルマザー(35歳)
「子どもの送り迎えや家事は家族に分担してもらい、休日にカフェや図書館で集中勉強。合格後は“ママでも諦めなければ受かる”と多くの方に伝えたいです。」
実例③:転職歴3回・30代後半で社会人枠合格
「職歴の多さがネックかと不安だったが、面接で“さまざまな現場で学んだ柔軟性と適応力”をアピール。“あなたなら幅広い業務に対応できそうだね”と評価されて、念願の内定へ!」
4. 社会人受験生によくあるQ&A
Q. 残業が多い職場でも合格できる?
A. 可能です!短時間集中型の勉強法や、休日の“まとまった時間”を上手に使うのがコツ。1日1時間でも毎日継続が合格への近道。
Q. 筆記と面接、どちらを重視すべき?
A. 一般枠は筆記重視。社会人枠は面接・論文の比重が高めです。自分の受験枠の特徴に合わせて対策を最適化しましょう。
Q. ブランクや転職歴はマイナス?
A. そのままではなく「なぜ・どう活かすか」を前向きに語れば、むしろ多様性や経験値として高評価につながります。
5. 社会人受験生へ——筆者からのエール
社会人からのチャレンジは「不安」も多い反面、「社会人としての強み」を生かせる大きなチャンスでもあります。
私自身も「仕事を辞めて大丈夫か?」「家族や生活はどうなる?」と悩みましたが、計画的な準備と“絶対に諦めない気持ち”があれば、道は必ず開けます。
年齢や職歴で遠慮する必要なし!
今までの人生経験を公務員試験で“武器”に変えてください。
まとめ|公務員試験は年齢も職業も関係ない!“今のあなた”でチャレンジしよう
ここまで、公務員試験の合格者年齢・職業・社会人比率や、具体的な合格データ・体験談、社会人受験生向けの勉強法や面接のコツまで、徹底的に解説してきました。
年齢や職業、経歴に不安がある方こそ、「自分は無理かも…」と諦めないでほしい――これが、元県職員としての心からのメッセージです。
実際のデータを見ると、20代後半や30代・40代、50代の合格者も多く存在し、民間企業や官公庁、無職・フリーターなど、様々な職業・人生経験を持つ方が公務員の世界にチャレンジしています。
一般枠なら30歳まで、社会人枠なら40代・50代でも合格の可能性は十分。
「年齢が高いから」「職歴に自信がないから」という理由で挑戦を諦めてしまうのは本当にもったいないことです。
あなたの“人生経験”は、必ず公務員の現場で生きる
社会人や異業種からの転職者が増えている今、自治体や官公庁側も多様な人材を積極的に採用しています。
年齢や職歴は“ハンデ”ではなく“強み”です。今までの経験で身につけた「課題解決力」「コミュニケーション力」「視野の広さ」は、どの自治体・現場でも必ず活きます。
一歩踏み出す勇気が、未来を変えます。
あなた自身の「これまで」を活かして、新しい道にチャレンジしてみませんか?
さいごに筆者から
公務員試験は年齢や経歴が全てではありません。
あなたの“今”の想い・努力・人生経験をぜひ試験でぶつけてみてください。
きっと同じように悩みながらも挑戦し、夢を叶えた先輩があなたの周りにもいます。
一緒に一歩を踏み出しましょう!
本記事があなたの背中を押すきっかけになれば嬉しいです。
ご相談や質問もお気軽にどうぞ。
あなたの合格を心から応援しています。
ほかにも役立つ関連記事をたくさんまとめているので、よければご覧ください。
- 公務員に転職したい社会人におすすめの本を紹介(試験区分や日程等の情報収集はこれで完璧)
- 公務員試験の内容をわかりやすく解説した本を紹介!(職種・試験科目・年齢・日程など)
- 【元公務員が厳選】公務員通信講座おすすめ12選と選び方ガイド(2025年版)
- 【2025年最新版】社会人が公務員に転職するためのおすすめ通信講座4選を元県職員が徹底比較
- 忙しい社会人必見!公務員試験独学勉強法【教養・面接対策完全ガイド】