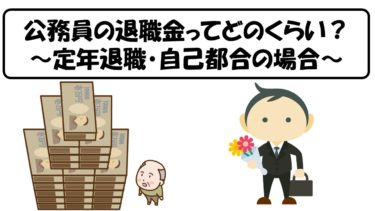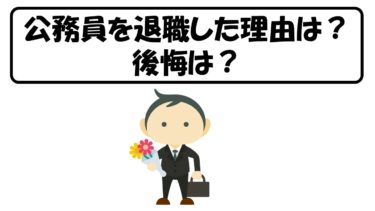公務員を辞めたいと考えている方は意外と多いですが、実際に辞めるとなると多くの不安や疑問が頭をよぎるものです。
特に、公務員ならではの退職手続きや引き止めへの対処法、退職後の生活設計など、考えなければならないことが山積みです。
私自身も、県職員として9年間働いた後に退職を決断した経験があります。
退職を考え始めた頃は、「本当に辞めてもいいのか?」という葛藤や、「退職後の生活はどうなるのか?」という漠然とした不安に苛まれました。
さらに、周囲に退職の相談をすることも難しく、誰にも打ち明けられずに一人で悩む日々が続きました。
特に、公務員は安定した職業というイメージが強く、辞めること自体に対する世間の目も厳しいものがあります。
そのため、家族や同僚に相談することすら気が引けてしまい、孤立感を感じることもありました。
しかし、最終的に自分の気持ちに正直になり、退職を決断しました。
そして、その後は新たなキャリアに挑戦し、自由な働き方や自己成長を追求する道を選びました。
この記事では、私の実体験をもとに、公務員が退職する際の具体的な手続きや心構え、準備すべきことを時系列で詳しくご紹介します。
これから公務員を辞めたいと考えている方がスムーズに退職できるよう、必要な準備や注意点も合わせて解説していきます。
少しでも参考になれば幸いです。それでは、退職までの道のりを一緒に見ていきましょう。
- 約2ヶ月半前に係長に相談
- 管理職や人事課との面談
- 1ヶ月前から退職事務手続きスタート、退職届は退職日2週間前までに提出
- 退職日に辞令交付があり、退職
【この記事を書いた人↓】

公務員が退職を決意するまでの流れ
公務員を辞める決断は非常に大きなものです。
安定した職業であり、社会的な信用も高い公務員という立場から離れることは、多くの人にとって人生の大きな転機となります。
そのため、退職を決意するには多くの葛藤や不安が伴います。
退職を決意した理由
私が公務員を辞めることを決断した背景には、以下のような要因がありました。
ワークライフバランスの欠如
公務員は安定している反面、仕事量が多く、残業も避けられません。
特に繁忙期には深夜まで働くこともあり、家庭やプライベートの時間が圧迫されがちです。
例えば、年度末や予算編成の時期には、深夜残業が続き、プライベートな時間がほとんど取れない日々が続くこともありました。
また、休日でも突発的な業務や対応が求められることがあり、完全なオフが取れないストレスが積み重なっていきました。
メンタルヘルスの悪化
長時間労働や責任の重さから精神的な疲労が蓄積しやすく、うつ状態や燃え尽き症候群に陥る公務員も少なくありません。
私自身も、度重なる業務のプレッシャーなど、心身に大きな負担を感じるようになり、次第に仕事への意欲が低下していきました。
パワハラ・アルハラ
全ての上司ではないですが、一部の上司からパワハラやアルハラを受けたことも退職した理由の一因でした。
例:書類を具体的な改善点を挙げずに何度も書き直しさせる、無理難題を押し付けてくる、ゴミ箱を蹴る、残業して滞っている業務を済ましたいのに飲み会に誘ってきて断ると不機嫌になるなど
新たな挑戦への意欲
公務員としてのキャリアに限界を感じ、新たな分野で自分の力を試してみたいという気持ちが芽生えました。
特に、「自由な働き方」、「自己成長の機会が欲しい」、「人の役に立ちたい」と感じるようになり、起業やフリーランスといった選択肢にも興味を持ち始めました。
長時間労働による心身の負担
体力的にも精神的にも限界を迎えることがあり、健康への不安が増していきました。
例えば、慢性的な睡眠不足やストレスからくる体調不良が続いていました。
人間関係のストレスや組織文化への違和感
公務員は年功序列や上下関係が厳しい職場が多く、人間関係のストレスも大きな要因です。
例えば、上司や同僚との意見の相違や組織内の派閥争いに巻き込まれることがあり、精神的な負担が増していきました。
引き止めへの対処法
退職を決意しても、実際に行動に移す際には「引き止め」という大きな壁が待っています。
特に、長年勤めた組織からの引き止めは強力で、心理的なプレッシャーも大きいものです。
退職理由を明確に伝える
上司や同僚に退職の意志を伝える際は、なぜ辞めたいのかを明確に伝えることが重要です。
具体的な理由を準備しておくと、引き止めに対して毅然とした態度で臨むことができます。
事前に退職理由を整理し、強い意志を持つ
引き止められることを想定して、事前に退職理由を紙に書き出し、自分の意思を再確認しておくと効果的です。
例えば、「家族との時間を大切にしたい」「新たな挑戦に踏み出したい」といった具体的な目標や理由を明確にしておくと、迷いが少なくなります。
引き止めに負けずに自分の意思を貫く
どんなに情に訴えられたり、待遇改善を提案されたとしても、自分の決断を貫くことが大切です。
「今が退職のタイミングだ」と強く信じる気持ちが重要です。
面談での質問に備えて、退職後の計画を明確にする
退職後のキャリアや生活設計についても質問されることが多いため、具体的な計画を準備しておくと説得力が増します。
例えば、「フリーランスとして独立する」「異業種に転職する」といった具体的なビジョンを持つことが大切です。
同僚や上司との関係を大切にしつつ、自分の意志を貫く
退職後も人間関係は続くことがあるため、感謝の気持ちを忘れずに、円満に退職することを心がけましょう。
最後の職場での経験が次のステップに繋がることもあります。
【参考記事】
【公務員・会社員を辞めたい人必見】強い引き止めにあったら「退職代行」の検討を!
退職前に準備すべきこと
退職を決意したとしても、いきなり辞表を提出するわけにはいきません。
公務員には特有の手続きがあり、退職後の生活設計も考慮する必要があります。
ここでは、退職に向けて事前に準備しておくべきことについて詳しく解説します。
経済的な備え
退職後の生活は経済的な不安が大きなハードルとなります。
公務員は基本的に失業保険の対象外であり、収入が途絶える可能性があります。
そのため、以下のような経済的な備えが重要です。
退職後の収入源の確保
- フリーランスや副業の開始
- 転職先の確保や準備
- 投資や資産運用での安定収入の確保
生活費の見積もりと貯金計画
退職後の生活費を見積もり、少なくとも半年から1年分の生活費を貯金しておくことが理想です。
具体的には、家賃、光熱費、食費、交通費、税金などの固定費と変動費をリストアップし、月々の支出を把握しましょう。
退職手当や退職金の確認
公務員には退職手当が支給されますが、その額は勤務年数や役職に応じて異なります。
退職前に人事課に問い合わせ、具体的な支給額や支給時期を確認しておくことが重要です。
退職金が思ったより少ない場合、貯金や収入源の確保がさらに重要になります。
私は9年勤めて退職金は約100万円でした。
退職後の社会保障の準備
国民年金や国民健康保険への加入手続きも必要です。
これらの手続きには期限があるため、早めに準備しておくことが大切です。
精神的な準備
退職は経済的な問題だけでなく、精神的な負担も伴います。
特に長年働いてきた職場を離れることは大きな決断です。
家族や友人への相談
退職の決断は自分一人で背負うものではありません。
家族や信頼できる友人に相談し、精神的な支えを得ることが大切です。
特に、配偶者や親との話し合いは重要です。
彼らの理解と協力があれば、退職後の不安も軽減されます。
退職後の生活イメージの明確化
退職後にどのような生活を送りたいのか、具体的なビジョンを持つことがモチベーションにつながります。
例えば、「自由な時間を増やして趣味に集中する」「新たなスキルを身につける」「起業に挑戦する」といった目標を設定しましょう。
実務的な準備
書類整理と引き継ぎ準備
退職前には、業務の引き継ぎや必要な書類の整理が不可欠です。
例えば、業務マニュアルの作成や後任者への引継書の準備が求められます。
退職理由の明確化と伝え方の準備
退職面談での質問に備え、退職理由を明確に整理しておくことが大切です。
具体的なエピソードやキャリアの展望を準備しておくと、説得力が増します。
人脈の整理と関係の維持
退職後も役立つ人脈を維持するため、上司や同僚への感謝の気持ちを忘れずに。
最後の挨拶や感謝のメールを準備しておくと、良好な関係が続くことが多いです。
退職に関する手続きの確認
退職届の提出期限や必要な手続きを事前に確認しておきましょう。
退職に伴う各種手続きは煩雑なため、スケジュールを立てて計画的に進めることが大切です。
これらの準備が整っていれば、退職後もスムーズなスタートが切れるはずです。
次のステップでは、実際の退職手続きについて詳しく見ていきましょう。
退職手続きの流れ(時系列)
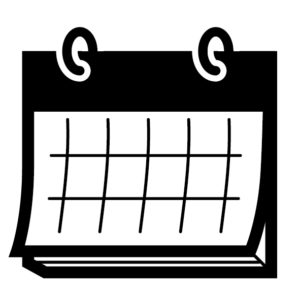
退職の意思を固めたら、実際に手続きを進める必要があります。
公務員の退職手続きは一般の民間企業とは異なり、独自のルールや段取りが求められるため、計画的に進めることが重要です。
ここでは、私自身が経験した具体的な退職手続きを時系列で詳しく解説します。
退職2ヶ月半前:初動
直属の係長に相談
退職の意思を最初に伝える相手は直属の係長がベストです。
別室での面談が一般的で、ここでのやり取りがその後の退職プロセスに大きく影響します。
私の場合、係長からは「本当に辞めるのか?」「後悔しないか?」といった質問を受け、引き止めの言葉もありました。
ただ、ここで曖昧な態度を取ってしまうと、退職の意思が揺らいでしまう可能性があるため、強い意志を持って臨むことが大切です。
課長との面談
係長への報告後、課長との面談が設定されることが多いです。
私の場合は課長、係長、私の3者面談でした。
この面談では、退職の理由や今後のキャリアについて詳しく尋ねられることが一般的です。
私の場合、課長からは「辞めた後の仕事や生活はどうするのか?」「家族の理解は得られているのか?」といった、かなり踏み込んだ質問がありました。
時には、感情的なやり取りになることもありますが、冷静に対応し、自分の意思を貫くことが重要です。
課長から質問攻めで、まるで面接試験のような感じですごく苦労しました。
「辞めたあとの進路がしっかり固まっていなければ辞めるのを許すわけにはいかない」とまで言われました。
所属長・人事課との調整
課長との面談が終わると、次は所属長や人事課との調整に移ります。
この段階では、退職日や引き継ぎの具体的なスケジュールが話し合われることが多いです。
私の場合、課長が所属長や人事課に直接説明してくれたおかげで、このステップは比較的スムーズに進みました。
最終退職申し出の待機
これで内部的には準備が整った(根回しが出来た)ので、あとは私の心の準備ができしだい、再び退職を申し出るように言われました。
退職1ヶ月前:本格的な準備開始
そしていよいよ退職日を6月30日に決め、退職1ヶ月前に係長に再度退職の申し出をしました。
これで正式に退職に関する事務手続きが始まりました。
手続き自体は、非常に簡単なもので、私は以下のことをしました。
- 「退職願」の様式を係長から受け取り、自筆で記入
- 退職手当(退職金)に関する申出書等の記入
- 団体保険の給与天引き停止の依頼
- 共済組合関係の事務処理
- 互助会関係の事務処理
- 職員宿舎の明渡しの準備
業務マニュアルの作成や進行中のプロジェクトの状況整理など、引き継ぎがスムーズに進むよう準備を進めましょう。
私は体調を崩していて、休職中での退職だったので、引き継ぎは係長にお願いしました。
退職2週間前:最終調整
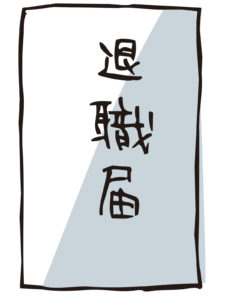
退職2週間前には以下のことを行いました。
- 退職願の提出
- 上司や同僚や同期へのあいさつ
- 職員宿舎明渡し(私は早めに宿舎から引っ越しました)
- 確定拠出年金の加入者種類変更手続き
退職届の提出期限には特段決まりはありませんが、「できれば退職日の2週間前までに提出してほしい」と言われました。
【参考記事↓】
【公務員辞めたい人必見】退職願は「いつまで」に提出すべきか(県職員経験談)
退職日:最後の日
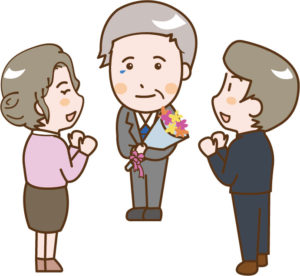
退職日は以下のことを行いました。
- 辞令交付
- 保険証の返納
- 県職員バッチの返納
辞令交付で「人事通知書」をもらいます。
民間では離職証明書がもらえますが、公務員はこの人事通知書が離職証明書の代わりになります。
ちなみに、私は体調を崩し休職していたため、退職日は出勤せず、自宅に課長・係長が来て、辞令交付が行われました。
最後の出勤日には、送別会やお礼の挨拶が行われることもあります。
退職後に必要な手続き
退職が完了しても、すぐに気を緩めてはいけません。
退職後にはさまざまな手続きが待っています。
特に、公務員から民間企業やフリーランスへの転職、またはしばらく休養する場合、それぞれの状況に応じて必要な手続きが異なります。
ここでは、退職後に必要な主な手続きについて詳しく解説します。
国民年金への加入
- 手続き期限:退職日の翌日から14日以内
- 手続き場所:市区町村の役所または年金事務所
- 必要な書類:年金手帳、本人確認書類、退職証明書(人事通知書)
- ポイント:公務員退職後は厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。任意で付加年金への加入も可能です。
国民健康保険への加入
- 手続き期限:退職日の翌日から14日以内
- 手続き場所:市区町村の役所
- 必要な書類:本人確認書類、退職証明書(人事通知書)
- ポイント:共済組合の健康保険を脱退するため、新たに国民健康保険への加入が必要です。また、扶養家族がいる場合は、その家族分の手続きも忘れずに。※条件を満たしていればそのまま共済組合の健康保険に入り続ける「任意継続」を選ぶこともできます。
退職手当の受け取り
- 支給時期:退職月の翌月末頃が一般的
- 手続き場所:所属していた自治体の人事課または給与担当部署
- 必要な書類:退職願の写し、退職証明書
- ポイント:退職手当は勤務年数や役職に応じて支給される額が異なります。事前に具体的な金額や支給時期を確認しておきましょう。
住民税の支払い
- 支払い方法:一括払いまたは分割払い
- ポイント:退職後も住民税の支払い義務は続くため、退職前に納付方法を確認しておきましょう。
失業保険(基本手当)の確認
- 対象者:一般的に公務員は失業保険の対象外
- ポイント:ただし、特定の条件を満たす場合や非常勤職員であれば、失業給付の対象になることもあります。
共済組合の任意継続
- 手続き期限:退職日の翌日から20日以内
- 手続き場所:共済組合の事務局
- ポイント:退職後も共済組合の健康保険に継続して加入することが可能ですが、全額自己負担となります。
確定拠出年金(DC)の移管手続き
- 手続き期限:特になし(早めの手続きを推奨)
- 手続き場所:各金融機関または証券会社
- ポイント:企業型DCから個人型iDeCoへの移管が必要な場合があります。放置すると手数料がかかることがあるため、早めの対応が望ましいです。
退職後の所得税や年末調整
- ポイント:退職後に収入がある場合、年末調整や確定申告が必要になることがあります。税務署への確認を忘れずに。
その他の手続き
- 住所変更(引越しの場合)
- 銀行口座の変更(退職金の受け取り口座)
- 携帯電話やインターネットの契約変更(勤務先の割引サービスを利用している場合)
- 保険や積立金の見直し(退職後の収入に合わせて調整)
税金について
- 健康保険(任意継続) 約23,000円/月
- 市県民税(住民税) 約14,000円/月
- 国民年金 約16,000円/月
会社員が退職をした場合、次の職を探すまでの間にお世話になるのが「雇用保険」(別名:失業保険)です。 この雇用保険をもらいながら、ハローワークなどに通うなどして、次の職を探すのが一般的です。 […]
猫さん公務員の退職金は多いって聞くけど実際どのくらいもらってるの?伯爵さんズバリ定年退職の場合、平均で2,000万円以上もらえます!話題になった老後2,000万円問題は公務員には心配ないね。た[…]
よくある質問と対策
退職を決意する際や手続き中、さらには退職後にもさまざまな疑問や不安が生じることがあります。
ここでは、公務員退職に関するよくある質問とその対策について解説します。
Q1. 引き止めが怖いのですが、どう対処すればいいですか?
対策:引き止めは避けられないものと考え、事前にしっかりと準備しておきましょう。
退職理由を明確に整理し、強い意志を持つことが重要です。
例えば、「家族との時間を大切にしたい」「新たな挑戦に踏み出したい」といった具体的な理由を準備しておくと効果的です。
また、感情的にならず冷静に対応することも大切です。
必要に応じて、退職理由を簡潔にまとめたメモやプレゼン資料を用意するのも一つの手です。
Q2. 退職後の収入が不安です。どうすればいいですか?
対策:退職後の収入が不安な場合、事前に収入源を確保しておくことが重要です。
副業やフリーランス、転職など、複数の収入源を確保しておくと安心です。
また、投資や資産運用も選択肢の一つです。
退職金や貯金をどのように運用するかを計画しておくことも大切です。
Q3. 家族の反対が心配です。どう説得すればいいですか?
対策:家族の理解は退職において非常に重要です。
退職後の具体的な計画や見通しを示し、家族が安心できるように説明しましょう。
例えば、収入源の確保や新たなキャリアプランについて具体的に話すと説得力が増します。
また、家族の不安や心配に耳を傾け、真摯に向き合う姿勢が大切です。
Q4. 退職後の社会保障や年金が不安です。
対策:退職後も年金や健康保険の加入が必要です。
国民年金や国民健康保険への切り替え手続きを忘れずに行いましょう。
共済組合の任意継続も選択肢の一つですが、費用がかかるため事前にシミュレーションしておくと良いでしょう。
Q5. 退職後に後悔することはありませんか?
対策:退職後に後悔しないためには、退職理由や今後の目標を明確にしておくことが重要です。
「なぜ辞めるのか」「退職後に何をしたいのか」をしっかりと考え抜くことが大切です。
また、退職を決意した理由や動機を定期的に見直し、自分の意思を再確認することも有効です。
【参考記事】
【公務員】就職・転職する前に絶対に知っておきたい元県職員が後悔したこと15選(デメリット)
Q6. 退職後に人間関係が途切れてしまうのが心配です。
対策:退職後も良好な人間関係を維持するためには、感謝の気持ちを忘れないことが大切です。
最後の出勤日にお礼の手紙やメールを送る、送別会でしっかりと感謝を伝えるなど、小さな心遣いが大切です。
また、SNSを活用して、退職後も積極的に連絡を取り続けることも有効です。
Q7. 退職後の孤立が怖いです。
対策:新しいコミュニティに参加することが孤立を防ぐ鍵です。
同じ境遇の仲間とつながるために、オンラインサロンやコミュニティに参加することも検討しましょう。
趣味や新しい挑戦を通じて、ポジティブな人間関係を築くことも大切です。
これらの対策を踏まえ、自信を持って退職に向けた準備を進めましょう。次は、この記事のまとめに移ります。
まとめ

公務員を辞めることは大きな決断であり、多くの不安や疑問が伴います。
しかし、適切な準備と計画があれば、その一歩は必ず新たな可能性への扉を開くものです。
この記事では、私自身の経験をもとに、公務員が退職する際に必要な手続きや心構え、引き止めへの対処法、退職後に必要な手続きについて詳しく解説してきました。
退職の成功に向けてのポイント
明確な退職理由を持つ
なぜ辞めるのか、その理由を明確にすることが退職成功への第一歩です。
家族や同僚への説明もスムーズになり、引き止めにも冷静に対応できます。
経済的な備えを整える
退職後の収入源を確保し、生活費の見積もりや貯金計画を立てることが重要です。
退職手当や退職金、年金なども事前に確認しておきましょう。
精神的な準備も大切
退職は大きな人生の転機です。家族や友人に相談し、精神的な支えを得ることが大切です。
手続きを計画的に進める
退職願の提出や各種手続きは早めに準備し、期限を守ることが重要です。
退職後の生活を楽しむ準備も
新たな挑戦や趣味、コミュニティへの参加を通じて、退職後の生活をより充実させましょう。
最後に
退職は人生の大きな転機ですが、その先には新たなチャンスと成長の機会が広がっています。
自分の人生をより充実させるための一歩として、前向きに退職を考えましょう。
もしこの記事が少しでも皆さんの退職に向けた不安を軽減し、次のステップへの勇気を与えることができたなら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
少しでも辞めたいと悩まれている方の参考になれば幸いです。
公務員は離職率が非常に低く、民間の離職率15%に対し、地方公務員は約1.6%と10分の1程度になっています。※データ元↓ 民間離職率:厚生労働省令和4年雇用動向調査結果 地方公務員離職率:総務省令和4年度地方公務員の[…]
公務員のなかでも、うつ病などのメンタル疾患で休職している人や休職・復職を繰り返している人が結構います。 そのなかには、過労というよりは、人間関係が原因でうまくいかなくなってしまう人が多いかと思います。&nb[…]
ねこさん公務員を退職して転職活動した元公務員の体験談が聞きたい!伯爵さん私は公務員を退職して半年後くらいから転職活動をしたので、今回はその体験談を紹介するね!本記事では、30代[…]
退職する理由は人それぞれです。
ただ、退職理由・状況によっては、上司への申し出に難があって困る場合(パワハラ、引き止めなど)もあるでしょう。
退職する・しないは労働者の自由、権利です。
退職したいのにできず、体調を崩してしまったり、転職する機会を失ったりしてしまうことだけは避けましょう。
退職で困っている場合は、下記の「退職代行」を検討してみるのも一つの手です。
どの退職代行を利用すればいいか迷っている人は、
- 公務員の退職代行実績あり
- 退職成功率100%
- 弁護士事務所が代行するから安心
の「弁護士法人ガイアの退職代行サービス」がおすすなので検討してみてください。