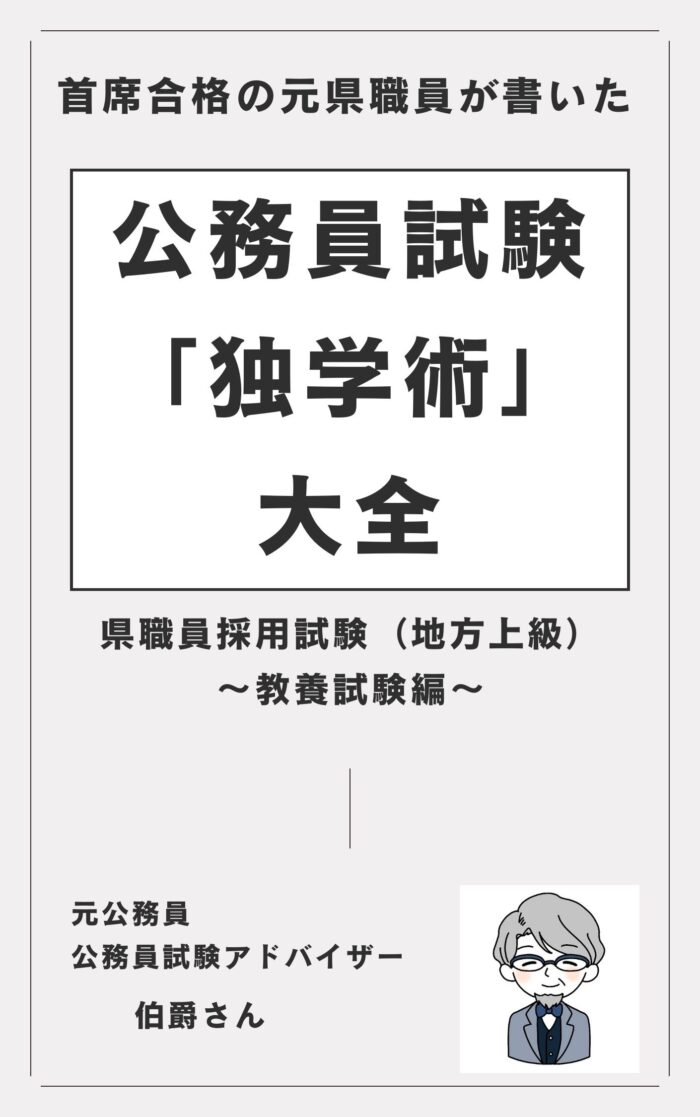今回の記事では、私が実践した文章理解の効率的な勉強法(独学)について解説します。
(私はこの勉強法でどの公務員試験の文章理解もほぼ満点でした。教養試験合計では7~8割得点)
この記事は、
- 独学で文章理解を勉強している受験生
- 効率的な勉強方法を探している受験生
などに役立つ記事となっています。
この記事を書いた人

文章理解は絶対に対策すべき
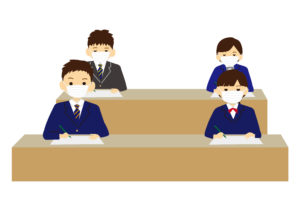
まずは文章理解の重要性について解説します。
文章理解は出題数が多い=失敗したら致命的
文章理解は出題数が多い、つまり配点が高い科目です。
そのため、試験当日に文章理解でつまづくと不合格になる可能性が高いです。
【配点例】
2024年度 国家公務員採用試験(一般職・大卒程度) 文章理解11題/総問題数40題
2023年度 静岡県職員採用試験(大卒程度) 文章理解8題/総問題数40題
2023年度 長野県職員採用試験(大卒程度) 文章理解8題/総問題数40題
試験本番、時間をかけてでも9割以上は得点したい
公務員試験は試験時間が短いのが特徴です。
そのなかで、文章理解は時間をかけて丁寧に解けば答えが分かる問題が多いです。
そのため、できる限り文章理解には時間を割いて問題を解くようにしましょう。
なお、時間配分については以下の記事が参考になります。
【参考記事↓】
【公務員教養試験】1問あたりにかける時間&解く順番のおすすめ!
文章理解で満点を取るための勉強法5選
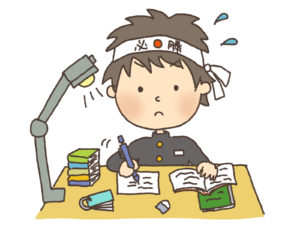
それでは、下記の私が実践した文章理解の効率的な勉強法5つをご紹介します。
- 1日1問新しい問題を解き続ける
- 必ずタイム計測を行う
- 問題を解くときはまず選択肢に目を軽く通してから解き始める
- 問題文にマークをつけていく
- 古典や英単語はそこまで対策に時間をかけない
1日1問新しい問題を解き続ける
私は試験本番まで1日1問必ず新しい問題を解き続けていました。(英語1問、国語1問)
これは問題を解く「勘」を鈍らせないためで非常に大切なことです。
また、毎日新しい問題を解くことで解くスピードも向上します。
必ずタイム計測を行う
文章理解の問題を解く際は、毎回タイムを計測すると良いです。
実践さながらの目標タイム内で解くことを意識して日々問題を解いていると、解くスピードが格段に向上します。
また、普段から時間を意識することで時間配分が体得でき、試験本番も慌てることなく問題を解き進めることができます。
問題を解くときはまず選択肢に目を軽く通してから解き始める
文章理解を素早く解くコツとして、いきなり問題文を読むのではなく、まずは選択肢をさらっと読むことをおすすめします。
あらかじめ選択肢を読むことで、
「こんなジャンルの内容なんだな」
「キーワードはこの単語だな」
と目星をつけたうえで、問題に取り組むことができるので非常に効率的です。
問題文にマークをつけていく
完全に私の自己流になりますが、問題中のキーワードによくマークを付けていました。
「重要なキーワードに丸をつける」
「大事なそうな部分に下線を引く」
などしていました。
これをすることで視覚的にワードを取らえることができ、問題文を何度も読み返すことがなくなって速く解くことができます。
古典や英単語はそこまで時間をかけない
古典や英単語の勉強については、費用対効果の面からあまり得点向上が期待できないので、私はほとんど対策しませんでした。
英単語は一応英単語帳を買いましたが、あまり使うことなく本番を迎えました。
英単語は解いた問題中の英単語の意味を再確認しておく程度で良いと思います。
まとめ

文章理解は出題数が多いわりに、対策が後手に回りがちな科目です。
毎日解いて勘を鈍らせないようにすることが試験本番で失敗しない唯一の方法です。
ポイントは、必ず新しい問題を解くこと。
参考書を一回やり通したら新しい問題集を買ってください。
文章理解、ぜひ満点目指して日頃から継続して努力しましょう。
ここまでお読みいただき本当にありがとうございます☆