国家公務員(総合職・一般職)の試験データ
都道府県や政令市、特別区の合格率
難易度が高い/低い自治体ランキング
合格者の出身大学やボーダーライン
おすすめの勉強法・予備校比較
など、実際の数字をもとに「どのくらい受かりやすいのか」が分かる内容になっています。
公務員試験の合格率は平均約35%!3人に1人が合格できる試験
まず最初に押さえておきたいのは、全体の合格率です。
国家公務員(総合職):29%
国家公務員(一般職):44%(行政のみの場合)
都道府県職員:39%
特別区:44%(実質採用率は19%)
政令指定都市:31%
これらを平均すると、公務員試験全体の合格率は「およそ35%」。
つまり、3人に1人が合格できる計算です。
率直に公務員試験はかなり合格しやすい試験とみることができます。
例えば、資格試験の合格率をみると、
司法書士:約5%(令和6年度司法書士試験 受験者13,960人、合格者737人)
(引用:令和6年度司法書士試験の最終結果について)
税理士:約17%(令和6年度税理士試験 受験者34,757人、合格者5,762人)
(引用:令和6年度税理士試験結果)
行政書士:約13%(令和6年度行政書士試験 受験者47,785人、合格者6,165人)
(引用:令和6年度行政書士試験実施結果の概要)
となっています。
- 受験生のレベルが一緒ではない
- そもそも受験資格があり受験者のレベルが高い
など、一律に比較はできませんが、「行政書士や税理士になるよりは簡単」って感じで捉えておくといいですね。
国家公務員試験の難易度【総合職・一般職】
国家総合職の合格率と特徴
国家総合職は、いわゆるエリート公務員。
官庁訪問を経て採用されるため、筆記合格しても最終的に採用されないことも多いのが特徴です。
| 試験区分 | 合格率 |
|---|---|
| 政治・経済 | 15% |
| 法律 | 5% |
| 経済 | 16% |
| 人間科学 | 22% |
| デジタル | 35% |
| 工学 | 40% |
| 数理科学・物理・地球科学 | 26% |
| 化学・生物・薬学 | 17% |
| 農業科学・水産 | 53% |
| 農業農村工学 | 54% |
| 森林・自然環境 | 31% |
(出典:国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)実施状況2024年度)
総合職では、
一番高い合格率 : 農業農村工学の54%
一番低い合格率 : 法律の5%
平均合格率 : 29%
という結果でした。
特に法律系は競争が激しく、5%台という非常に低い合格率です。
また、実際に採用された人数は最終合格者の40%程度にとどまり、「最終合格=内定」ではない点に注意が必要です。
※【最終合格者と採用者】
2023年度総合職試験最終合格者は、
総合職(院卒者試験):667人
総合職(大卒程度試験):1360人
総合職(大卒程度・教養区分):423人
合計2,137人です。
そのうち、官庁訪問を経て、最終的に採用になった受験生は、
総合職(院卒者試験):269人
総合職(大卒程度試験):506人
です(過年度試験の合格者で採用された者を含む)。
国家一般職の合格率と特徴
| 試験区分 | 合格率 |
|---|---|
| 行政・北海道 | 69% |
| 行政・東北 | 50% |
| 行政・関東甲信越 | 35% |
| 行政・東海北陸 | 41% |
| 行政・近畿 | 37% |
| 行政・中国 | 48% |
| 行政・四国 | 42% |
| 行政・九州 | 35% |
| 行政・沖縄 | 37% |
| デジタル・電気・電子 | 64% |
| 機械 | 63% |
| 土木 | 58% |
| 建築 | 63% |
| 物理 | 82% |
| 化学 | 64% |
| 農学 | 62% |
| 農業農村工学 | 51% |
| 林学 | 69% |
(出典:国家公務員採用一般職試験(大卒程度)実施状況2024年度)
一般職では、
一番高い合格率 : 物理の82%
一番低い合格率 : 行政・関東甲信越と九州の35%
平均合格率 : 54%(行政のみだと44%)
という結果でした。
技術職系は比較的合格率が高めですが、行政系は倍率が高く、人気エリアでは35%前後です。
都道府県職員試験の合格率
自治体ごとに大きな差があるのが地方上級試験(都道府県職員)です。
| 自治体 | 合格率 |
|---|---|
| 北海道 | 49% |
| 青森県 | 52% |
| 岩手県 | 46% |
| 宮城県 | 28% |
| 秋田県 | 41% |
| 山形県 | 42% |
| 福島県 | 64% |
| 茨城県 | 34% |
| 栃木県 | 33% |
| 群馬県 | 30% |
| 埼玉県 | 42% |
| 千葉県 | 39% |
| 東京都 | 62% |
| 神奈川県 | 36% |
| 新潟県 | 26% |
| 富山県 | 42% |
| 石川県 | 53% |
| 福井県 | 44% |
| 山梨県 | 39% |
| 長野県 | 26% |
| 岐阜県 | 37% |
| 静岡県 | 53% |
| 愛知県 | 27% |
| 三重県 | 42% |
| 滋賀県 | 37% |
| 京都府 | 57% |
| 大阪府 | 11% |
| 兵庫県 | 24% |
| 奈良県 | 15% |
| 和歌山県 | 62% |
| 鳥取県 | 32% |
| 島根県 | 65% |
| 岡山県 | 37% |
| 広島県 | 39% |
| 山口県 | 57% |
| 徳島県 | 30% |
| 香川県 | 33% |
| 愛媛県 | 35% |
| 高知県 | 42% |
| 福岡県 | 15% |
| 佐賀県 | 12% |
| 長崎県 | 51% |
| 熊本県 | 39% |
| 大分県 | 21% |
| 宮崎県 | 53% |
| 鹿児島県 | 35% |
| 沖縄県 | 24% |
都道府県の結果は以下のとおりとなりました。
一番高い合格率(難易度が低い):島根県65%
一番低い合格率(難易度が高い):大阪府11%
平均合格率:39%
【ポイント】
- 合格率には都道府県で格差があり、一番合格率が高い島根県(合格率65%)だと3人に2人が合格できますが、一番合格率が低い大阪府(合格率11%)では10人に1人しか合格できません。
- どこの都道府県でもいいのでとにかく公務員になりたい人は合格率が高い都道府県を選ぶべきだと思います。(どこに入っても仕事内容や年収などはそこまで大差ないです)
- 都市部の合格率が低く、地方の県の合格率が低いというわけではない。自治体ごとの募集人数の差だと考えれれる。
特別区(東京都23区)の合格率と採用率
1次受験者:6,868人
最終合格者:3,035人(合格率44%)
採用予定者:約1,300人(実質採用率19%)
23区全体での競争倍率は高めです。(引用:特別区令和6年度Ⅰ類採用試験(春試験)実施状況)
筆記試験を突破しても、各区の面接に進むため「二段階選抜」で絞られます。
政令指定都市の合格率
政令市も自治体によって合格率にバラつきがあります。
| 自治体 | 合格率 |
|---|---|
| 大阪市 | 32% |
| 名古屋市 | 37% |
| 京都市 | 29% |
| 横浜市 | 22% |
| 神戸市 | 16% |
| 北九州市 | 26% |
| 札幌市 | 29% |
| 川崎市 | 44% |
| 福岡市 | 17% |
| 広島市 | 43% |
| 仙台市 | 20% |
| 千葉市 | 31% |
| さいたま市 | 32% |
| 静岡市 | 36% |
| 堺市 | 22% |
| 新潟市 | 33% |
| 浜松市 | 39% |
| 岡山市 | 37% |
| 相模原市 | 26% |
| 熊本市 | 45% |
政令指定都市では、
一番高い合格率 : 熊本市の45%
一番低い合格率 : 神戸市の16%
平均合格率 : 31%
という結果でした。
政令市は人口が多く、志望者が集中する傾向にあるため、筆記突破後の面接倍率も高めです。
合格率が高い&低い自治体ランキング【2024年度版】
ここでは、2024年度の最新データをもとに、都道府県および政令指定都市を含めた「合格率の高い自治体」と「合格率の低い自治体」のランキングを紹介します。
「どこを受ければ受かりやすいのか?」
「競争率が高くなる自治体は?」
を知るうえで非常に参考になります。
難易度が高い(合格率が低い)自治体ランキング
| 順位 | 自治体 | 合格率 |
|---|---|---|
| 1位 | 大阪府 | 11% |
| 2位 | 佐賀県 | 12% |
| 3位 | 奈良県 | 15% |
| 4位 | 福岡県 | 15% |
| 5位 | 神戸市 | 16% |
これらの自治体では、10人受けて1〜2人しか合格できないという狭き門。
特に大阪府は募集人数に対して志願者が非常に多い傾向があり、筆記試験の時点から倍率が高くなります。
また、佐賀県や奈良県のような地方自治体でも合格率が低い理由としては、「試験区分が少ない」「募集人数が限られている」ことが挙げられます。
難易度が低い(合格率が高い)自治体ランキング
| 順位 | 自治体 | 合格率 |
|---|---|---|
| 1位 | 島根県 | 65% |
| 2位 | 福島県 | 64% |
| 3位 | 東京都 | 62% |
| 4位 | 和歌山県 | 62% |
| 5位 | 京都府 | 57% |
合格率が高い自治体では、2人に1人以上が最終合格しているという驚異的なデータもあります。
特に島根県は応募者数が少ない割に採用人数が比較的多いため、合格率が突出して高くなっています。
東京都も意外に思われるかもしれませんが、「採用数の多さ」が高合格率につながっている典型例です。
人口が多い=受験者も多いですが、それ以上に採用者数も多く、結果的に合格率が高くなるという仕組みです。
一番合格率が低い大阪府(11%)、一番合格率が高い島根県(65%)ではかなり差があります。
難易度の違いは「自治体の採用方針」による
ここで大切なのは、難易度の差は勉強量の差ではないということです。
「大阪府の問題が特別難しい」わけではない
「島根県の問題が簡単」なわけでもない
ではなぜ差がつくのか?
それは、各自治体の「採用人数」が大きく関係しているからです。
たとえば、
大阪府:受験者1,657人 → 最終合格者185人(採用枠が少ない)
東京都:受験者2,137人 → 最終合格者1,335人(採用枠が非常に多い)
このように、「採用枠の規模」と「応募者数のバランス」が合格率に直結しています。
難易度の高い自治体を目指すべきか?
「やっぱり合格率の高いところを狙ったほうがいいのかな…」と感じる人もいるでしょう。
確かに、どうしても公務員になりたい!という方は、合格率の高い自治体を狙うのは一つの戦略です。
特に以下のような方にはおすすめです。
居住地にこだわりがない
地元に戻ってUターン就職を希望している
国家公務員よりも地域密着で働きたい
一方で、難関自治体に挑戦する場合は、
学歴や筆記に自信がある
都市部で働きたい(福祉、インフラ、国際交流など分野が多い)
募集人数の多さを活かして逆にチャンスと捉えたい
といった考え方もできます。
公務員試験の知っておいたほうがいいポイント
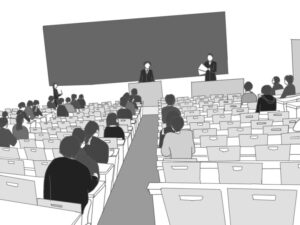
ここでは、自治体の合格率を調べているなかで気づいたことや私の経験に基づく公務員試験のポイントを紹介します。
試験区分で倍率は全然違う(様々な試験タイプがある)
行政職の試験には、「一般枠」以外にも様々な試験タイプがあります。
- SPI型
- アピール型
- プレゼンテーション型
- 創造力型
- Uターン型
- 先行実施型
- 社会人型
- キャリア活用型
これらの試験は専門試験がなかったり、一般枠との併願もできることが多いため、とても人気で競争倍率も高くなり狭き門となっています(合格率が低い)。
申込者数にビビりすぎない(受験者は大幅に減る)
公務員試験の申込者数は多くなりがちですが、実際に受験する人は大幅に減ります。
申込して実際に試験を受けた人の割合(受験率)を調べたところ、
- 国・総合職 約78%
- 国・一般職 約70%
- 都道府県 約74%
- 政令指定都市 約73%
という結果でした。
受験しない理由としては、
- 併願のつもりで申し込んだけど結局受けなかった
- 申し込みしたけど、勉強が間に合わなかった
- 予定が入ってしまった
- 体調不良
- なんとなく申し込んでみた
などが考えられます。
公務員試験は無料で受験できるので、その点も影響していると思います。
そして、受験したとしても、「記念受験」が多いのも事実です。
そのため、実際の合格率よりは難易度が低いと推察されます。
地方より都市部のほうが合格率が低い?
私は「都市部の自治体は受験生が多いので合格率が低くなる」と思っていました。
しかし、調査してみると、地方でも合格率が低い自治体はたくさんあり、逆に都市部でも合格率が高い自治体もありました。
都市部は受験者は多いですが、その分多く採用している自治体があるので、合格率が高くなっています。
面接試験で落とされる受験生が結構いる
実は公務員試験では、筆記試験に合格しても面接試験で結構落とされます。
面接試験の合格率は、以下のとおりです。
- 国・総合職 約68%
- 国・一般職 約87%
- 都道府県 約61%
- 政令指定都市 約64%
筆記試験に合格しても、3人に1人ぐらいは不合格になっていることが分かります。
国は面接試験後に個別面接みたいな官庁訪問があるので、さらに落とされる受験生は多くなります。
合格者の出身大学&1次試験合格ライン

ここでは、合格者のデータとして、私の県庁時代の知り合いの出身大学を紹介します。(地方の県庁)
また、筆記試験を合格ライン(ボーダーライン)も紹介しますので、勉強の参考にしてください。
私の県庁時代の知り合いの出身大学(地方の県庁)
私の先輩・同期・後輩(地方上級で採用された人たち)39人分の出身大学を紹介します。
【行政職】
国立大学:地元国立大学2人、京都大学、東北大学、神戸大学大学院、金沢大学、筑波大学、横浜国立大学2人、新潟大学、群馬大学
私立大学:早稲田大学2人、中央大学4人、法政大学、中堅私立大学大学院(大学名忘れ)、中堅私立大学(大学名忘れ)
【技術職】
国立大学:地元国立大学(総合土木3人、建築、農業、林業2人)、東大(林業)、新潟大学(林業2人、建築)、名古屋大学(林業)、金沢大学(総合土木)、宇都宮大学(林業2人)、三重大学(林業)
私立大学:北里大学(獣医師)、日本大学(薬剤師)
【参考記事↓】
【公務員試験合格率】国立大学と私立大学どっちが高い?(県庁職員の出身大学名も紹介!)
【参考】1次試験合格ライン
1次試験の合格ライン(合格者最低得点)はいくつかの自治体で公表されています。
私が調べたところ、以下のようになりました。
【都道府県行政職(大卒程度)の1次試験合格ライン(得点率)】
- 長野県 50%
- 愛媛県 49%
- 高知県 48%
- 徳島県 57%
- 佐賀県 56%
- 大分県 53%
- 熊本県 44%
- 沖縄県 54%
- 千葉市 55%
※得点率は教養+専門の数値
【参考記事↓】
公務員試験(教養・専門)の平均点やボーダーライン(合格者最低点)はどのくらい?
勉強法
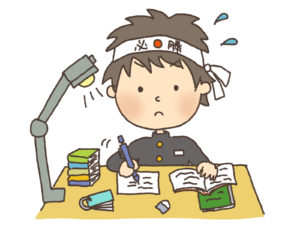
簡単に公務員試験の勉強法について、紹介します。
勉強法(独学・通信講座・予備校)
公務員試験の勉強法には、
- 独学
- 予備校(通信講座)
- 予備校(通学)
があります。
それぞれの勉強法を比較すると以下のようになります。
| 勉強法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 独学 | 最安(1~3万円) | 自分で勉強できる人 |
| 通信講座 | 安価&面接対策あり | 忙しい社会人・地方在住者 |
| 通学予備校 | 高いが手厚い | 面接が苦手、モチベ維持が苦手な人 |
【参考記事↓】
【公務員試験(教養試験)】合格できる人の独学の方法9選(教養の勉強は独学で十分)
公務員試験独学受験生必見!最新のおすすめ参考書10選(教養試験・大卒程度)
おすすめの予備校(通信講座・通学)
予備校といってもたくさんあるので、私のおすすめを紹介します。
【おすすめの予備校(通信講座タイプ)】
内定特典で全額返金がある(合格すれば無料) → アガルート
【おすすめの予備校(通学タイプ)】![]()
合格率が多く信頼できる → EYE(資料請求)
【参考記事↓】
【公務員予備校11社比較】もう迷わない!おすすめ「通信講座」はズバリここ!(元県職員監修)
まとめ
この記事では、公務員試験の難易度を「合格率」という明確なデータをもとに紹介してきました。
ポイントを振り返ると…
✅ 公務員試験の難易度は「思っているより高くない」
国家一般職や都道府県の平均合格率は約35〜44%
難関資格(司法書士5%、行政書士13%など)と比べれば合格しやすい
つまり、しっかり準備すれば十分に合格が狙える試験です。
✅ 合格率は自治体ごとに大きく異なる
合格率が65%の島根県もあれば、11%の大阪府もある
難しさは問題のレベルではなく、**倍率(採用数と受験者数のバランス)**によるところが大きい
つまり、受験先の選び方次第で合格の可能性はグッと変わります。
✅ 筆記試験に受かっても油断禁物!面接対策が重要
多くの自治体で筆記合格者の3人に1人は面接で不合格
「筆記さえ受かれば何とかなる」は間違い!
だからこそ、筆記対策と並行して、面接対策にも力を入れることが重要です。
✅ 独学でも合格は可能!でも戦略と自己管理がカギ
独学で合格する人もたくさんいる(筆者もその一人)
ただし、「面接」「論文」「モチベ維持」に自信がない人は通信講座・予備校の活用もアリ
最近は「合格で全額返金」など、コスパの良い通信講座も多く、上手に活用すればお金をかけずに最短合格を目指せます。
✅ そして一番大事なのは「最後まで諦めないこと」
公務員試験は、東大生や有名大学出身者だけが受かるような試験ではありません。
情報をしっかり集めて、
自分のレベルに合った戦い方をして、
最後まで学習を継続できた人
が合格している試験です。
どんなに倍率が高い自治体でも、毎年必ず合格者は出ています。
だからこそ、「どうせ無理かも…」と決めつけずに、まずは一歩踏み出してみましょう。
▶ 公務員を本気で目指すあなたへ
もっと詳しい試験の流れや対策法を知りたい方は、クレアールが無料配布している「公務員試験入門ハンドブック」もチェックしてみてください。
✔ 公務員の仕事内容がざっくりわかる
✔ 試験スケジュールや科目も一覧で確認できる
✔ 合格体験談や勉強のコツも掲載
👉 無料で資料請求できます(※売り込みなし・勧誘なし)
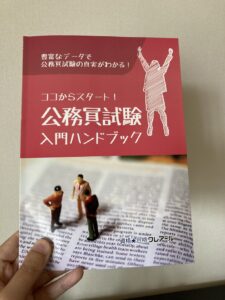
最後に、あなたが公務員として活躍する未来を心から応援しています。
「正しい努力を、正しい方向で、継続する」
これが、公務員試験を勝ち抜くための最大の秘訣です。
一緒に、頑張っていきましょう!
