「公務員ってお盆に休めるの?」
「夏季休暇って何日あるの?」
「民間企業みたいに長期連休は取れるの?」
──こうした疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
実は、公務員には「夏季休暇」という独自の特別休暇制度があります。
ほとんどの自治体で導入されており、年次有給休暇(いわゆる有給)とは別に、夏の時期に数日間の休みを取ることができる制度です。
ただし、「お盆休み」は法律上存在しません。
多くの公務員はカレンダーどおりに出勤しており、夏季休暇をお盆に合わせて取るかどうかは個人や職場の判断に委ねられています。
私自身、9年間県職員として働いていましたが、夏季休暇の取り方や雰囲気は部署によって大きく異なりました。
お盆中に出勤する“若手あるある”や、上司から「必ず全員取得しろ」と言われた実態など、ちょっとした裏話もあります。
この記事では、
公務員の夏季休暇の日数・取得時期
お盆休みとの違い
各自治体の具体例(東京都・千葉県・横浜市など)
取得の実態と上手な使い方
を、元県職員・FP資格保有の筆者がわかりやすく解説します。
「夏季休暇のリアルな取り方」から「混雑を避けた休みの使い方」まで、この記事を読めばすべてわかります。
それでは早速、基本から見ていきましょう。
- 国家公務員は3日間、地方公務員は5日間が多い
- 取得できる時期は7月から9月が多い(自治体によっては6月からもある)
- 夏季休暇はあるが、お盆休みはない
- 夏季休暇の取得をノルマとしている自治体がある
公務員の夏季休暇とは?【基本制度をわかりやすく解説】

夏季休暇の目的と法的根拠
公務員の「夏季休暇」とは、暑い時期に職員が心身をリフレッシュするために設けられた特別休暇制度のことです。
これは年次有給休暇(いわゆる「有給」)とは別に付与されるもので、給与は全額支給(有給扱い)されます。
法的には、国家公務員の場合は「人事院規則(勤務時間・休暇等)」に基づき、地方公務員は各自治体の「職員の勤務条件に関する条例」または「人事委員会規則」で定められています。
この制度の目的は、
「職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため」(引用:人事院規則15-14第22条の15)
とされています。
つまり、単なる“おまけ休暇”ではなく、公務員の福利厚生の一環として国・自治体が制度的に整備している休暇なのです。
「有給休暇」や「特別休暇」との違い
「夏季休暇」と「年次有給休暇(有給)」を混同している方も多いですが、次のような明確な違いがあります。
| 項目 | 夏季休暇 | 年次有給休暇 |
|---|---|---|
| 日数 | 3〜6日(自治体による) | 年20日(勤続年数に応じ付与) |
| 給与 | 100%支給 | 100%支給 |
| 取得時期 | 夏期(6〜9月が中心) | 通年(自由に取得可能) |
| 性質 | 特別休暇(福利厚生目的) | 労働者の権利として付与 |
要するに、「夏季休暇」は“追加で与えられる特別な有給”のようなもの。
この日数分は年休とは別枠で休めるため、うまく活用すれば長期休暇を作ることもできます。
ほぼすべての自治体で導入されている
総務省の「令和5年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」によると、都道府県・指定都市・市区町村の99.6%が夏季休暇制度を導入しています。
つまり、公務員として働いている限り、ほぼ全員がこの制度の対象です。
自治体によって呼び名が「夏期休暇」「夏季特別休暇」など微妙に異なる場合もありますが、内容はほぼ共通しています。
元県職員としての実感
私が勤務していた県庁では「7月〜9月の間に5日間取得」がルールでした。
管理職が毎年、各係に「夏季休暇計画表」を配り、誰がいつ休むかを事前に調整。
多くの職員はお盆期間に休みを合わせますが(お盆中必ず誰か1人は出勤するよう事前に係内で調整)、私はあえてお盆を避けて取得する派。
なぜなら、観光地も空いていて旅行費も安く、役所内も業者が休みで県民も帰省やお盆で忙しく来庁者がほぼなく落ち着いて仕事が進めやすかったからです。
また、夏季休暇の取得状況は管理職がしっかりチェックしており、「全員必ず取るように」という指示が出ていたのをよく覚えています。
「7月中に1日、8月に3日、9月に1日」というように分割取得もOKでした。
ただし、夏季休暇の取得率は100%を求められていたため、どんなに忙しくても「必ず全員が取ること」がノルマ化していました。
(取得日を提出しておかないと“管理職査定”に響くという噂もありました……)
国家公務員と地方公務員の夏季休暇の違い
公務員の夏季休暇は、国家公務員と地方公務員で日数・取得時期に違いがあります。
まずは、それぞれの制度の概要を整理してみましょう。
国家公務員の夏季休暇:原則「連続3日間」

国家公務員の場合、夏季休暇は「連続する3日間」と定められています。
取得可能な期間は、7月から9月までの3か月間です。
休暇日数:連続する3日間
取得期間:7月1日~9月30日
根拠:人事院規則15-14「勤務時間及び休暇」第15条(参考:「人事院HP 勤務時間・休暇制度」)
なお、原則として連続取得が求められますが、特別な事情があれば分割取得が認められる場合もあります。
職場によっては「業務が立て込むので1日ずつ分けて取ってもよい」と柔軟に運用しているケースもあります。
地方公務員の夏季休暇:自治体により5~6日が主流
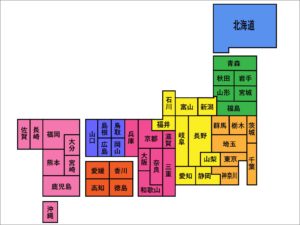
一方、地方公務員(都道府県・市町村職員)の場合、夏季休暇の日数や取得可能期間は自治体によって異なります。
おおむね「5〜6日間」が多く、6月から取得できるところもあります。
以下は主要自治体の例です。
| 自治体 | 日数 | 取得期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 5日間 | 7月1日~9月30日 | 自由に分割可 |
| 千葉県 | 6日間 | 6月1日~9月30日 | 6月から取得可能 |
| 新潟県 | 原則5日間(連続) | 7月1日~9月30日 | 分割は原則不可 |
| 横浜市 | 5日間 | 6月1日~9月30日 | 分割可・時季変更命令あり |
出典:「東京都人事委員会HP 職員の勤務条件」、「千葉県HP 勤務条件・研修制度」、「新潟県HP 勤務時間・休暇制度概説」、「横浜市一般職職員の休暇に関する規則」
このように、国家公務員よりも日数が長く、柔軟に取れるのが地方公務員の特徴です。
【比較表】国家公務員 vs 地方公務員
| 区分 | 国家公務員 | 地方公務員 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 人事院規則 | 各自治体条例・人事委員会規則 |
| 休暇日数 | 3日間(原則連続) | 5~6日間(自治体により異なる) |
| 取得時期 | 7~9月 | 6~9月が多い |
| 分割取得 | 原則不可(特例で可) | 多くの自治体で可 |
| 給与 | 全額支給(有給) | 全額支給(有給) |
夏季休暇はいつ取得できる?お盆との関係を解説

「公務員にはお盆休みがあるの?」──この質問、非常に多いです。
結論から言うと、公務員には「お盆休み」という制度は存在しません。
しかし多くの職員が、夏季休暇をお盆の時期に合わせて取得しています。
公務員に「お盆休み」が存在しない理由
民間企業では「お盆休み(会社全体の一斉休業)」を設けているところが多いですが、公務員の場合は基本的にカレンダーどおりの勤務です。
理由はシンプルで、役所は住民サービスを提供する機関だから。
役所の窓口を閉めてしまうと、住民票の発行や手続きができなくなってしまうため、一斉に休むことはできません。
ただし、役所内では「お盆中は来客が少ないから休みを取るチャンス」という暗黙の了解があり、多くの職員がお盆の週に夏季休暇をまとめて取得するのが一般的です。
実際のお盆期間の勤務状況
お盆期間中(例:8月13日〜16日頃)は、庁舎内がかなり静かになります。
来客・電話も減り、業務も比較的落ち着くため、“夏季休暇のピーク”といってよいでしょう。
ただし、完全に職員がいなくなるわけではなく、どの部署でも最低限の人員(当番)を残す体制が取られています。
若手職員の“お盆出勤あるある”
お盆期間中の職場には、こんな“あるある”も存在します。
「若手が率先してお盆出勤を名乗り出る」のが通例
お盆中の出勤は“気遣いアピール”の一環になる
管理職から感謝されることもある
職場が静かで意外と快適
「食堂が閉まってて困る」など地味な苦労も
このように、お盆期間中の勤務は人間関係の潤滑油的な行動になるケースもあります。
バランスが大事です。
夏季休暇をお盆以外に取るメリット
お盆に休む人が多い中、あえて時期をずらして休むメリットもあります。
旅行や宿泊費が安い(繁忙期を避けられる)
観光地や帰省先が空いている(渋滞を回避できる)
職場の業務が落ち着いている時期を選べる
他の職員と休暇が重ならず気兼ねが少ない
まとめ:お盆=休みではないが、うまく活用できる
公務員には制度上の「お盆休み」は存在しない
ただし多くの職員が、お盆時期に夏季休暇を取得している
若手は出勤当番になるケースも多い
時期をずらせば旅行・家族行事にも便利
つまり、夏季休暇は“自分で自由に設計できる休み”なのです。
混雑を避けて休むも良し、お盆に家族と過ごすも良し──うまく使えばメリットだらけです。
夏季休暇の取得率と「ノルマ化」の実態
制度としては恵まれている公務員の夏季休暇ですが、実際の運用には独特の“現場ルール”があります。
多くの自治体では、夏季休暇の取得が「実質ノルマ」になっているのです。
「必ず全員取得しろ」と言われる理由
多くの自治体では、管理職が部下の夏季休暇の取得状況を定期的にチェックしています。
その背景には、「職員の健康保持」「取得率向上」の他に、上層部への報告義務があるからです。
✅ 典型的な流れ
各係が「夏季休暇計画表」を提出
課長 → 部長 → 人事課 に報告
取得率が低いと「なぜ取らせていないのか?」と管理職が注意される
つまり、職員が自発的に休みを取らないと、上司の評価が下がるという構造があります。
そのため、上司から「まだ取ってない人は早く日程を出せ」と声がかかるのです。
「もぐり出勤」とは?現場に潜むグレーな慣行
とはいえ、繁忙期などでどうしても休めない職員もいます。
そんなときに発生するのが、いわゆる「もぐり出勤」です。
「休暇届は出したが、実際は出勤して仕事をしている」という行為で、形式上は“休暇を取ったことにしている”状態。
もちろん公式にはNGですが、実際には一部の職場で黙認されていました。
「忙しい部署ほど、もぐりが多い」のが実情です。
もぐり出勤が生まれる背景には、「全員取得が義務化されているのに、実際は仕事が回らない」という制度と現実のギャップがあります。
取得率を上げるための“形だけ運用”
一部の自治体では、夏季休暇取得率100%を目標値として掲げており、報告書上は全員取得となっているケースが少なくありません。
実際の勤務実態を反映していないことも多く、「形式的な運用」「数字合わせ」になっていることもあります。
しかし、最近では働き方改革の流れもあり、「無理に取得率を上げるより、実際に休ませよう」という方向にシフトしつつあります。
まとめ:夏季休暇は「制度としては理想、運用は現場次第」
夏季休暇は原則全員が取得を求められる(ノルマ化傾向あり)
繁忙期の部署では「もぐり出勤」も発生
実際の取得状況は部署の業務量に大きく左右される
近年は働き方改革で“本当に休める職場づくり”が進行中
夏季休暇の上手な使い方とおすすめ時期
せっかくの夏季休暇。
「なんとなく家で過ごして終わった」ではもったいありません。
公務員の夏季休暇は、取得時期をずらすだけで満足度が大きく変わる休暇です。
ここでは、実際に元県職員だった私が感じた「賢い使い方」や「おすすめの取得時期」を紹介します。
お盆を避けた“穴場休暇”の取り方
お盆(8月中旬)は多くの職員が夏季休暇を取得するため、職場も観光地も混雑します。
そのため、お盆以外の時期に休むのが圧倒的におすすめです。
たとえば──
| 時期 | メリット |
|---|---|
| 7月中旬 | まだ夏本番前で宿泊費が安い・空いている |
| 8月下旬 | 観光地の混雑が落ち着く・職場も休みやすい |
| 9月上旬 | 涼しく快適・旅費が最安水準になる |
長期休暇を作る裏ワザ:有給との組み合わせ
夏季休暇は「特別休暇」なので、有給休暇と併用することが可能です。
うまく組み合わせることで、最大9連休にすることもできます。
📅 例:5日間の夏季休暇+2日の有給を組み合わせたケース
金曜:年休
土曜:公休
日曜:公休
月曜〜金曜:夏季休暇5日
土曜:公休
日曜:公休
👉 10連休達成!
このように、祝日や土日を挟むだけで大型連休が手軽に作れるのが公務員の特権。
仕事の引き継ぎをしっかり行えば、気兼ねなく長期休暇を楽しめます。
家族や育児と両立する夏季休暇の使い方
家庭がある方は、「家族の予定に合わせて柔軟に休める」のが夏季休暇の魅力です。
学校の夏休みや保育園行事に合わせて取得すれば、家族時間をしっかり確保できます。
💡おすすめの使い方例
子どもの夏休み最終週に合わせて旅行
保育園の登園日を利用して“夫婦で平日デート”
お盆後の静かな時期に帰省
実家で祖父母と過ごす時間を確保
旅行・帰省以外のおすすめの過ごし方
夏季休暇は必ずしも「旅行に行くための休み」ではありません。
“リセット週間”として、自分の時間に使うのも大いにアリです。
✅ 夏季休暇の有意義な過ごし方アイデア
溜まった本を読む(自己啓発・資格勉強)
普段できない家の片付けや断捨離
将来設計・資産運用の見直し
- 株式投資に没頭
新しい趣味のスタート
家族と日帰りドライブ
混雑・ストレスを避けるコツまとめ
お盆期間を避けるとコスパ最強
夏季休暇+有給で9連休も可能
家族行事・育児に合わせて自由に調整
旅行以外にも自己投資のチャンスあり
【悲報】公務員に「ゴールデンウィーク休み」は存在しない?
「公務員はゴールデンウィーク(GW)も長期休みなんでしょ?」
──こんな誤解、よく聞きます。
しかし実際のところ、公務員には“ゴールデンウィーク休み”という特別な制度は存在しません。
カレンダー通り勤務が基本
国家公務員・地方公務員ともに、基本はカレンダー通りの勤務です。
つまり、祝日と土日が続く期間は自動的に休みになりますが、その間に平日が挟まっていれば出勤日になります。
例:5月の暦が「3日・4日・5日が祝日」で「2日が平日」の場合
→ 5月2日は原則、通常出勤。
役所は住民対応のため、民間企業のように「会社全体で休業」とはいきません。
そのため、「10連休」などになることはほぼありません。
それでも“実質連休”を作る方法はある
ここでポイントとなるのが、夏季休暇や年次有給休暇との組み合わせです。
公務員は有給休暇を比較的自由に取得できるため、GWや夏休みをカスタマイズ連休化することが可能です。
📅 例:5月2日(平日)を年休にした場合
→ 4月29日(土)〜5月7日(日)で 最大9連休!
また、夏季休暇を7月や9月にまとめ取りすれば、GW・夏・年末年始の「3大連休」をそれぞれ充実させることもできます。
夏季休暇のように“全員取得必須”ではない点が特徴でした。
夏季休暇+GW+年休=最強カレンダーの作り方
| 期間 | 活用する休暇 | 最大連休例 |
|---|---|---|
| 5月上旬 | 年次有給休暇(GW中の平日) | 9連休 |
| 7〜9月 | 夏季休暇+年休 | 8〜10連休 |
| 12〜1月 | 年末年始の公休+年休 | 9〜11連休 |
上手に計画すれば、年3回の大型連休を作ることができます。
夏季休暇を“お盆以外の穴場”に取ると、混雑を避けながらコスパ良く過ごせるのも公務員の強みです。
まとめ:制度を理解すれば“連休設計”は自由自在
公務員に特別な「GW休暇制度」はない
祝日と土日が重なる年は自然に長期連休になる
年休や夏季休暇を組み合わせれば9連休以上も可能
スケジュール管理と引き継ぎがカギ
まとめ:夏季休暇は有効活用して心身をリフレッシュしよう
ここまで、公務員の夏季休暇制度の内容からお盆期間との関係、取得の実態、上手な活用法までを詳しく解説してきました。
最後に、ポイントを簡潔に整理しましょう。
✅ 公務員の夏季休暇まとめポイント
夏季休暇は公務員全員に与えられる特別休暇(有給扱い)
国家公務員は3日、地方公務員は5〜6日が一般的
取得時期は6月〜9月の間(自治体により異なる)
「お盆休み」は制度上存在しないが、多くの職員がお盆に取得
取得率は高く、実質“ノルマ化”している自治体も多い
有給休暇と組み合わせれば9連休以上も可能
お盆を避けることで“コスパの良い休み方”が実現できる
💬 筆者からのアドバイス(元県職員・FP資格保有)
私が県庁で勤務していた頃、夏季休暇は数少ない「自分の裁量で取れる休み」でした。
多くの職員が「仕事が落ち着いてから取ろう」と後回しにして、結局消化できないケースも見てきました。
ですが、休暇を取ることは「自己管理能力の一部」です。
うまく活用すれば、
業務の効率アップ
家族との関係改善
ストレス軽減
など、長期的なパフォーマンスにも良い影響を与えます。
🧩 チェックリスト:夏季休暇前にやっておきたいこと
夏季休暇計画表の提出(早めに!)
引き継ぎ資料の作成
お盆以外の時期の旅行プランを調べる
有給との組み合わせを検討
休暇中の自己投資(本をあらかじめ探しておく)・資格勉強(目指す資格を決めておく)の時間を確保
「休む=怠ける」ではなく、「休む=整える」。
夏季休暇は、公務員が長く健やかに働くための“戦略的休暇”です。
他にも公務員の休暇制度などについて記事を書いていますので、良かったらご覧ください。
