今回の記事では公務員の「副業(せどり、ブログ、YouTubeなど)」について、元公務員(9年)が紹介します。
おもに、
- 現役公務員で副業をしたいと考えている人
- 公務員になりたいと思っている人
に役立つ内容となっています。
- 国家公務員の「せどり」は禁止!ヤフオクやメルカリにも注意が必要!
- ブログやYouTubeも報酬を得る場合は注意!
- 公務員が副業を行う際は、事前に職場に確認し、許可を得てから行うべき!自己判断は厳禁!
この記事を書いた人

公務員の副業はグレーゾーン化

公務員は、法律で「あらゆる兼業を制限」されていて、禁止あるいは許可がなければ原則行うことはできません。
細かい法律の話は別記事の「【公務員副業】兼業は許可制。ただし、具体的な許可基準がない。」をご覧ください。
ただし、副業を制限する法律はありますが、公務員の副業については「グレーゾーン」となっている部分があります。
その一番の原因は「禁止または制限する副業の具体的な基準(仕事名)」がないためです。
そのため、ブログはダメ、YouTubeは良い、ココナラはダメ、クラウドワークスは良い、ヤフオクは良いなど、法律を拡大解釈したりして、個人で判断してしまう公務員がいて「グレーゾーン」化しています。
ネット上にも、公務員の副業について賛否両論さまざまな意見がありますし、現役公務員ブロガーでブログ上に広告を貼り付けている方も見かけます。
ちなみにですが、不動産または駐車場の賃貸については、なぜか以下のように詳しく法律で基準が定まっています。
【不動産又は駐車場の賃貸】
- 独立家屋・・・5棟以上
- アパート・・・10室以上
- 土地・・・10件以上
- 駐車台数・・・10台以上
- 賃貸料収入・・・年額500万円以上
等の場合は、「所轄庁の長等の承認を得た場合には、自営兼業を行うことができる」となっています。
「せどり」は禁止!メルカリやヤフオクには注意!

グレーゾーンが多い公務員の副業ですが、人事院が令和6年3月に発行した「義務違反防止ハンドブック」でいわゆる「せどり」は禁止と書かれています。
このように人事院がはっきりと禁止と言っています。
ここで、注目したいのが「自営に該当し、禁止」です。
「せどり」が自営にあたるなら、ブログやYouTubeだって、
- 「定期的に・継続的に」
- 「不特定多数」
- 「営利追求」
に該当するので、「禁止」とみなすのが筋でしょう。
ブログやYouTubeの私的利用はセーフ

公務員がブログやYouTubeなどのソーシャルメディアを商業目的ではなく、私的に利用することは禁止されていません。
ただし、利用の際の留意点は以下のように決まっています。
- 法令(国家公務員法、著作権法等)を遵守すること。特に国家公務員法に規定する守秘義務、信用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反する発信を行わないこと。
- 所属又は氏名の一部又は全部を明らかにして発信する場合においては、その発信が自らが所属する組織の見解を示すものではない旨を自己紹介等であらかじめ断ることが必要であること。また、その旨を断ったとしてもなおその発信が当該組織の見解であるかのように誤解され、一人歩きするおそれがあることから、発信の内容が個人の見解に基づくものである場合には、その旨が明確に分かるような記述を心がけること。さらに、職務に関連する内容については、発信の可否も含め、慎重に取り扱うこと。
- 業務上支給されている端末を用いて発信を行わないこと。
(「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」総務省人事・恩給局平成25年6月)
報酬を得る場合は許可制

しかし、ブログやYouTubeから報酬を得る場合は話が変わってきます。
結論からいって、公務員は「報酬」を得て、「継続的又は定期的」に働く場合は、「許可制」となっています。
根拠法令は、国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)です。
【国家公務員法第104条】
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問もしくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、もしくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
この第104条について、政府の見解が示されています。
- 国家公務員法第104条は、営利企業の役員兼業や自営兼業以外の報酬を得る兼業を対象としています。
- 対象となる「兼業」とは、労働の対価として「報酬」を得て、事業又は事務に「継続的又は定期的に従事する」場合をいいます。
「報酬」とは、労務、仕事の完成、事務処理の対価として支払われる金銭をいい、交通費等の実費弁償は含まれません。
単発的な講演や雑誌等への執筆で報酬を得る場合は、「定期的又は継続的に従事する」ことに当たりません。
(引用:「国家公務員の兼業について(概要)」内閣官房内閣人事局平成31年3月)
細かい法律の話は以下の記事を参考にしてください。
【参考記事↓】
【公務員副業】兼業は許可制。ただし、具体的な許可基準がない。
ブログやYouTubeで広告収入を得ようと思うと、継続的に記事を書いたり、動画をアップし続けなくてはなりません。
そのため、「継続的」な労務となりますし、広告収入が入るように慣れば継続して報酬を得ることにもなりますので、第104条に該当し許可が必要となります。
バレると場合によっては懲戒処分
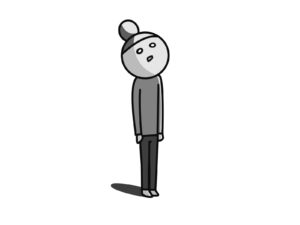
兼業・副業関係もバレると懲戒処分の対象となる場合があります。
例えば、
- 家族から賃貸不動産を含む全財産を相続し、アパート及び駐車場の賃貸を行っていたにもかかわらず、自営兼業の承認申請を怠っていた → 減給処分
- 任命権者の許可を得ることなく、勤務時間外に、飲食店でアルバイトを行い、報酬を得ていた → 減給処分
- 約4年間にわたり、自身が開設したブログや会員制サイトで申込者を募り、対面又はオンラインでコーチングセッションを実施した対価として、報酬を受け取り、兼業をした → 減給処分
(引用元:人事院「義務違反防止ハンドブック」)
このほか公務員の懲戒免職の事例を知りたい方を以下の記事もよかったらご覧ください。
【参考記事↓】
公務員の懲戒免職(クビ)などの事例(受験生、採用予定者、試用期間中も要注意)
副業をする際は職場で事前確認・許可を受けるべき!自己判断は厳禁!

公務員が副業で報酬を得る場合は、基本的に「許可制」or「禁止」だと思ってください。
人事院の「義務違反防止ハンドブック」の兼業について簡単に整理すると、
- 「役員兼業」 → 禁止 (国公法第103条)
- 「自営兼業」 → 禁止 (一定規模以上の不動産又は駐車場の賃貸、太陽光電気の販売は承認を得れば行うことが可能)(国公法第103条)
- 「役員・自営以外のあらゆる有報酬兼業」 → 許可制 (国公法第104条)
となっています。
ポイントは、行いたい副業が「自営兼業」か「役員・自営以外のあらゆる有報酬兼業」のどちらに該当するかです。
そして、その判断は自分で行うのではなく「許可権限をもつ管理職の判断に委ねる」ことが大切です。
法律の文言を自分で拡大解釈して、セーフと決めつけて許可を取らずに勝手に行っている現役公務員がいますが、かなり際どい行動だと思います。
実際に、懲戒処分の事例はたくさんあります。
最後に、国公法第104条の兼業に該当する場合の許可基準の中に、
「国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがある」
と認められるときは不許可となるとあります。
例えば、自分が問題ないと思ってブログを書いたとしても、世の中には様々なご意見をお持ちの方々がいます。
その不特定多数の人の一部でも不信感を抱けばダメということです。
その点からいうと、公務員がブログで稼いだりYouTubeなどで稼ぐことは、法改正がない限り私はあまり良くないと考えます。
公務員でこれから副業をしようと計画している人は、リスクを理解した上で慎重に検討してください。
【関連記事】

