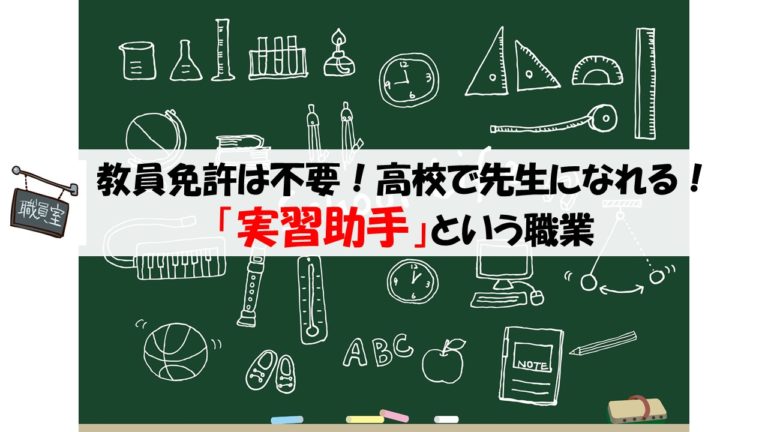教員免許を持っていなくても、高校で学校職員(正規公務員)として働くことができる職業があります。
それは「実習助手」という仕事です。
本記事では、「実習助手の仕事内容」と「試験概要」と「受験体験談」などについて、ご紹介します。

実習助手の仕事内容

実習助手の仕事内容ですが、簡単に言えば、高校での実験や実習時に教員のサポートをする仕事です。
具体的な科目でいうと、理科・農業・工業・土木・水産・社会福祉・家庭など。
ただし、実習助手の職務内容は曖昧な点があり、都道府県などでその扱いが異なる場合があります。
実習助手ができる仕事(一例)
- 実験・実習の補助(メインはこれ)
- 実験室の維持管理
- 校務分掌(進路指導や生徒指導など)
- 部活動等の顧問(ただし、引率は教員免許をもつ教諭が行わなければいけないので、実習助手だけで生徒を大会には連れていけない)
実習助手ができない仕事(一例)
- 担任
- 成績評定
上記の2つは、教員免許が必要な仕事です。
実習助手の採用試験

実習助手の募集ですが、全ての都道府県で実施しているとは限りません。
毎年募集している県もあれば、久しく募集していない県もあります。
また、自治体によって試験名称や試験区分が違う場合があります。
ここで参考例として、令和5年度の東京都、埼玉県、長野県の実習助手採用試験の例を挙げます。
東京都の公立学校教職員採用候補者選考(実習助手)
【採用教科・採用見込数】
- 工業(機械系、電気・電子系、建築・建設系、工芸系)・若干名
- 農業(園芸系、食品系)・若干名
- 家庭・若干名
- 理療・若干名
- 水産・若干名
- 舞台表現・若干名
【受験資格】
- 昭和60年4月2日以降に出生した人
- 高等学校を卒業した人(原則として受験教科に関する学科を卒業した人。普通科は含まない。)
【試験日】
令和6年9月8日(日)
【試験内容】
- 専門教養(60分)
- 論文問題(60分、800字程度)
- 個人面接
【(参考)令和5年度選考結果】
| 教科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 工業(電気・電子系) | 7 | 6 | 1.2 |
| 工業(工業化学系) | 2 | 1 | 2.0 |
| 農業(園芸系) | 5 | 1 | 5.0 |
| 農業(食品系) | 0 | 0 | ー |
| 農業(造園系) | 1 | 1 | 1.0 |
| 家庭 | 6 | 1 | 6.0 |
| 水産 | 0 | 0 | ー |
参考:東京都HP「令和5年度東京都公立学校教職員採用候補者選考(令和6年度採用)(実習助手及び寄宿舎指導員)実施要綱
千葉県の県立学校実習助手採用選考試験
【採用教科・採用予定者数】
- 一般・5人程度
- 工業・若干名
- 農業・若干名
【受験資格】
昭和39年4月2日以降に生まれた人で、高等学校卒業以上の学歴を有する者、または高等学校卒業程度認定試験に合格した者
【一次試験日】
令和6年1月12日(日)
【試験内容】
- 専門試験(受験教科)
- 適性検査
- 論文試験
- 個別面接
長野県の県立高等学校実習助手採用選考
長野県は一般選考と若年者選考の2種類があります。
【採用教科・採用予定者数】
- 農業・若干名
- 工業・若干名
- 理科・若干名
【受験資格】
- 一般選考 昭和39年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人で高等学校卒業以上の学歴を有する人
- 若年者選考 平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人で高等学校卒業以上の学歴を有する人
【一次試験日】
令和5年9月16日(土)
【試験内容】
- 一般教養
- 小論文(800字以内)
- 適性検査(MMPI、クレペリン)
- 個人面接
参考:長野県HP「令和6年度長野県立高等学校実習助手採用選考要項」
実習助手の初任給・手当

実習助手の給与などについては以下のとおりとなっています。
初任給
| 都県 | 初任給 | ※計算式 |
|---|---|---|
| 東京都 | (高校新卒)約196,000円 | 給料月額+教職調整額+地域手当+義務教育等教員特別手当 |
| 千葉県 | (高校新卒)約198,359円 (短大新卒)約220,818円 (大学新卒)約244,272円 | 給料+教職調整額+地域手当等 |
| 長野県 | (高校新卒)186,247円 (大学新卒)229,683円 | 本俸+教職調整額+地域手当+教員特別手当 |
各種手当
扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当(ボーナス)などが支給されます。
昇給は年1回(4月)あります。
実習助手採用試験時の様子(経験談)
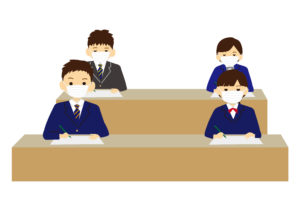
参考に私が実習助手を受験した際の様子(2017年)をご紹介します。
教養試験の難易度
教養試験は、公務員試験初級レベル(高卒程度レベル)ぐらいで、全ての科目からまんべんなく出題されるので、事前に試験勉強の対策をしたほうがいいです。
一次試験合格ライン(ボーダーライン)
私の受験した某県の実習助手の場合ですが、私は記念受験だったので、ノー勉強で臨み、得点率は7割でした。
得点率7割で平均点よりも結構上という結果でした。
(試験結果通知に平均点が掲載されていました)
受験者層
試験会場には、下は現役の高校生、上は50代くらいの人達が来ていました。
過去問
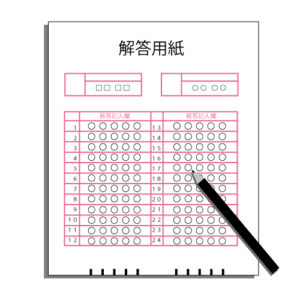
- 「過去問(一般教養と小論文)」
- 「解答及び配点」