「体調を崩して公務員を退職したけど、失業手当がもらえないなんて…今後の生活どうしよう…」
そんな不安や悩みを抱えていませんか?
現役公務員や退職したばかりの元公務員の方の中には、病気やケガが原因で働けなくなった場合のお金の支援制度について、十分な情報が得られずに悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
実際、公務員は「失業手当(雇用保険)」の対象外。
しかし、病気やケガで働けなくなった場合には「傷病手当金」が受給できる可能性があることは、意外と知られていません。
「公務員は傷病手当金なんて出ないでしょ?」
そう思い込んでいたけれど、条件を満たせば在職中はもちろん、退職後でも申請・受給が可能なのです。
このページでは、実体験をもとに、傷病手当金の申請方法・必要書類・注意点・退職後の流れまで、公務員・元公務員の皆さんの悩みや疑問を徹底的に解消できるよう、元受給者で元県職員FPの私がわかりやすく解説します。
【このガイドが役立つ方】
病気やケガで休職中・退職を検討している現役公務員
すでに退職したものの、経済的に不安を抱えている元公務員
傷病手当金の具体的な申請方法や注意点について知りたい方
「申請できるか不安」「退職したらもう間に合わない?」と悩んでいる方
【このガイドでわかること】
公務員の傷病手当金の概要と支給条件
退職後でも申請できるのか?その条件と実体験
申請方法・必要書類・流れを徹底解説
よくある質問(Q&A)・申請時の注意点
プロ(社労士・退職コンシェルジュ等)への無料相談サービスの活用法
実際の受給者の体験談・リアルな支給額例
退職前にやるべきこと・受給に必要な準備
これから傷病手当金の申請を考えている公務員・元公務員の方に、「この記事だけ読めば迷わない!」と言ってもらえる徹底ガイドを目指します。
- 傷病手当金は、病気などで働けなくなり、給料が減額・支給されなくなった場合に支給される
- もらっていた給料のおおよそ2/3が毎月支給される
- 1年6ヶ月間受給できる
- 退職後でも申請すれば受給できる
- 申請先は共済組合(申請書類には医師の証明が必要)
- 1 公務員の傷病手当金とは?概要とよくある誤解
- 2 傷病手当金の支給条件と対象となるケース
- 3 公務員の傷病手当金「在職中」の申請方法と流れ
- 4 退職後でも申請できる?公務員の傷病手当金|退職後の受給条件と流れ
- 5 申請時によくある質問と注意点Q&A|障害年金や他制度との違い・申請失敗例も解説
- 6 退職前にやるべき準備|職場や医師との調整ポイント/スムーズな申請のコツ
- 7 傷病手当金で困ったらプロに無料相談!退職コンシェルジュ等の活用法・具体例
- 8 まとめ|傷病手当金を最大限活用して人生を立て直そう
公務員の傷病手当金とは?概要とよくある誤解
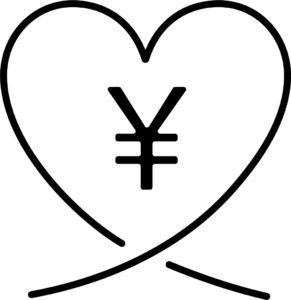
民間と公務員の「傷病手当金」の違いと誤解
まず大前提として、「公務員は民間企業のように失業手当(いわゆる雇用保険の失業給付)が受け取れない」という点を知っている方は多い一方、傷病手当金については誤解が非常に多いです。
「公務員はそもそも傷病手当金がないのでは?」
「病気で休職や退職した場合、全くお金がもらえなくなるの?」
「在職中だけで、退職したら申請できないのでは?」
こうした誤解は、現役の公務員でも、意外と正確に制度を知らない方が少なくありません。
理由は、制度の案内があまり手厚くない・窓口によって説明がバラバラ・自治体や共済組合によって運用が微妙に違う、といった事情があるからです。
【豆知識】
民間企業で働く人は「健康保険組合」から、病気やケガで働けなくなった場合「傷病手当金」が支給されます。
公務員の場合も、ほぼ同等の制度が「共済組合」を通じて用意されています。
(国家公務員は国家公務員共済組合、地方公務員は地方職員共済組合、公立学校職員は公立学校共済組合など)
公務員の傷病手当金とは?
「傷病手当金」とは、病気やケガが原因で就労できず、給料が減額または支給されなくなったときに支給される生活保障の制度です。
組合員が公務によらない病気やケガで勤務を休み、報酬が減額されたり、支給されなくなったりした場合に、傷病手当金が支給されます。また、傷病手当金の受給終了後、同じ病気やケガで引き続き勤務することができない場合は、傷病手当金附加金が支給されます。
(引用:「地方職員共済組合HP」)
在職中はもちろん、一定の条件を満たせば退職後も受給可能です。
【例:実際の相談シーン】
ある地方公務員(30代男性・うつ病で退職)
「退職してから無収入になり、生活費が不安で眠れなくなった。自分で共済組合のHPで調べたら“退職後も傷病手当金が申請できる”と知って、人生が救われた気がした…」
このように、知らなかったがゆえに金銭面で大きな損をするケースも珍しくありません。
退職後の生活資金の要となる大切な制度なので、まずは正しく制度内容を理解しましょう。
傷病手当金の支給額は?
おおよその目安ですが、もらっていた給料の2/3が毎月支給される形となります。
支給額の細かい計算方法は以下のとおりとなります。
1日につき、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近した継続した12ヶ月の各月の標準報酬の月額の平均額の1/22の額(10円未満四捨五入)の2/3の額(円位未満四捨五入)
(引用:「地方職員共済組合HP」)
傷病手当金の支給期間は?
傷病手当金は、病気やケガによる療養のため勤務することができなくなった日から起算して4日目から1年6か月間支給されます。
なお、出勤した期間は支給期間に算入されません、したがって出勤した日数分だけ支給期間を延長されます。
ただし、在職中に傷病手当金が支給されていた期間分は1年6ヶ月間から引かれます。
傷病手当金の基本ポイントまとめ
共済組合から支給される(自治体や職種に応じた共済組合)
支給額は給料の約2/3(標準報酬月額の2/3相当)
最長1年6カ月間受給できる(支給開始から通算)
退職後も条件を満たせば継続受給可
申請には医師の診断書や申請書類が必要
支給対象となるかは「就労不能」かつ医師の証明が必須
給与や他の給付との関係で、受給額や受給可否が変動する場合あり
なぜ「退職後」でも申請・受給できるのか?
多くの人が「退職したら何ももらえない」と思いがちですが、“退職日において傷病手当金の受給要件を満たしていれば、退職後も引き続き支給される”というのが共済組合のルールです。
たとえば、
在職中から病気で休職→退職した
退職時にまだ「就労不能」が続いている
こういった場合、退職日以降も申請・受給できます。
【注意】
ただし、採用1年未満で退職した場合など、一部の例外があります(後述で詳しく解説)。
公務員のメンタルヘルス事情――長期休職・退職が増加している背景
現在、公務員の職場環境は非常にストレスフルであり、長時間労働・高い業務量・責任の重さなどからメンタル疾患で長期休職・退職する職員が年々増えています。
令和5年度における「精神及び行動の障害」による長期病休者数は10万人中約2,286人となっていて、15年前の2倍となっています。
引用データ:一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会「地方公務員健康状況等の現況」(令和6年度)
【参考】公務員の休職中の給料は?
次に、公務員がうつ病等で長期休職した場合の給料事情について、順を追って説明します。
(ここではうつ病などの精神疾患での期間を例にあげます。自治体で算定期間が異なりますので、あなたの自治体の休職制度をよく確認してください。)
【私が勤務していた県の例】
- 最初の180日間:「療養休暇」扱いとなり、この間は病気以前にもらっていた給料の100%が支給されます。(全額支給)
- 療養休暇180日間経過後の2年間:「休職」扱いとなり、給料の80%が支給されます。
- 2年間経過後の1年間:同じく「休職」扱いとなり、今度は給料の約2/3の「傷病手当金」が支給されます。
- 休職期間が3年経過すると、基本的に免職になり、公務員を退職することになります。
例えば、2025年4月1日から療養休暇を取得し始めた場合、おおよそ以下のような流れとなります。
| 種類 | 期間 | おおよその月日 | 給料 |
|---|---|---|---|
| 療養休暇 | 180日 | 2025年4月~2025年9月 | 100% |
| 休職 | 2年 | 2025年10月~2027年9月 | 80% |
| 休職 | 1年 | 2027年10月~2028年9月 | なし(共済組合から約2/3の傷病手当支給) |
| 免職 | 3年経過後 | 2028年9月 | ー |
傷病手当金の支給条件と対象となるケース
傷病手当金の支給条件 ― どんな時にもらえる?
公務員の傷病手当金は、「病気やケガが原因で就労できない」「給料が減額・または支給されなくなった」場合に、共済組合から生活保障として支給されるお金です。
主な支給条件
就労不能の状態であること(医師の証明必須)
「今の状態で公務の仕事はできない」と医師が診断し、診断書に記載する必要があります。
休業により報酬(給料)が減額、または支給されなくなったこと
例えば、休職期間に入り給料がカットされた、あるいは無給になったなど。
4日以上連続して仕事を休んでいること
3日間の待期期間後、4日目から支給対象となります(3日間は有給でも無給でもOK)。
退職後も「傷病手当金の受給要件」を満たしていること
退職前から就労不能状態が続いている場合は、退職日以降も継続して受給できます。
共済組合に1年以上加入していること(例外あり)
採用1年未満で退職した場合などは受給できません。
ここがポイント
「診断書がもらえない」「自分では働けないと思うが、医師が“就労可能”と判断した」場合は受給できません。
軽度の体調不良(軽い風邪など)は対象外です。
原則、自己都合の退職や自己判断の休職は対象外。「医師の診断」「共済組合の承認」がセットで必要です。
支給対象となる主なケース
傷病手当金の支給対象となる病気やケガの種類については、以下のように一般的に認められています。
「働けない状態」が前提となるため、病気やケガの程度や状況によっても判断が変わりますが、主に以下が支給対象となります。
1. 病気やケガによる休業
- 入院や手術後など、治療を受けるために仕事を休まざるを得ない場合
- 慢性的な疾患(糖尿病、心臓病、肝炎など)や急性疾患(インフルエンザ、肺炎など)によって長期間働けない状態
- 外傷(骨折、捻挫、脱臼など)や交通事故によるケガなどで働けない状態
- 精神疾患(うつ病、パニック障害、適応障害など)による休職(精神的な病気も対象)
2. 妊娠・出産に関連する疾患
- 妊娠中のつわりや切迫流産などで働けない場合
- 出産後の産後うつや体調不良による療養が必要な場合
3. リハビリや後療法
- ケガや病気から回復するためのリハビリテーションや後療法(例:手術後の回復期に療養が必要な場合)
4. 精神的・心理的な問題
- うつ病や不安障害、精神的なストレスなどが原因で働けなくなった場合
- 精神的な疾患に関しても、治療やカウンセリングが必要と判断される場合に対象となります
5. 再発性の疾患
- 例えば、がんや喘息などの慢性疾患が再発し、長期間治療を要する場合も対象になることがあります
【注意点】
- 自己判断や軽い病気(風邪や軽度の体調不良など)では、傷病手当金の支給対象にはならないことが一般的です。支給には医師の診断と**「労務不能」**であることの証明が必要です。
- また、公務員の共済組合によって具体的な判断基準が異なることもありますので、共済組合に直接確認することが重要です。
この情報を基に、傷病手当金を申請する際には、しっかりと医師の診断書や必要書類を整え、労務不能の状態であることを証明することが求められます。
支給対象にならないケース・よくある誤解
一方、以下のようなケースは傷病手当金の対象外となるので注意が必要です。
単なる疲労や軽度の風邪・体調不良(医師による“就労不能”の証明がない場合)
自己判断・自己都合での欠勤や退職
労働災害(業務上のケガ)は別途労災保険の対象となるため、傷病手当金と同時には受給できません
1年未満の勤務で退職した場合(新規採用者で早期退職など)
既に障害年金(1・2級)を受給している場合(ただし差額支給の場合もあり。詳しくは後述Q&Aへ)
支給までの流れをシミュレーション
【シミュレーション事例】
2025年4月1日:精神疾患により療養休暇取得(給料100%支給)
2025年10月1日:療養休暇満了→休職(給料80%支給)
2027年10月1日:休職満了→給料ゼロ、共済組合へ傷病手当金の申請(給料の2/3支給開始)
2028年9月30日:支給開始から1年6か月経過→支給終了
Q&A:読者からよくある質問
Q. 精神疾患でも傷病手当金はもらえますか?
A. もちろん対象です。精神科・心療内科の診断書で“就労不能”の証明が出れば申請・受給可能です。
Q. 怪我や病気が原因で退職したが、まだ療養中。退職後でももらえますか?
A. はい。退職日に受給要件を満たしていれば、退職後も継続して傷病手当金を申請・受給できます。
Q. 妊娠や出産が理由の場合も対象になりますか?
A. 切迫流産や重度のつわりなど、医師が“就労不能”と診断した場合は対象になります。
申請時に“落とし穴”になりやすいポイント
医師にしっかり現状を伝える
曖昧な説明だと「就労可能」と診断されてしまい、受給不可になる例あり
庶務担当・共済組合担当と密に連絡をとる
申請手続きや必要書類は自治体・組合で細かい違いがある
退職前に手続きを進めておく
退職後は庶務担当や上司と連絡が取りづらくなり、手続きが煩雑化する
公務員の傷病手当金「在職中」の申請方法と流れ
1. 傷病手当金の申請タイミング
公務員が「傷病手当金」を申請できるのは、病気やケガで“就労不能”となり、給料が減額または支給停止となったタイミングからです。
実際には、以下のような流れをたどります。
【申請の主なタイミング】
療養休暇や病気休暇の期間を経て、「休職」に移行したとき(自治体によって「休職」に入る時期や給料の扱いは異なる)
休職中に、給料や手当が減額またはゼロになったとき
すでに休職しているが、「これから無給になる」というとき(前もって申請準備を進めておくのが理想)
2. 申請に必要な書類
必要な書類は以下のとおりです
傷病手当金支給申請書
(共済組合のWebサイトや庶務担当で入手可能)医師の診断書または証明書
(「就労不能」である旨が記載されているもの。診断期間が明記されているとベスト)給与支給明細や出勤簿等の証明書類
(減額・支給停止の状況を証明するため。必要な場合のみ)本人確認書類(必要に応じて)
注意
初回申請時は「所属長の証明(押印)」が必要なケースが大半です。
2回目以降は医師の証明と本人の申請のみでOKの場合が多いです。
3. 申請手続きの実際の流れ
ステップ1:まずは庶務担当または共済組合に相談
「傷病手当金を申請したい」と申し出ましょう。
最初は“何から始めればいいの?”と不安になるものですが、職場の庶務担当や共済組合に問い合わせれば、基本的な手続きや必要書類を案内してもらえます。
ステップ2:医師に“就労不能”の証明を記入してもらう
定期的に通院している主治医に「傷病手当金の申請をしたい」と伝えます。
医師は診察内容・病状に応じて「就労不能」かどうかを判断し、診断書や申請書に記入します。
【注意点】
申請書の医師記入欄は“いつからいつまで就労不能”かをしっかり記載してもらいましょう。
曖昧な診断内容だと申請が通らない場合があります。
ステップ3:初回申請は“所属長の証明”が必要
初回のみ、所属長(課長や係長など)の証明欄に記入・押印が必要です。
申請書は「庶務担当」を経由して共済組合に提出します。
所属長が不在の場合や休職中は、代理で庶務担当や上司に依頼してもらうことも可能です。
ステップ4:共済組合へ申請書を提出
書類が揃ったら、共済組合へ提出(通常は職場経由。場合によっては直接提出も可)。
不備や疑問があれば庶務担当や共済組合が連絡をくれます。
ステップ5:審査・給付決定
申請後、通常1か月前後で共済組合から「給付決定通知書」が届き、指定口座に振り込まれます。
2回目以降は医師の証明+本人申請のみでOK(所属長の証明不要)。
毎月申請が原則。まとめて申請はできません。
4. 申請手続きでつまずきやすいポイント・よくある質問
Q. 申請書類はどこでもらえる?
A. 各共済組合のWebサイト、または職場の庶務担当で入手できます。
Q. 診断書の費用は自己負担?
A. はい、診断書作成料(数千円~)は原則自己負担です。経済的に厳しい場合は自治体の福祉課などに相談してみましょう。
Q. 初回申請時の「所属長証明」は必須?
A. ほぼ全自治体・職場で必須です。どうしても難しい場合は、共済組合に相談してください。
Q. 審査結果が遅い・書類に不備があった場合は?
A. 共済組合から書類不備や追加提出の連絡があります。不安な場合は早めに問い合わせを。
Q. 申請のタイミングが遅れたらどうなる?
A. 退職後でも“さかのぼって”申請できる場合がありますが、できるだけ早めに手続きを!
退職後でも申請できる?公務員の傷病手当金|退職後の受給条件と流れ
「退職後でも傷病手当金をもらえる」は本当
公務員の多くが「退職したら傷病手当金は申請できない」と誤解しています。
実は、退職時点で傷病手当金の受給要件を満たしていれば、退職後も支給を継続して受けることができます。
これは公務員の共済組合規程で明記されており、現役時代にしっかり手続きを進めておけば、生活再建のための強い味方になります。
退職後に傷病手当金を受給できる条件
1. 退職日に「就労不能状態」が続いていること
退職日の時点で医師が「就労不能」と診断している必要があります。
自己判断ではなく、必ず医師の診断書(証明書)が必要です。
2. 退職前から「傷病手当金の受給要件」を満たしていること
つまり、退職前からすでに病気やケガで休職しており、「4日以上の連続休業」+「給料が減額・支給停止」+「医師の証明」という条件を満たしている必要があります。
3. 共済組合への「毎月申請」が必須
退職後も、毎月、医師の証明と共済組合への申請が必要です。
退職前にしっかり申請フロー・書類を確認し、退職直後もスムーズに動けるようにしておきましょう。
4. 共済組合に1年以上加入していること
新規採用者で1年未満の勤務の場合、傷病手当金の受給資格がないため注意してください。
退職後の傷病手当金 申請手続きの流れ
退職前に庶務担当と調整・手続き準備
申請書類や今後の流れを確認し、必要な証明書はコピーをとっておきましょう。
退職後は職場との連絡が取りづらくなるので、退職前に申請用紙を多めにもらっておくのがベスト。
初回申請時は「旧所属長の証明」が必要
退職直後の初回申請だけは「旧所属長」の証明(押印)が必要です。
旧所属へ書類を郵送するケースが多いので、早めに準備を。
医師に「就労不能」の証明をもらう
退職後も療養が続く場合、毎月、診断書や申請書に「就労不能」の証明を記入してもらいます。
通院予約や診断書発行には日数がかかる場合もあるので余裕を持って行動を。
共済組合へ申請(毎月)
2回目以降は医師の証明のみで直接共済組合へ申請すればOKです(旧所属長の証明は不要)。
郵送での申請が一般的です。
給付決定通知と振込
通常は申請から2~4週間程度で支給が決定し、支給決定通知が届きます。そして、申請から1ヶ月程度で指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の傷病手当金・申請時の注意点
必ず退職前に手続きを確認・準備すること
退職後は庶務担当との連絡が困難になりがち。余裕を持って準備しましょう。
診断書・申請書類のコピーは多めに用意
役所や共済組合とのやりとりで、何度もコピーが必要になるケースがあります。
受給条件・手続きは自治体や共済組合で細かい違いあり
気になることは必ず直接、共済組合へ問い合わせましょう。
Q&A|退職後の傷病手当金についてよくある質問
Q. 退職してから何か月も経ってしまったが、今から申請できる?
A. 申請が可能です。共済組合に問い合わせしましょう。
Q. 退職後、健康保険を「任意継続」せず、国民健康保険に切り替えても受給できる?
A. はい、健康保険の種類にかかわらず、退職時点で共済組合の受給資格を満たしていれば受給可能です。
Q. 初回申請時に旧所属長の証明がもらえない場合は?
A. 共済組合に状況を説明し、必要書類や代替手続きについて相談しましょう。
Q. 退職後に就労できるようになったらどうなる?
A. 医師が「就労可能」と診断した段階で支給はストップします。短時間でも収入が発生すると、「労務不能」ではないと判断される場合があります。必ず主治医と相談しましょう。
退職後の傷病手当金、必ずプロや共済組合に相談しよう
退職後は特に、「誰に聞けばいいのか分からない」「自治体ごとの違いが分からない」と悩む方が非常に多いです。
「分からない…」ときは、迷わず共済組合や退職サポート専門家(退職コンシェルジュ等)に無料相談を利用しましょう。
気になる方は↓
申請時によくある質問と注意点Q&A|障害年金や他制度との違い・申請失敗例も解説

Q1. 複数月まとめて請求できますか?
A. いいえ。傷病手当金は原則「毎月申請」が必須です。
理由は、「申請時にその月の“就労不能”を医師に証明してもらう」必要があるためです。
※どうしてもやむを得ない事情がある場合は共済組合へ事前相談を。
Q2. 申請からどれくらいで振り込まれますか?
A. 通常は「申請から1ヶ月前後」で指定口座に振込となります。
ただし、申請内容や書類不備、共済組合の繁忙期によっては遅れることもあるので余裕を持って申請しましょう。
あくまで私の場合の例ですが、申請から振込まで数週間程度でした(以下、私の実例です)。
【初回申請】
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 3月2日 | 医師から証明欄に記入してもらう |
| 3月2日 | 申請書を提出 |
| 3月19日 | 共済組合より給付金決定通知書が届く |
| 3月29日 | 振込 |
【2回目申請時】
| 月日 | 内容 |
|---|---|
| 4月7日 | 医師から証明欄に記入してもらう |
| 4月7日 | 申請書を共済組合に提出 |
| 4月23日 | 共済組合より給付金決定通知書が届く |
| 4月26日 | 振込 |
Q3. 退職後に健康保険を「国民健康保険」に切り替えたら受給できませんか?
A. 退職後に健康保険を切り替えても、傷病手当金の受給権利は消えません。
退職時点で共済組合の資格と受給要件を満たしていれば、健康保険の種類に関わらず申請・受給できます。
Q4. 障害年金や失業手当との違い・併給は可能?
A. 「傷病手当金」と「障害年金」は基本的に併給不可です。
1・2級の障害年金(共済年金・厚生年金等)を受給している場合は、傷病手当金との差額のみが支給されます。
失業手当(雇用保険)は、公務員はそもそも加入していないため受給不可です。
【参考記事】
公務員は雇用保険(失業保険)未加入なので失業給付はない!(退職時注意!)
Q5. 障害年金と傷病手当金はどちらが有利?
A. 障害年金の方が長期的な収入安定につながりますが、申請のハードルは高いです。
障害年金(特に2級以上)は一生涯または障害状態が続く限り支給されますが、審査・要件が厳格です。
傷病手当金は「最長1年6か月」「医師の“就労不能”証明で申請しやすい」という特徴があります。
両制度の違いを理解し、将来的な見通しや症状の重さに応じて選択・併用を検討しましょう。
Q6. 受給中に「バイト」「副業」や「復職」をしたらどうなりますか?
A. 原則「就労可能」とみなされ、支給は停止になります。
就労可能となった(再就職した、パート・アルバイト・自営業等で労働を始めた場合)または傷病手当金受給の原因となった傷病等が治癒したとの医師の診断があった場合は、その後の傷病手当金は支給されません。
例えば短時間・軽作業など「部分的な就労」の場合でも、収入の有無に関わらず、「労務不能」ではないと判断されると支給停止となる可能性があります。ただし、就労内容や医師の意見によって判断が異なる場合があり、グレーゾーンも存在します。
一度復職した後に再び同じ病気・ケガで働けなくなった場合、一定期間内(同一傷病で1年6か月以内)なら再度受給できることもあります(継続給付)。
Q7. 傷病手当金受給中に公務員試験の受験・再就職活動は可能?
A. 受験・就職活動自体は自由ですが、「勤務可能」となったら支給は止まります。
現在勤めている職場や職種が原因で病気を発症した場合、他の公務員に転職したい場合もあると思います。
または、一度公務員を退職して傷病手当を受給中だけど、公務員に出戻りたくなった場合も考えられます。
その場合でも、受験することは可能ですし、面接官も傷病手当のことは一切聞いてきませんし、既往歴等を聞くことは差別につながるので禁止されています。
Q8. 受給に失敗しやすい・もめやすいポイントは?
【落とし穴・失敗例】
退職前に十分な説明や申請準備をしなかった
旧所属と連絡が取れず初回申請が遅れる
医師の証明が曖昧/「就労可能」と書かれてしまい却下
主治医にきちんと状況・症状を説明し、「就労不能」と明確に記載してもらうこと
必要書類・診断書のコピーを取り忘れ、再取得に苦労
共済組合ごとの細かいルールの違いを見落とす
必ず自分の共済組合に直接確認!
退職後、最初に手続きしたとき“申請書の記入ミス”で差し戻しや、診断書の有効期間が切れていて取り直しなど、不備があることがあります。
慣れない書類作成は面倒ですが、細かい部分まで要チェックです!
Q9. どうしても手続きや条件が不安なときは?
A. 迷わず「共済組合」または「退職コンシェルジュ」などプロの無料相談を活用しましょう。
特に退職後の初回申請、長期に療養が必要な場合はサポートを受けた方が安心です。
診断書の取得・申請書記入・証明のもらい方・トラブル時の対応など、個別に丁寧にアドバイスをもらえます。
気になる方は↓
退職前にやるべき準備|職場や医師との調整ポイント/スムーズな申請のコツ
1. 退職前に必ずやっておくべき準備
(1)庶務担当や共済組合担当と事前にしっかり打ち合わせを
退職後の傷病手当金申請には「旧所属長の証明」や職場の協力が不可欠です。
退職前に申請書類をもらい、手続きの流れを確認しておくことがスムーズな受給のカギ!
「何もわからないまま退職して、あとで困った…」という声が多いので、できれば庶務担当に「傷病手当金を退職後に申請したい」とはっきり伝えておくと安心です。
(2)診断書・申請書のコピーを多めに用意しておく
退職後は職場と物理的な距離ができるため、「診断書」や「申請書の控え」を多めに用意しておくことが重要です。
郵送や再取得には時間も手間もかかるため、必要書類はすべてPDFなどでも保存しておくと安心です。
(3)主治医と綿密に相談し「就労不能」の証明を明確に記載してもらう
傷病手当金の可否は医師の「就労不能証明」にかかっています。
診断内容や症状を医師にしっかり伝え、「今の自分の状態では就労できない」ことを具体的に記載してもらいましょう。
必要があれば診断書のサンプルや「こう書いてほしい」という希望を伝えることも大切です。
【ワンポイント】
医師に「○月○日から○月○日まで“就労不能”」と明確な期間を書いてもらうと、申請がスムーズです。
(4)申請書・診断書の有効期限を意識する
傷病手当金は「毎月」申請が必要なため、診断書の有効期間が切れていないか毎回確認しましょう。
体調が安定しない場合、長めに診断期間を書いてもらう相談も◎。
(5)共済組合ごとの細かいルールを必ず確認する
共済組合は自治体や職種によって運用に差があります。
「ネット情報」や「他人の経験談」だけを頼らず、自分の所属する共済組合に直接確認しましょう。
2. スムーズな申請のコツ
◎ 退職前に「申請書」「診断書」をまとめて入手しておく
退職後に「もう1枚診断書が必要…」となると手続きが遅れがち。数か月分をもらっておける場合は、前もって主治医に相談しましょう。
◎ 申請のタイミング・時効を厳守
遡及申請できる場合もありますが、できるだけ早く、毎月申請するのがベストです。
◎ 困ったら迷わずプロや相談窓口を活用
退職コンシェルジュや社労士、共済組合の相談窓口を使えば、トラブル時にも最短で解決策が得られます。
「無料相談」があるサービスは積極的に利用しましょう。
3. よくある“つまずきポイント”と対策
退職直後に申請書の記入ミス/証明書の不備で手続きが大幅に遅れる
→「事前に庶務担当や共済組合に申請書の書き方を確認」「見本をもらう」と安心
主治医が多忙で診断書が間に合わない
→「受診予約を早めに取る」
退職後、旧所属とのやり取りが煩雑に…
→「電話やメールで担当者と連絡が取れる体制を作る」「退職時にお礼と共に今後の連絡方法を伝えておく」
4. 退職後の「生活再建」を考えた相談・準備
傷病手当金は最長1年6か月しか受給できません。
「その後どうするか」「障害年金や転職、就労支援なども視野に入れる」ことが重要です。
精神的・経済的な不安を一人で抱え込まず、行政・専門家の支援も使いながら次のステップを計画しましょう。
5. 退職前にやるべきチェックリスト
庶務担当と退職後の申請フローを確認したか
申請書・診断書を十分にもらい、控えも取ったか
主治医と診断内容・証明内容を打ち合わせたか
共済組合のルールや連絡先をメモしたか
退職後も生活を維持するための公的支援・相談先を調べたか
傷病手当金で困ったらプロに無料相談!退職コンシェルジュ等の活用法・具体例

1. 傷病手当金は「自己流」で悩まず、プロに頼るのが正解
傷病手当金の申請や退職後の受給は、
書類の準備が多い
職場や医師・共済組合とのやり取りが複雑
自分の症状やケースが「制度に該当するのか」判断しづらい
…など、“自己流でやると不安や手間が大きい”のが現実です。
2. プロ(社労士や退職コンシェルジュ)に相談するメリット
◎ 最新情報や制度の細かな解釈に強い
制度改正や自治体ごとのルール差もカバーしてくれる
「自分の症状や退職理由で本当に受給できるのか?」を的確に判断
◎ 面倒な書類作成・記入もサポート
「申請書のどこをどう書けばいいか」「医師にどう頼めばいいか」など、細かいポイントまでアドバイス
ミスや不備で手戻りが発生しづらい
◎ 申請後のトラブル・不支給時の再申請にも対応
「共済組合との交渉が難航した」
「不支給通知が届いたけど、異議申し立てしたい」
そんな場面もプロの助言があると“解決率”がまったく違う
3. 退職コンシェルジュ等の無料相談はどう活用する?
【利用の流れ】
無料個別相談をネットや電話で申し込む
退職コンシェルジュなど、多くのサービスは公式サイトから申し込み可能
初回は無料、無理な勧誘は基本なし
自分の症状や退職理由、過去の経緯をざっくばらんに伝える
今の不安・困っていること・申請状況を説明
「こういう場合どうなる?」など細かい疑問もOK
プロが「受給の可能性」や「今後やるべきこと」を整理・提案してくれる
必要書類の揃え方、申請手順、医師への頼み方など、すぐ実践できるアドバイスがもらえる
場合によってはそのまま有料サポートや書類作成代行を頼むこともできる
もし受給できなかった場合は「全額返金」のケースも
たとえば退職コンシェルジュは「給付金が出なかった場合は全額返金保証」があるので、リスクゼロで頼れる
4. どんな人にプロ相談をおすすめしたい?
退職後、受給条件や申請フローが不安な方
「複雑な状況」(転職・転居・長期療養・公務員→民間など)で受給できるか自信がない方
書類作成や共済組合とのやりとりでつまずいている方
障害年金など他制度との併用や切り替えを考えている方
不支給・減額通知が届いた方(再申請や異議申し立てを検討している方)
5. 利用者のリアルな体験談・サポート内容の例
【サービスを受けた利用者の例】
前職:研究開発
退職理由:精神的にも体力的にもきつく「適応障害」と診断されたため
現在までの受給期間:約10カ月間
現在までの受給金額:合計170万円(毎月17万円)
前職:外資系企業の営業
退職理由:人間関係と営業売上のプレッシャーから体調不良になったため
現在までの受給期間:約6カ月間
現在までの受給金額:合計156万円(毎月26万円)
前職:看護師
退職理由:心身の体調不良のため
前職の月収:26~30万円
現在までの受給金額:約81~200万円
6. 無料相談サービスの利用のしかた
「傷病手当金 無料相談」や「退職コンシェルジュ」とネット検索して公式ページから申し込み
不安な点や疑問点をリストアップしておくと、相談がスムーズ
サービス利用前に「全額返金保証」や「初回無料」などの条件もチェックしておきましょう
一人で悩まず、必ず専門家に相談!
「これって受給できるのかな?」と迷ったら、まずは無料相談を活用してみてください。
正しい制度利用は“あなたの権利”です。
気になる方は↓
まとめ|傷病手当金を最大限活用して人生を立て直そう
公務員として働いていると、「まさか自分が体調を崩して働けなくなるなんて…」「退職したら収入がゼロでどうしよう…」と、不安や焦りを抱くのは決して珍しいことではありません。
しかし、傷病手当金は“公務員の権利”として用意された生活再建の強い味方です。
在職中はもちろん、退職後でも条件さえ満たせば1年6カ月もの間、給料のおよそ2/3が支給されるというのは非常に大きなセーフティネットになります。
傷病手当金を活用して「人生の再スタート」を切ろう
体調が悪いときに「お金の不安」が減るだけで、治療や療養にも余裕が生まれます。
受給の権利を“知らなかったから”使わなかった、というのは本当にもったいないこと。
自分自身や家族のためにも、「申請しない」という選択肢はありません。
まずは今できること(職場・主治医・共済組合への相談、書類準備)から行動しましょう。
よくある落とし穴と対策
「退職後でも受給できること」を知らず、手続きをしなかった
→退職前に必ず確認・準備。さかのぼって申請できる場合もあるので、迷ったら早めに相談!
申請書や診断書の不備で給付が遅れる
→主治医・庶務担当・共済組合に細かく確認。コピーも忘れずに!
自己判断で“働けそうだから”と無理に復職→支給停止・体調悪化
→復職や就労再開は必ず主治医・専門家と相談してから!
「申請するか悩んだら、まず相談」が鉄則!
自分だけで悩まないで大丈夫!
共済組合や専門家の無料相談を積極的に使いましょう。失敗やトラブルの多くは「知らない」「相談しなかった」が原因です。
執筆者からひとこと
最後までお読みいただきありがとうございます。
私自身も体調不良で退職し、不安の中で傷病手当金に救われた経験があります。
「こんな制度があったんだ」と気づいて行動できる人が一人でも増え、人生の再スタートに役立つことを心から願っています。
【関連記事】
- 【公務員】うつ病発症から休職、復職までの流れ。休職できる期間と給与は?
- 【公務員】うつ病で退職を考えている人へ。おすすめの1人で稼げる働き方25選。
- 国家公務員・地方公務員の退職金ってどのくらい?(定年退職・自己都合の場合)
【参考サイト・書籍】
