「公務員試験で林業職を受けようか迷っているけど、実際にどんな仕事をしているの?現場のリアルな声が知りたい!」
そんな悩みや疑問を持つ方は多いはずです。
林業職公務員(県庁・自治体職員)は、大学で農学や生態学を学んだ方だけでなく、森林や自然に興味のある多くの受験生から人気が高い職種。
しかし、「林業公務員=木こり」や「毎日山で作業する仕事」というイメージを持っている方も少なくありません。
- 実際はどんな仕事を任され、どんな部署に配属されるのか?
- 事務仕事と現場作業のバランスは?
- 大学で学んだ知識はどこまで活かせるのか?
- 働く上でのやりがいや大変な点、本音で語ってほしい!
こうした悩み・疑問に、元県庁林業職員として約9年の現場経験をもとに、徹底的に解説します。
この記事を書いた人

林業職公務員の主な配属先と異動パターン

林業職はどの部署で働く?リアルな配属例と異動の実態
林業職公務員として採用されると、最初はどこに配属されるのか、どんな部署でキャリアをスタートするのか——これは受験生にとって非常に気になるポイントですよね。
林業職の配属先は大きく分けて以下のようなパターンがあります。
1. 県庁の林業関係部署(林務部・環境部など)
県庁本庁には林業行政を担当する「林務部」や、森林保全・自然環境を所管する「環境部」などがあり、林業職公務員が配置されています。
ただし、新人でいきなり県庁配属になることはごく一部。
多くは「現場経験」を積むため、最初は現地機関からスタートするケースが大半です。
2. 現地機関(地域振興局など)
ほとんどの林業職公務員は、まずこの現地機関でキャリアをスタートします。
ここでは、森林の管理、間伐・造林事業、治山事業の設計や監督、補助金の審査・現地調査、地元との調整など、林業現場の“最前線”を支える仕事に幅広く携わることになります。
まずは現地機関で働き、上司から学びながら技術や知識を習得するケースが多いです。
3. 林業大学校・林業試験場
林業人材の育成や、森林技術の研究開発を担う「林業大学校」「林業試験場」でも林業職公務員が活躍しています。
ここでは、研修運営や調査研究、普及指導など、やや専門色の強い業務が中心となります。
4. 林野庁(国の出先機関)への出向
キャリアを重ねて部内で一定の実績を積むと、「林野庁」など国の機関への出向を経験する人もいます。
出向はキャリア形成のステップの一つで、国の政策づくりや大規模プロジェクトに関わるチャンスもあります。
現地機関でしっかり専門知識を習得しておかないと、県庁の部署に配属になったときに役に立たない人材になってしまうので、現地機関でしっかり修行を積むことが大切です。
なかにはいきなり県庁で働くことになる新人職員もいると思いますが、林業職ではごく一部の人です。
配属・異動の基本パターン
林業職は「数年ごとに異動」が原則。
だいたい3~4年ごとに現地機関や県庁、林業大学校、研究機関などを異動していきます。
「県庁→県庁」「現地→県庁」「県庁→現地」「研究機関への異動」など、多様なキャリアパスが用意されています。
【注意ポイント】
希望の配属先や業務に必ず就けるとは限りません。配属は人員配置や部内事情、本人のキャリア形成を考慮して決まります。
大学で生態学や野生動植物学を専攻していても、最初は森林整備や補助金業務の部署になる可能性が高いです。
林業職公務員の主な仕事内容と1日の流れ

林業職の仕事は多岐にわたる!主な業務の全体像
林業職公務員の仕事は、単なる“森林の管理”にとどまりません。
配属先や担当によって仕事内容が大きく変わるのが特徴で、「現場系」と「事務系」が混在する技術職ならではのダイナミックさがあります。
【主な業務カテゴリ】
| 項目 | 業務内容 |
|---|---|
| 林業の振興 | 林業雇用対策、林業経営支援、県産材利用促進など |
| 森林の整備保全 | 間伐等の森林整備の推進など |
| 林業の普及指導 | 林業知識技術の指導や普及など |
| 県営林管理 | 県で所有している山林の管理など |
| 野生鳥獣対策 | 野生鳥獣の保護管理、農林業被害等の防除など |
| 治山・林道事業 | 治山や林地荒廃防止のための施設整備の設計・施工管理など |
| 保安林管理 | 保安林に関する指定・解除・許認可事務など |
| 森林林業の試験研究 | 育林・育種、林産物、木材加工、林業技術の試験研究など |
| 自然保護 | 希少野生動物の保護、外来種対策など |
林業職といっても、その仕事の幅はとても広いです。
それぞれの業務で専門的な技術や知識が必要となります。
特に、高度な土木知識が必要になる治山林業事業では、自分1人で設計・現場監督をこなせるようになるまでに3~10年ぐらいの歳月は必要です。
上記の全ての業務を一度に任されるのではなく、上記の項目から1~2つ担当することになります。
業務の中でも細かく仕事が枝分かれしているので、係員ごとにさらに細分化されます。
私の具体的な仕事内容(経験談)
私は林業職として入庁し、約8年以上働いてきました。
- 1~3年目(現地機関) 県営林の経営管理、造林事業(補助金)、木造事業(補助金)、木育、ペレットストーブ
- 4~6年目(現地機関) 治山事業の設計・現場監督、保安林管理
- 7~8年目(県庁) 希少野生動植物の保護、外来種対策、自然保護センターの維持管理
- 9年目(現地機関) 林業普及指導
ここでは1~8年目までの業務経験をざっくり紹介します。
【1~3年目】 県営林の経営管理、造林事業(補助金)など
【4~6年目】(1回目の異動) 治山事業の設計・現場監督、保安林管理など
【7~8年目】(2回目の異動) 希少野生動植物の保護など
【1~3年目】県営林の経営管理、造林事業(補助金)など
大学で生態学を学んでいたので野生鳥獣対策を希望して入庁しましたが、初めての仕事は地域振興局(現地機関)での「県営林管理」などでした。
具体的には県で所有している山の管理をする仕事で、
- 森林整備や林道維持管理の設計・現場監督
- 林産物の処分
- 試験調査
- 境界管理
などを行いました。
大学で林業を詳しく習わずに入庁したため、初めは林業の基本も全然分からずなかなかハードな状態でした。
ただ、1年も経ってくれば慣れてきて、それなりに一人で業務をこなせるようにもなってきました。
2~3年目には県営林管理に併せて、「造林事業の補助金」なども担当しました。
各森林整備を行った事業体が補助金申請をしてくるので、それの審査・支給を行いましたが、その申請量が半端でなく、残業の日々が始まりました。
仕事が間に合っていないときは、土日も出勤して対応していました。
【4~6年目】(1回目の異動)治山事業の設計・現場監督、保安林管理など
異動となり、4~6年目は地域振興局(現地機関)で治山事業と保安林の担当となりました。
【主な業務内容】
- 治山ダム・山腹工・森林整備の設計、発注、現場監督
- 保安林の許認可業務
治山事業では本格的に土木知識が必要となります。
異動した先でいきなり「治山ダムを設計してくれ」「現場に行って調査測量してきて」といわれたときの衝撃は今でも忘れません。
そもそも治山ダムがどんなものも分かっていなかったし、大学でも土木関係は全く習っていなかったにもかかわらず、異動先でいきなり治山ダムの設計や現場監督を任され、まさにカルチャーショック状態でした。
上司に叱咤激励を受けながら教えを請い、そして夜中まで土木の勉強を続ける日々を送りました。
「私は野生鳥獣の関係の仕事がしたくて入庁したのに、なんでコンクリート相手に仕事をしているんだろう」と仕事の内容にギャップを感じる日々でした。。。
【7~8年目】(2回目の異動)希少野生動植物の保護など
2回目の異動で、初めて大学の知識(生態学)が役立てそうな自然保護関係の部署(県庁)に異動することができました。
【主な業務内容】
- 生物多様性の保全に関わる諸般のこと
- 希少野生動植物の保護管理計画の策定
- 希少野生動植物の保護活動
- レッドデータブックの管理
- 外来種対策
しかし、業務を始めてみると、大学のころに学んだ知識はあまり役立たないことが分かり、大変失望しました。
計画を策定する際、専門的な部分は大学教授などに教えを請う形になるので、自分の知識は全く施策には活かせませんでした。
自分の考えで施策を考えていくというよりは、教授や専門家を集めて開催される専門委員会で県の指針や施策を決めていくので、公務員はその事務処理(裏方)に奔走します。
裏方の仕事とは、
- 教授たちの日程調整
- 教授たちへの謝礼や旅費の計算
- 議事録作成
- 当日の司会進行
- 会場の手配
- 事務局案(たたき台)
- 根回し
などが主な仕事になります。
事務局案も考えますが、それも教授や専門家頼みのところが多いです。
(もちろん課内でも意見を出し合い練りに練ります)
また、初めて県庁への異動となりましたが、現地機関とは仕事の量と質ともに桁違いの大変さでした。
林業職公務員の1日の流れ(繁忙期の例)
参考までにですが、私の県庁時代のとある1日(ちょっと多忙期)を時系列でご紹介します。
| 時間 | 仕事内容 |
|---|---|
| 6時 | 始発バスで早朝出勤。 |
| 7時 | 朝一でメールをチェックすると県民から問い合わせあり。 特別な内容だったので、回答案を作成し、上司・係長・課長・広報担当管理職にそれぞれ回答内容を説明、決裁をもらう必要あり。 |
| 8時 | 業務開始前に新聞をチェックし、自分の課に関係する記事を探しその部分をコピーして課長へ渡す。 |
| 9時 | 前任者がやっとの思いで完成させた県発行の図書1000冊以上を納品。 しかし知事の挨拶ページが抜けていたことが判明、課長イライラ、どうするんだと対応求められ困窮。 |
| 10時 | 県管理施設修繕工事の関係で業者が来庁、一部設計通りに行かない部分が生じ、変更設計を作成することに。 |
| 11時 | 県庁内の担当課から自然保護センターの耐震化に関するヒアリングを受ける。 |
| 11時半 | 毎週やってくるクレーマーが来庁、対応に苦慮。 |
| 12時 | 省エネのため電気が消された暗い課内で出前弁当を食べながら、朝の問い合わせの回答案を作成。 |
| 13時 | 県が作成する希少野生動植物保護管理計画のための専門委員会を開催。 大学教授や専門家などで構成される委員会で県側のたたき台を提示し、様々な意見を頂戴する。 |
| 17時 | 委員会が終わったあとは教授たちと慰労会をするため、一度職場をでる。 慰労会の手配も係員の役目。 |
| 21時 | その後、慰労会が終わったあと職場に戻り、数日後に開催される現地機関の職員への業務説明会の発表資料を作成。 朝の問い合わせの回答案は係長からダメ出しされ机の上に戻ってきている。 今日は結局溜まっていた仕事は全然処理できず。土日にやるしかない。 |
| 0時 | 自費でタクシー帰り。 |
| 1時 | 持ち帰り残業(地元説明会の議事録)を作成。 |
| 3時ころ | 就寝。 |
林業職は木こりじゃない?よくある誤解と本当の役割

林業職=山に入って木を切る?実は“管理・調整”が主なミッション
「林業職公務員」と聞くと、「毎日山に入って木を切っている」「チェーンソーで伐採作業をしている」といったイメージを持たれる方も多いかもしれません。
しかし、林業職公務員の本当の仕事は、現場作業員(木こり)とは大きく異なります。
林業職公務員の仕事は、主に以下のようなものです。
森林整備や林道建設などの計画立案・設計・発注
事業者(実際に作業する林業会社等)への技術指導・助言
補助金交付の審査・現地調査・現場監督
森林所有者や地域住民との調整・相談窓口
自然環境保全のための行政手続きや規制管理
関係機関(大学・試験場・専門家)との連携・調整役
つまり「自分がチェーンソーで伐る」「重機で間伐する」というよりも、“現場の総合マネージャー”として森林・林業・地域をつなぐ役割が大きいのです。
事務仕事がメイン、でも“現場を知らずに机上だけ”では務まらない
配属や時期によりますが、林業職公務員は事務所での書類作成や会議、発注業務や設計業務が主な日常です。
補助金関連の膨大な申請書類処理
予算執行や決算対応
会議の資料作成や議事録
上司・専門家・業者・住民との調整
ただし「現場を知らないと机上の空論」になりがちなので、週2~3回は山林へ現地確認や調査に出るのも一般的。
また繁忙期やトラブル対応では毎日現場へ…ということも少なくありません。
こんな人は要注意!林業職公務員が“向かない”タイプ
「自然の中で体を使って毎日働きたい!」→ 現場作業員(木こり)向き
「とにかくフィールドワークがやりたい」→ 研究職や民間林業会社が合う可能性
「現場の泥臭さ・地元調整が苦手」→ 林業職は意外と“人間関係”も多い仕事です
林業職公務員のキャリアパス・出向・昇進例
林業職公務員は、民間の林業会社や現場職とは異なり、「行政ならではのキャリア形成」や「多様な異動」「昇進コース」が特徴です。
入庁してからどのような成長や選択肢があるのか、具体的に見ていきましょう。
1. 入庁~数年は“現場力”重視
ほとんどの新人林業職公務員は、まず現地機関で森林管理・補助金業務・治山事業の現場を経験します。
この時期は現場感覚・地元との調整力・林業行政の基礎知識を身につける大切な期間です。
2. “県庁本庁”や“研究・教育機関”でスキルアップ
経験を積むと、県庁本庁(林務部や環境部)に異動する機会も増えてきます。
ここでは委員会運営・予算管理・新規事業の企画立案・専門家との調整など、マネジメント力や調整力、政策づくりの視点が鍛えられます。
3. 国の機関(林野庁など)への出向やリーダーポスト
キャリアを積むと、国の林業行政に関わる「林野庁」や場合によっては他府県への“出向”も選択肢となります。
出向先では、より広域的な政策や大規模プロジェクト、林業施策の調整など“上位レベル”の行政運営を学ぶことができます。
昇進モデルの一例(県庁の場合)
- 技師
主任(主任技師など)
- 主査
担当係長
- 係長
課長補佐
課長(現地機関)
- 課長(本庁)
部長級(林務部長など)
昇進は年功や勤務評価だけでなく、「現場・本庁・出向」と多様な経験を積むことが重視されます。
管理職になると、組織の運営や大規模事業のマネジメントも重要なミッションです。
4. “自分らしい”キャリアを描くヒント
現場に根ざして地元密着型で働く道
行政の企画・制度づくりに関わる道
研究・教育機関で専門性を極める道
出向や交流で新しい分野やスキルを身につける道
「林業公務員=決まったコース」ではなく、自分の強みや興味を活かして柔軟にキャリアを広げられるのが行政技術職ならではのメリットです。
大学で学んだ知識は役立つ?理想と現実のギャップ
「大学で生態学や林業を学んだから、即戦力として活躍できるはず…」は本当か?
林業職公務員を目指す多くの方が「大学で学んだ森林科学・生態学・土木などの専門知識を現場で活かしたい!」と期待しています。
実際に受験生からよくある質問として、
「大学での勉強がどれだけ仕事で役立ちますか?」
「自分の得意分野を活かせる配属になるのでしょうか?」
といった声をよく聞きます。
しかし、現場で求められる知識やスキルと、大学で学ぶ“アカデミックな知識”は、想像以上にギャップがあります。
実際に役立つ知識・ギャップを感じやすいポイント
役立つケース
基礎的な森林・生態学、土壌・植生・林業技術の理解
→ 調査現場や基礎的な業務で「専門用語や仕組みをすぐ理解できる」アドバンテージになる統計・GIS・測量・法令知識
→ 調査データの集計や現場地図の作成、許認可の根拠理解などで強みになる
ギャップを感じやすい現実
配属・担当は希望通りにならないことが多い
→ 野生動物や自然保護をやりたくても、最初は森林整備や治山工事の現場、補助金業務がメイン土木・建設・補助金・行政手続き…“実務系”知識が圧倒的に不足しがち
→ 書類の作り方、調整・交渉、現場での土木技術など、大学では習わなかったことばかり
なぜ理想と現実にズレが生じるのか?
配属は「組織都合」や「キャリア形成重視」で決まる
林業職公務員の配属や業務は、個人の希望や専攻よりも「現場の人員バランス」「経験値アップ」「部門ごとの人材育成計画」によって決まります。
そのため「専門を活かせる部署に最初から配属される」ことは実は少数派です。
行政には「幅広い分野への対応力・調整力」が必要
現場では、森林・林業だけでなく土木や環境、時には建設・住民対応まで多様な分野と関わります。
大学時代の“深い専門性”よりも「幅広い知識」と「現場で学び続ける柔軟性」「チームで仕事を進める調整力」がより重要視されるのです。
それでも大学での学びが“無駄”になることはない
たとえ最初は直接的に活かせなくても、「専門知識のベースがある」「専門家との会議で話が理解できる」「勉強する習慣がある」という点は大きな強みです。
また異動を重ねていく中で、必ずどこかで自分の得意分野が“活きる瞬間”がやってきます。
やりがい・大変なこと・本音体験談
林業職公務員の“やりがい”はどこにある?
林業職公務員の仕事には、民間企業や他の公務員職にはない独自のやりがいがあります。
「森林・地域の未来を守る」「自然と人をつなぐ」「現場から社会課題の解決に貢献できる」——この想いに共感できる人には、かけがえのない経験が積める仕事です。
1. 地域・森林への直接的な貢献を実感できる
森林整備や治山工事を通じて、災害防止や環境保全に役立てる
県産材の活用や林業振興で地元産業を支える
野生動植物保護や生物多様性の維持に最前線で関わる
2. 現場と行政、地域と専門家をつなぐ“調整役”としての達成感
現場職員、地元住民、事業者、専門家など、多様な人と協力して一つのプロジェクトを動かす
“調整ごと”が大変な分、うまくまとまった時の達成感も大きい
3. 多岐にわたる分野・業務を経験できる
森林・環境・土木・野生動物・教育・研究…とにかく幅広い分野を担当できる
一つの部署・担当にとどまらず、数年ごとの異動で自分の可能性を拡げられる
林業職公務員の“しんどい”ところ・本音で語る苦労
1. 書類・事務作業の膨大さと“現場とデスクワークの両立”
補助金申請・審査、設計図面、行政手続き…「山よりパソコンに向かう時間」のほうが長いことも多い
山→役所→現場→事務所と“移動”が多く、繁忙期は残業・休日出勤も発生しやすい
2. 配属や担当が思い通りにならない“理想と現実のギャップ”
希望の部署・業務に就けるとは限らず、全く畑違いの仕事を担当することも
専門分野が活かせるまで何年もかかる場合も珍しくない
3. 地元・住民・関係者との調整の難しさ
現場では“行政=敵”と見られることもあり、説明や根回しに神経を使う
住民クレームや合意形成、時には板挟みになることも
それでも“この仕事を選んでよかった”と思う瞬間
苦労も多い林業職公務員ですが、自然・地域の未来に貢献し、多様な専門家・現場・地域と関われるのは大きな魅力です。
日々の仕事の中で「自分の成長」「誰かの役に立つ喜び」を実感できることこそが、この仕事の最大の報酬だと言えるでしょう。
林業職公務員に向いている人・向いていない人
向いている人の特徴
林業職公務員は、“自然が好き”“地域の役に立ちたい”という動機だけでなく、多様な適性や心構えが求められる仕事です。
どんな人が林業職公務員で活躍しやすいのか、主な特徴をまとめました。
1. 現場と事務、両方のバランスを楽しめる人
山林調査や住民対応など“現場仕事”が好き
書類作成や調整業務も前向きに取り組める
「体も頭も使いたい」「多様なスキルを身につけたい」タイプ
2. 幅広い知識や新しい分野を学ぶ柔軟性がある人
配属先や担当業務がコロコロ変わることを前向きに捉えられる
「知らないことも勉強すればOK」「どんな経験も自分の糧になる」と考えられる
新しい技術や法令、地域の事情も自主的に学ぶ姿勢
3. 調整力・コミュニケーション力を発揮したい人
地元住民や事業者、同僚、上司、専門家など、多様な人との連携が苦にならない
対立や板挟みになっても、冷静に話し合える
「人と自然」「現場と行政」をつなぐ役割にやりがいを感じる
4. 忍耐力・継続力がある人
すぐに結果が出なくてもコツコツ続けられる
目の前の仕事を一つひとつ地道に積み重ねられる
失敗や苦労も「成長の糧」と前向きに捉えられる
向いていない人の特徴
林業職公務員のリアルは「自然と触れ合う夢の仕事」というより、行政の論理や“泥臭い現場対応”も多い現実的な職種です。
下記のようなタイプはミスマッチを感じやすいかもしれません。
1. 毎日フィールドワーク中心で働きたい人
「現場に出て体を動かす仕事だけしたい」という人
事務処理や書類仕事が苦手・嫌いな人
2. 配属や担当が希望通りにならないと納得できない人
「自分の専門分野だけやりたい」という強いこだわりがある人
異動や新しい分野に興味が持てない人
3. 人間関係や調整ごとにストレスを感じやすい人
対立やクレーム対応が苦手
地元調整や行政手続きを“面倒くさい”と感じてしまう人
4. ルーティンワークを好む人
一定のパターン・同じ作業を淡々と続けたい人
毎日違う業務や突発的な仕事にストレスを感じる人
自己分析のすすめ
林業職公務員を目指す方は、「なぜ林業をやりたいのか」「自分のどんな性格・価値観が活きるのか」「苦手なこともチャレンジできるか」をじっくり自己分析してみてください。
実際の現場の声や体験談をもとにイメージを深めることで、ミスマッチのない進路選択がしやすくなります。
Q&A・林業職公務員によくある質問・悩み相談
Q1. 林業職公務員の“将来性”は?これからも需要はある?
A.
森林資源の管理や山林の災害対策、環境保全への社会的ニーズが年々高まっています。
今後も「森を守る」「地域を支える」行政の担い手として林業職公務員の役割はますます重要になります。
SDGsや脱炭素政策、バイオマス利用など新しい領域にも活躍の場が拡大しています。
Q2. 大学の専門が林業と違っていても受験できますか?
A.
多くの自治体で「農学系」「理学系」「土木・建築系」など幅広い理系出身者が林業職を受験しています。
実際に、入庁後に知識を身につけながら活躍している職員もたくさんいます。
大切なのは「学び続ける意欲」と「幅広い仕事にチャレンジする姿勢」です。
Q3. 女性でも働きやすい職場ですか?
A.
女性の林業職公務員もたくさんいます。
現場調査・工事監督から自然保護・研究、行政企画まで多様なフィールドで女性職員が活躍中。
産休・育休制度や働き方改革も進み、仕事と家庭を両立しやすい職場が増えています。
Q4. 林業公務員と「木こり」や林業会社の仕事は何が違う?
A.
林業職公務員は「現場作業員」ではなく、事業発注・補助金支給・指導監督・施策立案など、“管理・調整・行政”の立場です。
現場作業を担うのは民間の林業会社や森林所有者。
どちらも森づくりに不可欠な存在ですが、役割・働き方が根本的に異なります。
Q5. 配属や異動はどこまで希望が通りますか?
A.
原則として人員配置や組織事情、キャリア形成を重視して配属・異動が決まります。
最初は希望外の部署になることも多いですが、経験を重ねることで徐々に自分のやりたい分野に近づける場合も。
幅広い経験を積むことで将来の可能性も広がります。
Q6. 民間企業(林業会社等)との違いやメリット・デメリットは?
A.
民間の林業会社は「森林作業」「施業計画の実行」がメイン、行政公務員は「森林・林業全体を調整し、社会全体の利益や制度を守る」立場です。
公務員は安定した雇用や福利厚生、幅広い業務を経験できる反面、異動・事務作業や調整業務の多さなど独特の大変さもあります。
まとめ|林業職公務員は「森の未来を守る」社会的使命と多彩なキャリアが魅力
本記事では「公務員 林業」「公務員 林業 仕事内容」で検索した受験生・学生に向けて、仕事内容・配属・1日の流れ・キャリアパス・リアルなやりがいと苦労まで網羅的に解説しました。
林業職公務員は“木こり”や現場作業員とは違い、管理・調整・行政運営が主な役割
配属や担当業務は幅広く、現場と事務のバランス、多様な異動・キャリア形成がある
書類や調整など大変な面もあるが、森林・地域・社会に貢献できるやりがいは大きい
「自然が好き」「地域の役に立ちたい」だけでなく、自己成長や柔軟性も求められる
進路選択では、“理想と現実のギャップ”も事前にしっかり理解しておくことが重要
林業職公務員は、森と人・地域社会をつなぎ、「これからの時代にますます必要とされる技術系公務員」。
ぜひ幅広い視野と柔軟な気持ちで、自分の将来像を描いてください。
私が林業職を希望する受験生に強く言っておきたいことは、
「配属先や業務は希望通りにはならない」と「大学で習ったことはそこまで役立たない」
ということです。
特に、大学時代に生態学や野生動植物学などを専攻していた人たちは、野生鳥獣関係の仕事をやりたくても、森林整備や治山工事の部署に行く可能性が十分あります。
その仕事内容のギャップに耐えられるか、あらかじめよく考えて林業職を志望してください。
正直に話すと、私も大学時代林業職公務員を受験するかすごく迷いました。迷った際に、すでに林業職公務員として働いている大学の先輩に相談したところ、「野生動物の部署に配属されるか分からないからおすすめできない」と言われました。そのときはとにかく公務員になれればいいやと思っていたので、アドバイスを無視する形となってしまいましたが、今振り返ると「もっと先輩のアドバイスに耳を傾け、広い視野で職業選択をすべきだった」と後悔しています。
公務員になれれば仕事内容はなんでもいいよって人は、行政職での受験も十分可能です。
【いますぐできるアクション例】
自治体の林業職・森林行政の採用ページや現役職員インタビューを読んでみる
公務員試験の林業職・専門職ガイドブックを取り寄せる
実際に林業職で働く人の体験談やSNSをチェック
迷いがあればココナラなどの相談サービスや現役・元林業職公務員に質問してみる
迷ったときは「現場の声」を集め、自分に合った働き方・キャリアをじっくり考えてみてください。
【林業職の参考書】
林業職の専門試験の勉強方法や面接対策を詳しく知りたい方は、下記の書籍が役立つので参考にしてみてください!
首席合格の元県職員が書いた【公務員試験「林業職」大全】~専門試験・面接試験編~
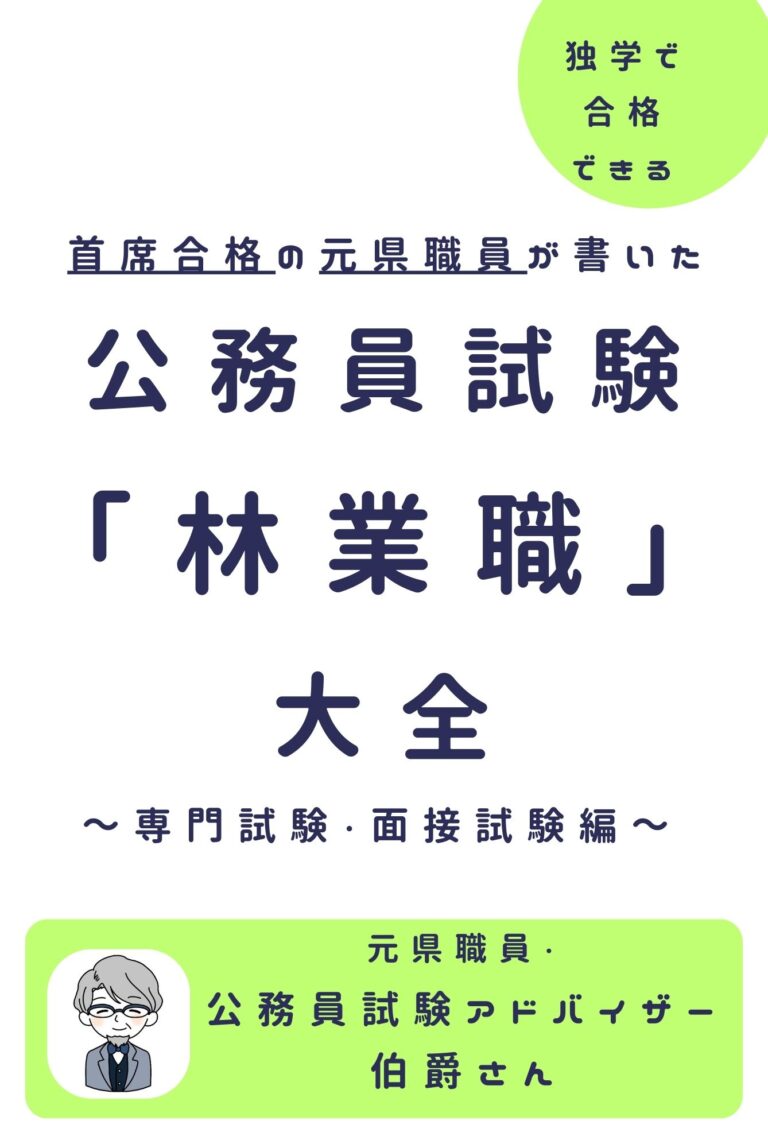
【林業職に関するなんでも相談】
林業職や公務員試験に関する悩みごとや困っていること、なんでも相談してください。
私がチャットで丁寧にお答えします。
【関連記事】
